あの土曜日の朝、OEMは危機管理室に駆け込んでグレートマシーンを起動した。われわれは地方の公選役人と力になってくれそうな人たちをそれに接続させた。数時間のうちに地域のコミュニティグループである中国統合慈善協会とともに家族支援センターを設立した。
悲惨な衝突現場の写真が放送電波と市内に満ちた。中でも結びつきの強いチャイナタウンの近隣への影響は深刻であった。その日のうちに家族支援センターはモットストリートの中国コミュニティセンターで開所された。スタッフは保健福祉省や赤十字などの災害救助の機関を含む政府機関の代表たちだった。
乗客名簿のない運行だったので、誰が家族なのか分からず、地元のメディアやソーシャルメディアと協力して家族支援センターの活動範囲を遠くへ広げる努力をした。家族の一員が乗っていた、あるいはその可能性があると思う人は誰でも出てきてほしかった。
その日のうちに、家族はやってきた、他に何をするべきかが分からないので、多くの家族がやってきた。中国コミュニティセンターの講堂は彼らでいっぱいになった。ぼんやりとして言葉もなく立ち尽くす人、公選役人や中国統合慈善協会のスタッフと話をする人がいた。
講堂内の周囲には市の機関、慈善団体、ボランティア団体の横断幕を掲げたテーブルが並べられた。金銭支援、住居、法律相談、移住支援、保険相談、動物ケアの支援などのサービスを提供するものだった。初日にあまりに忙しかったので、危機管理室の任務チームのスタッフは、オペレーションを10日あるいはそれ以上延長するための計画を完成させるのに精を出した。
翌日までに何かが変わっていた。講堂は静かだった。家族は正式の説明会には参加したが、講堂には戻ってこなかった。家族支援センターのスタッフはほとんどの時間を仲間内での話で過ごした。
やってきた人たちは現場へ行きたいと言い続けた。こうした状況においては珍しくない要望であるが、丘の斜面に切り開かれた高速道路の、急カーブの端にある交通量の多い直線コースに沿った危険な現場であった。われわれはそのアイデアを話し合ったが、そのための人の輸送は複雑すぎるとの結論になった。家族の安全を確保できるか自信がなかったので、家族支援センターには最後までがんばるよう申し入れた。その間、私は何が起きているかを知るために人混みで混雑した迷路のようなチャイナタウンの通りへ思い切って出て行った。
中国コミュニティセンターの”講堂“は陰気なリノリウムの床と低い白色タイルの天井板からなる大会議室だった。私が着いたときは、何家族かの人たちがいたが、彼らの方へ向かって行くことはできなかった。しばらくして、明るい白色の襟のついたネイビーブルーのスウェットシャツを着た感じのよいグループに近づいていった。慈済基金会のボランティアだった。われわれは台湾を本拠とする仏教系の国際人道救済機関である慈済基金会とは過去に何度も一緒に仕事をしたことがある。事務処理が簡単で現金を供与するので中国コミュニティでは人気がある。
慈済基金会は家族と何時間も過ごしていた。ボランティアの一人、背が高くて目立つ香港生まれのヘンリー・チューがわたしをわきへ連れ出した。彼が言うことには母親たちは大きなストレスを受けている。それは子供たちが死亡しただけではなく、その“死に方”によるものだとのこと。仏教の伝統に従えば、衝突の激烈さが魂を害してしまったのだ。最期の瞬間の突然の暴力はその魂を“餓鬼(怨念に駆られて死に場所をさまようことを運命づけられた奇妙な獣)”にした。家族とともにいた仏教僧によれば、愛する者の魂は路傍で囚われており、葬儀のみがそれを解き放つことができるとのこと。
それから彼はわれわれがすでに知っていることを言った。家族支援センターのスタッフがそのことに当惑しているということだ。同様に家族も、小口融資、寸法違いのトレーニングウエア、彼らにとっては何の意味もないアドバイスがいっぱいのパンフレットなど、家族支援センターでの”援助“に当惑していた。「現時点で家族支援センターを開けておくのは時間の無駄のようです」とヘンリーは言った。「ここには家族のためのものは何もありません。彼らが望んでいる唯一のことは、現場へ、高速道路の現場へ戻ることです」。
















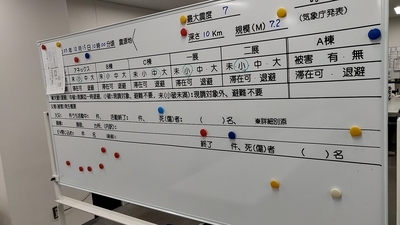




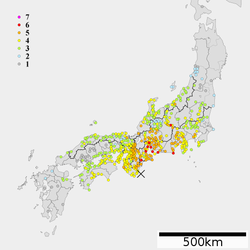







![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






![危機管理2022[特別版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/f/6/160wm/img_f648c41c9ab3efa47e42de691aa7a2dc215249.png)
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方