
残された課題と教訓
新型コロナウイルスの世界的感染拡大が始まって3年。国民の命と生活を守るためにさまざまな政策を打ってきた各国・各地域が徐々に関連規制の緩和、撤廃を始めている。日本政府も感染症法上の位置づけを「5類」に移行する方針を決定し、新型コロナ政策は一つの転換点を迎えた。
季節性インフルエンザと同等の扱いになることで、段階的だが、新型コロナも幅広い医療機関で対応が可能になる。緊急事態宣言や入院勧告・指示、感染者や濃厚接触者の外出自粛要請といった行動制限は法的根拠を失い、医療機関や保健所の全数報告もなくなって、感染対策に関する法規制上の縛りは大幅に緩和される見通しだ。
政府による一律の措置がなくなれば、どこまでの感染対策を行うかは個人や企業、組織の判断に委ねられる。厚生労働省の専門家会議は、対策の是非を強要しない配慮のもと、職場や集まりで合意形成することが望ましいとの考え方を示した。危機管理担当者の意見・知見が求められる機会も増えるだろう。
社会はコロナを終わらせることができるのか、どのような課題が残されているのか。専門家のインタビューから探るとともに、新型コロナ発生当初の企業の対応を本紙独自調査から振り返り、事業継続上でネックとなった点や改善が必要な点を整理した。
※本特集は「月刊BCPリーダーズvol.35(2023年2月号)」の記事からお届けします。



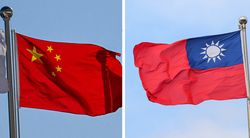















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



