事業を止めるサイバー脅威と対峙せよ
第39回:ERPのリスクとBCP/SPOF対策

林田 朋之
北海道大学大学院修了後、富士通を経て、米シスコシステムズ入社。独立コンサルタントとして企業の IT、情報セキュリティー、危機管理、自然災害、新型インフルエンザ等の BCPコンサルティング業務に携わる。現在はプリンシプル BCP 研究所所長として企業のコンサルティング業務や講演活動を展開。著書に「マルチメディアATMの展望」(日経BP社)など。
2025/10/29
企業を変えるBCP

林田 朋之
北海道大学大学院修了後、富士通を経て、米シスコシステムズ入社。独立コンサルタントとして企業の IT、情報セキュリティー、危機管理、自然災害、新型インフルエンザ等の BCPコンサルティング業務に携わる。現在はプリンシプル BCP 研究所所長として企業のコンサルティング業務や講演活動を展開。著書に「マルチメディアATMの展望」(日経BP社)など。

ランサムウェア攻撃が、本格的に日本の上場企業やそのグループ会社をターゲットにし始めました。攻撃を受けたシステムが長期間復旧せず影響範囲が拡大しているにも関わらず、原因はいまだ調査中という報道に、既視感を覚えるのは筆者だけではないでしょう。これではステークホルダーや取引先からの信用失墜は免れません。
ランサムウェア攻撃に対しては、セキュリティに疎いと言われる日本においても、さすがに上場企業ではそれなりの対策を取っているはずです。しかし、インシデントがこれだけ連続して報道を賑わす状況を見ると、何かが欠けていると思わずを得ません。

サイバー攻撃に対するシステム上の対策として、ネットワークやアクセス制御に関わる脆弱性を排除し、フィッシングメール対策を打つなどしていても、インシデントの発生には、例えば情報システム担当者や情報セキュリティ担当者が極めて少ないなど、運用体制の脆弱性も関係しています。
近年の傾向として、ERP(Enterprise Resource Planning:統合業務システム)のように、業務プロセスを統合し効率的に運用できるとしてシステムの範囲を拡大する企業が増えています。範囲は事業全体に広がり、結果、委託業者(SIerなど)への依存度も高くなります。SIerもライセンス料や保守運用費用が毎年入るわけですから、企業丸抱えでベンダーロックし、長期に渡る太客として手厚いサポートをするでしょう。
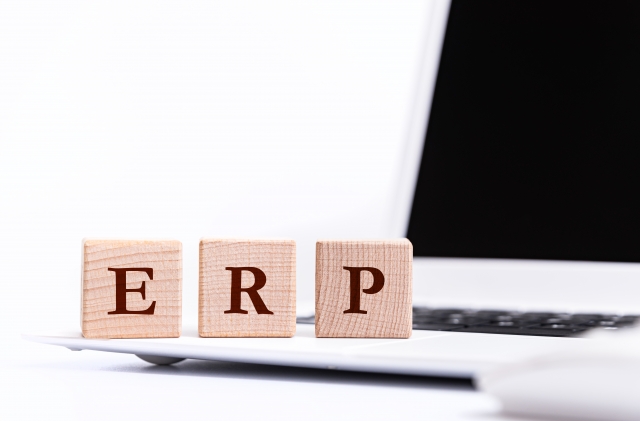
通常ERPは、会計・財務管理、人事・給与管理、販売・購買管理、在庫・物流管理、生産管理(OT)、顧客管理(CRM)などが統合連携され、業務効率が向上すると期待されて導入・展開されます。少ない運用担当者でも委託業者のリモート保守などを通じて何とか運用できていることで、おうおうにしてCIOを含む経営陣はそのリスクに気がつきません。
こうしたシステム運用のなかで欠落していくのが、情報システム担当者や管理職のスキル、開発・導入哲学、業務フローの理解であり、さらにはソフトウェアに内在するセキュリティ対策です。
近年では、セキュリティ対策として開発時にDevSecOps(※デブ・セック・オプス)を組み入れたりしますが、先に述べたような欠落があると、ベンダーが開発したパッケージソフトにセキュリティ的脆弱性が内在していても、検証することなく、言われたままカスタマイズし利用することになります。
※デブ・セック・オプス:ソフトウェアの開発、テスト、デプロイ(システムを稼働可能な本番環境に置くこと)のサイクルを、セキュリティチェックを包含させて高速でまわすスタイル
このような統合型ERPでは、Single Point of failure(SPOF:単一障害点)として、システムのある単一要素にいったん障害が発生すれば、影響範囲も企業の事業全体に及び、トラブルの原因究明も複雑性のために難航し、長期に当該企業の基幹業務が停止となるのは必然です。
企業を変えるBCPの他の記事
おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/01/27


発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26



報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点
ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。
2026/01/26

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン
家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。
2026/01/23



※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方