レジリエンス
-

災害時の人道アクセスを考える
ようこそ、ポッドキャストシリーズ「日本における人道支援のリスク」へ。ホストのジョエル・チャレンダーです。そして今回もチャールズ・マクジルトンさんをお迎えしています。今回は、人道アクセスの在り方を掘り下げます。あなたや、あなたが所属している組織が実際に被災地に立ち向かう方法を見ていきます。アクセスの交渉に関して避けるべき間違いにはどのようなものがあるのか、優先的に考えるには何が大切かを考えていきます。
2025/07/09
-
無電柱化加速へ新目標=緊急輸送道、30年度まで―国交省
国土交通省は、電線を地中に埋めて電柱を撤去する「無電柱化」の加速に向け、新たな目標を設ける方針だ。市街地の緊急輸送道路で2030年度までに工事の完了を目指す区間を、26年度から5年間の次期推進計画に盛り込む。有識者検討会で議論し、来春の取りまとめを目指す。
2025/07/07
-

第12回 社会生態システムにおけるリスクと企業活動
自然保全と社会の発展の両立の関係は単純ではない。人口増加によって、人の居住地域を拡大したり、食糧の確保のために農業や狩猟の生産量の増大が必要となる。そのため社会の境界は拡大し、動植物の生存地域と重なってゆく。この結果、自然の破壊や生態系への攪乱や生息生物の喪失の危機の可能性が起きる。また、この自然と社会との境界が曖昧になってゆくと獣害も発生し、野生動物の保護と獣害からの防衛といったトレードオフを深刻化させる。
2025/07/07
-

成熟するBCPの次なる一手
BCPが複雑化してマニュアル類が成熟、一方、ただでさえ人材不足のBCP事務局は情報量が増えて負荷が増大。この状況を打開すべく期待されるのがAIです。今回は活用シーンの代表例として、訓練シナリオの作成におけるAI技術開発の動きと実際の導入事例を紹介。恒例の企業事例は、経営戦略と連動した攻めのリスクマネジメントを取り上げます。
2025/07/05
-

第4回リスクアドバイザー情報交換会COVID-19の課題振り返りと、新たな感染症への備え~新たなパンデミック発生時の事業継続体制を見直す~
リスクアドバイザーの情報交換会を開催します。
2025/07/02
-
南海トラフ死者、10年で8割減=改定基本計画を決定―「推進地域」は16市町村追加・政府
政府は1日、中央防災会議を開き、南海トラフ地震の防災対策を推進するための改定基本計画を決定した。3月に公表した新たな被害想定で、最大で約29万8000人と見込んだ死者数を今後10年間でおおむね8割減少させる目標を盛り込んだ。
2025/07/01
-
能登の高齢者、医療費急増=災害前の1.1~1.3倍―地震1年半、支援課題に
能登半島地震の被災地で、高齢者1人当たりの医療費が急増していることが、石川県後期高齢者医療広域連合への取材で分かった。地震発生から1日で1年半。復興が長期化する中で心身に不調を抱える人が増え、どう支援体制を築くかが課題となっている。
2025/07/01
-
災害用キッチンカー、平時も活用=自治体所有、普段使われにくく―内閣府
内閣府は、自治体が所有する非常時用のキッチンカーについて、平時も活用する方法を研究する。災害が起きた際は被災者に温かい食事を提供できるが、普段は使われず、維持管理費が膨らむケースも考えられる。そこで、事業者への貸し出しなどを通じ、街のにぎわいづくりに一役買いつつ、維持費を出してもらう仕組みを想定。
2025/06/30
-
自治体の災害ごみ対応で支援機関=経験ない業務、迅速に―環境省検討
環境省は、巨大地震や集中豪雨で被災した自治体が実施する災害ごみ対応を支援するため、専門の機関を設置する方向で検討している。多くの自治体にとっては経験したことのない業務である上、大量に発生するごみを迅速に処理する必要があるため、支援機関を通じてサポートする。
2025/06/29
-
原発への影響確認=海域活断層評価受け―電力3社
海域活断層の今後30年以内の地震発生確率が公表された日本海中南部周辺には、複数の原発が立地している。
2025/06/28
-
M7級、30年以内に16~18%=近畿・北陸沖の海域活断層評価―能登周辺は高め・地震調査委
政府の地震調査委員会は27日、日本海中南部(近畿・北陸沖)に分布する23カ所の海域活断層について今後30年以内の地震発生確率を公表した。マグニチュード(M)7の地震を引き起こす恐れのある長さ20キロ以上の活断層や断層帯が評価対象。
2025/06/27
-
「空飛ぶ基地局」26年スタート=ソフトバンク、災害時に活用
ソフトバンクは26日、成層圏を飛ぶ無人機から電波を送る「HAPS(ハップス)」を使った通信サービスを2026年に国内で開始すると発表した。まずはプレ商用サービスとしてエリアや利用者を限定して試験的に運用。災害時などの活用を想定している。一般向けサービスは27年以降の開始を目指す。
2025/06/26
-

滞在か退避か 災害は待ったなし!!2重想定で取り組む防災 (押入れ産業)
2025年8月の危機管理塾は8月5日(火)16時から行います。今回は押入れ産業の木戸博美氏さんを講師にむかえて開催します。
2025/06/24
-

新・危機対応記者会見シミュレーション~実践型メディアトレーニング
本研修では記者会見の司会はじめ会社幹部(社長、担当役員、現場責任者等)の役になり、危機的状況についての説明や質問への回答、謝罪のポイントについて学んでいただきます。
2025/06/24
-
ETC障害時、渋滞防止を優先=情報不足なら料金徴収せず―高速道路3社
中日本、西日本、東日本の高速道路3社は23日、4月に発生した自動料金収受システム(ETC)の大規模障害を受け、広域的システム障害発生時の危機対応マニュアル案を取りまとめたと発表した。「交通の流れを止めない」ことを基本方針として明記。
2025/06/23
-
災害時のSNS収益化停止=偽情報対策で、法整備も検討―総務省
インターネット上の偽情報・誤情報対策を議論する総務省の作業部会は23日、中間取りまとめ案を示した。災害時などにSNSでの偽情報の拡散を防ぐための収益化停止について、事業者による自主的な規制に加え、必要に応じて法整備も検討する方針を示した。
2025/06/23
-

第11回 ソーシャルリスク管理体制の構築
企業にとって、リスクは、リターンの源泉であり、戦略的方針に従って積極的にテイクすべき対象といえる。誰にも将来の具体的なシナリオを正確に予測することができない。そのため、企業価値を向上させるためには、具体的で明確な戦略の策定と遂行、その遂行の過程で発生する不確実性に起因する価値の変動(=リスク)に対して的確に対応していかなければならない。
2025/06/22
-

柔軟性と合理性で守る職場ハイブリッド勤務時代の“リアル”な改善
比較サイトの先駆けである「価格.com」やユーザー評価を重視した飲食店検索サイトの「食べログ」を運営し、現在は20を超えるサービスを提供するカカクコム(東京都渋谷区、村上敦浩代表取締役社長)。同社は新型コロナウイルス流行による出社率の低下をきっかけに、発災時に機能する防災体制に向けて改善に取り組んだ。誰が出社しているかわからない状況に対応するため、柔軟な組織づくりやマルチタスク化によるリスク分散など効果を重視した防災対策を進めている。
2025/06/20
-
事業規模、5年で1.9兆円=26年度からの震災復興方針―政府
政府は20日の閣議で、東日本大震災の復興に向けた新たな基本方針を決定した。2026年度からの5年間の事業規模を1兆9000億円程度と見込み、21~25年度の1兆6000億円程度を上回る額を示した。東京電力福島第1原発事故に伴う除染で生じた「除去土壌」の最終処分や住民の帰還促進などに取り組む。
2025/06/20
-
経営改善へ計画策定求める=工業用水道、耐震化の補助要件―経産省
経済産業省は、工業用水道の耐震化や浸水対策などに取り組む自治体向けの補助金を巡り、申請を希望する場合、経営改善につながる事業計画の策定を求める方針を固めた。施設の老朽化が進む一方、水需要は減少し、事業の経営は厳しさを増している。
2025/06/18
-

最大出力2600W、容量1024Whのポータブル電源
ドローンメーカーのDJIは、2600Wの安定出力、1時間未満でのフル充電が可能なポータブル電源「Power 1000 V2」を販売する。昨年発売した「Power 1000」の後継機で、急速充電機能や信頼性を向上させ、アプリを使ったリモートコントロールなどの新たな特徴を備えたもの。一般社団法人防災安全協会の認証を取得済み。
2025/06/17
-
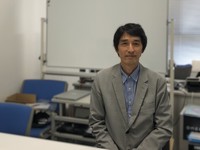
サイバーセキュリティを経営層に響かせよ
デジタル依存が拡大しサイバーリスクが増大する昨今、セキュリティ対策は情報資産や顧客・従業員を守るだけでなく、DXを加速させていくうえでも必須の取り組みです。これからの時代に求められるセキュリティマネジメントのあり方とは、それを組織にどう実装させるのか。東海大学情報通信学部教授で学部長の三角育生氏に聞きました。
2025/06/17
-
21カ所で「防災庁」誘致要望=都道府県の3割が名乗り―首都のバックアップ、集中是正
政府が2026年度の創設を目指す「防災庁」の地方誘致について、時事通信が調査、集計したところ、誘致を求める地域が少なくとも21カ所あることが分かった。名乗りを上げた都道府県は約3割に当たる15道府県。市などを含めると全国で28団体に上った。
2025/06/16
-
若い女性に地方離れ傾向=性別役割意識解消訴え―男女参画白書
政府は13日の閣議で、2025年版の男女共同参画白書を決定した。白書は若い女性が地方から都市へ転出し、地元に戻らない傾向が強くなっていると指摘。地方に根強く残る「固定的な性別役割分担意識」を解消し、女性が活躍しやすい環境を整備することが必要だと訴えた。
2025/06/13
-

入居ビルの耐震性から考える初動対策退避場所への移動を踏まえたマニュアル作成
押入れ産業は、「大地震時の初動マニュアル」を完成させた。リスクの把握からスタートし、現実的かつ実践的な災害対策を模索。ビルの耐震性を踏まえて2つの避難パターンを盛り込んだ。防災備蓄品を整備し、各種訓練を実施。社内説明会を繰り返し開催し、防災意識の向上に取り組むなど着実な進展をみせている。
2025/06/13


















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



