レジリエンス
-
南海トラフ地震、事前避難51万人超=「警戒」発表時、内閣府が初調査
内閣府は20日、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された際、1週間の事前避難が必要となる人数が全国で51万人超に上るとの初めての調査結果を発表した。事前避難者だけで、東京電力福島第1原発事故を含めて約47万人が避難した東日本大震災を上回る見込みとなった。
2025/08/20
-

BCPの発想転換「タラ型」への3ステップ
中堅メーカーの総務部で危機管理を担当するAさんはBCPについて悩んでいます。理由はBCPが危機ごとに乱立し、現場からはお荷物扱いされているからです。Aさんは、従来と異なるBCPを求めています。BCPの発想転換を紹介シリーズの2回目です。
2025/08/20
-
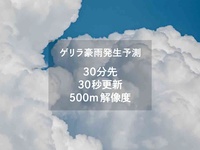
ゲリラ豪雨を30分前に捕捉 万博会場で実証実験
「ゲリラ豪雨」は不確実性の高い気象現象の代表格。これを正確に捕捉しようという試みが現在、大阪・関西万博の会場で行われています。情報通信研究機構(NICT)、理化学研究所、大阪大学、防災科学技術研究所、Preferred Networks、エムティーアイの6者連携による実証実験。予測システムの仕組みと開発の経緯、実証実験の概要を聞きました。
2025/08/20
-

BCPは危機対応からサステナビリティに移る
2027年から上場企業にサステナビリティ情報の開示が義務化されます。「サステナビリティ情報」には気候変動対応のほか災害対応、サイバーセキュリティ対応などが含まれ、BCP担当者は考え方の根本的な見直しに迫られています。つまり、BCPを単なるリスク対応ではなく企業価値向上の戦略的要素としてとらえ直すこと。BCPの大転換を考えます。
2025/08/19
-

お荷物化するBCP「カモ型」から「タラ型」に発想転換を
せっかくBCPを整備してきたのに本当に役立つのかと、疑問を持たれることは少なくありません。特に、危機ごとにBCP策定を進め、全ての災害に対応するために個別マニュアルが増え続けると、現場の評判は芳しくありません。なぜなら、現場では使えない“お荷物”になっているからです。今回から3回にわたって、視点を変えたBCPの考え方を紹介します。
2025/08/19
-

第4回 米国で急増する「逆差別」訴訟
最近の米国最高裁判所の「Ames v. Ohio Department of Youth Services」の判決において、判事らは、(差別的な扱いを受けたと主張する)多数派グループに属する原告が、「被告が多数派に対して差別的な雇用主であるという主張を裏付ける」追加的な状況を示す必要はないとの見解で一致した。
2025/08/19
-

危機管理カンファレンス2025秋
危機管理カンファレンス2025秋は、レジリエントな組織文化の構築に向け、企業はどのようにリスクマネジメント・BCM体制を築き上げるているのか、最新の動きや役立つソリューションを紹介します。
2025/08/18
-

第15回(最終回) ソーシャルリスクに対する能動的レジリエンス
レジリエンスとは、あるレジーム(体制、制度)にとどまるために、閾値内で変化を受容し、擾乱を吸収できるシステムを再生する能力のことである。また、適応可能性とは、社会生態システムが経験や知識、記憶を踏まえ学習し、外部からの変化や擾乱およびシステム内部の変動に対応して、レジームにとどまりながら発展しようとする力のことを指す。社会の抱える課題を解決して適切なレジームにとどまろうとする能力はレジリエンスと呼ぶことができる。
2025/08/16
-
来場客帰宅困難、検証を指示=伊東万博相
伊東良孝万博担当相は15日の閣議後記者会見で、大阪・関西万博の会場近くへ乗り入れる大阪メトロの運転見合わせにより、多くの来場客が帰宅困難となった問題で「大変なご迷惑をおかけして申し訳ない」と陳謝した。その上で、万博を所管する経済産業省に、対応を検証するよう指示したと明らかにした。
2025/08/15
-
「広く周知され進歩」=南海トラフ臨時情報、発表1年を前に―平田検討会会長
気象庁の南海トラフ地震の評価検討会会長を務める平田直東京大名誉教授は7日、会合後の記者会見で、「南海トラフ地震臨時情報」が初めて発表されて8日で1年を迎えるのを前に「臨時情報が広く知られたことは進歩だ」との見解を示した。
2025/08/07
-
鉄道「原則運行規制せず」=南海トラフ臨時情報の指針改定―内閣府
内閣府は7日、「南海トラフ地震臨時情報」の発表時に自治体や企業が取るべき対応を示したガイドライン(指針)を改定した。経済活動やイベントなどの開催に当たり、安全確保策を講じた上で「できる限り事業を継続することが望ましい」と明記。
2025/08/07
-

第3回 アメリカ海洋大気庁のデータの喪失
アメリカ海洋大気庁が最大19の嵐を予測している今年は、組織が最悪の事態に備えるために、データモデリングがこれまで以上に重要となる。実は重要なリソースが危険にさらされたり、完全に失われたりする可能性もある。
2025/08/05
-
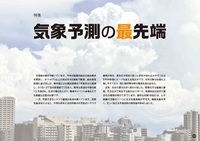
極端気象を捉える最新技術
災害級の猛暑と豪雨が常態化。そこへ新たなハザードが襲えば、危機対応は複合化を迫られます。先般の津波対応がそうでした。同時に、日々の気象がいかに人の活動に影響を与えているかにも気づきます。今号では極端気象をいち早く正確に捉える予測技術の最先端を紹介、またカムチャツカ半島地震と周辺の地震、火山との関係を解説します。
2025/08/05
-

多重・連鎖型リスク時代のBCP──専門家×ITベンダーが語る“本気の備え”
新型コロナウイルスを経て、企業を取り巻くリスク環境は劇的に変化した。感染症と自然災害、あるいは地震と豪雨による複合的な災害、さらにはサイバー攻撃とサプライチェーン分断、情報混乱などさまざまなリスクが次々と連鎖的に発生、予期できない形で発展し、甚大な被害をもたらす「多重・連鎖型リスク時代」へと突入したと言っていい。こうした予測不能な時代において、企業はいかにして事業を継続し、社会的な責任を果たしていくべきか。名古屋工業大学教授の渡辺研司氏とTISインテックグループの林伸哉氏に話を聞いた。
2025/08/04
-

サプライチェーンのリスク調査はより網羅的に
最も古くから定期的に発表され、筆者が継続的にウォッチしているレポートのひとつである『Supply Chain Resilience Report』。本稿ではその 2024 年版から、筆者が特に注目したデータをピックアップして紹介させていただく。
2025/08/02
-
避難時の熱中症対策を検証=坂井防災相
坂井学防災担当相は1日の閣議後記者会見で、ロシア・カムチャツカ半島付近の地震による津波で避難指示が長引いたことを踏まえ、十分な熱中症対策や円滑な避難が行われたか検証する考えを明らかにした。
2025/08/01
-
小売りや外食、一時休業=津波警報発令で
ロシア・カムチャツカ半島付近で発生した大地震で津波警報が発令されたことを受け、流通・外食業界では30日、太平洋沿岸地域を中心に店舗を一時休業する動きが相次いだ。 セブン―イレブン・ジャパンでは一時、最大344店が営業を見合わせた。午後5時時点でも休業店舗数は237店に上った。
2025/07/30
-
セブン、津波警報で316店一時休業=ファミマとローソンも
セブン―イレブン・ジャパンは30日、津波警報の発令を受け、午後2時半時点で太平洋沿岸を中心とする316店舗が一時休業していることを明らかにした。ファミリーマートは午後1時半時点で273店舗、ローソンは午前11時半時点で266店舗が休業している。
2025/07/30
-
指針見直しへ検討会が初会合=南海トラフ地震臨時情報―内閣府
内閣府は24日、「南海トラフ地震臨時情報」の発表時に自治体や企業が取るべき対応を示したガイドラインの見直しなどについて話し合う有識者検討会の初会合を開いた。昨年8月に初めて発表された際、一部地域で混乱が見られたことを踏まえ内容の拡充を検討し、今年8月中の改定を目指す方針を確認した。
2025/07/24
-
東海道新幹線、減速せず=南海トラフ臨時情報、日向灘なら―JR東海
JR東海は24日までに、宮崎県沖の日向灘を震源とする地震を受けた南海トラフ地震の「臨時情報」が発表された場合、東海道新幹線の減速を行わない方針を決めた。昨年初めて臨時情報が出された際は震度7が想定される一部区間で減速したが、対応を見直した。
2025/07/24
-
石破首相「仙台に防災拠点」
石破茂首相は19日、仙台市で街頭演説し、2026年度中の設置を目指す「防災庁」に関し、「仙台から防災の拠点をつくる。必ず実行する」と述べ、東日本大震災で被災した仙台市に地方拠点を設置する考えを示した。 災害対策の司令塔となる防災庁の設置は石破政権の看板政策。
2025/07/19
-

第2回 「エージェント型AI」とは?そして、安全に利用するために
エージェント型AIは、タスクを自律的に実行し、「思考」に基づく意思決定を行い、サードパーティ製アプリケーションと連携してタスクの完了を促進する。
2025/07/18
-

第13回 サステナブル経営におけるレジリエンス強化
企業に対する社会的価値観は大きく変化しようとしている。これに伴い、企業と社会との関係性の見直しと企業の存在意義の再考が進められている。SDGsが提示する社会・環境問題は、現代社会が享受している生活基盤を将来の世代へ継承するために解決していかなければならない喫緊の課題といえる。
2025/07/17
-

TIS×リスク対策.comハイレベルBCPセミナー大規模災害における迅速な情報共有のあり方
本セミナーでは、単なる知識の共有で終わることなく、現場と経営サイドをつなぐ「情報DX」の最前線をご紹介します。
2025/07/11
-

災害をリアルに疑似体験することで防災意識を高める
能美防災株式会社ではVR(バーチャルリアリティ)を活用した災害疑似体験コンテンツを開発している。すでにリリースされている『火災臨場体験VR~混乱のオフィス~』の続編としてリリースされたのが、『地震・津波臨場体験VR~命をつなぐ選択~』だ。今回は特販事業部 主査 佐々木聰文さんに、災害臨場体験VRシリーズ開発の背景や思い、『地震・津波臨場体験VR~命をつなぐ選択~』について話を伺った。
2025/07/10


















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



