2015/01/25
誌面情報 vol47
驚くことに、白馬に次いで被害が大きかった小谷村からは救助要請も入っていないという。小谷村では、家屋の全壊などが比較的に少なかったこともあるが、被災直後から地元消防団が見回りを開始し、危険家屋の住民を避難所に移すなどの活動にあたった。もともと、1軒1軒が離れポツリポツリと建つ山間部では、近所を見回るだけでも限界がある。その意味では、消防団の活動が共助の限界を助ける上では今後も期待されることは間違いない。

被災者が加害者になる
問題は、公設消防に限界があるとはいえ、住民が危険な地域で救出活動にあたることが、十分な検証がないまま「美談」とされてしまうことだ。現地には、1階がつぶれ、2階が中ぶらりになった建物もある。ちょっとした作業で、建物全体のバランスが崩れ、二次災害に発展することは十分考えられる。
今後の対策として求められることは、当然のことながら、住民による救出活動の負荷をなるべく減らすために、耐震化や家具の転倒防止について、一層推進していく必要があるということ。特に1人暮らしの高齢者などは、費用のかかる耐震化への理解を得ることは難しい。しかし、仮に被災してしまった時に、救出にあたってくれる近所の方までも危険な目にあわせるかもしれないということを認識してもらえば、多少なりとも耐震化への動機付けにはなるかもしれない。「自分はどうなってもいい」という考えは、共助の根底を揺るがす。支援者側だけでなく、要支援者の防災教育が求められる。
一方で、救出する側にもルールが必要だ。勇猛果敢に被災家屋から被災者を助けることは、結果が無事ならば、それほどありがたいことはないが、もし自らが被災すれば、自分を助けようと、さらに多くの人が被災する危険性もある。
例えば、見回りに行く時には必ず2人以上で回る、危険性の判断を十分に行った上で自らの安全性が確保できれば救助にあたる、そうでなければ公設消防の到着を待つ、救出後の搬送先を決めておくなど、あらかじめ対応の心得を持っておくことも重要ではないか。
東日本大震災で甚大な被害を被った岩手県大槌町では、安渡地区が独自の地区防災計画づくりに取り組んでいるが、その中で、老人への避難の説得は15分までにするというルールを検討している。この地区では、駄々をこねる老人を「こすばる老人」と呼んでいるが、東日本大震災では津波警報が発せられても「ここから動きたくない」と、こすばる(駄々をこねる)老人が多く、老人の避難を支援している最中に津波に巻き込まれた消防団員も出てしまった。
地元密着のボランティア支援

今回の地震では、非常に早い段階から、県と被災市町村の社会福祉協議会が中心となり、ボランティアセンターを立ち上げるなど、活躍した。被災規模が比較的に狭く、降雪時期とあって、危険性もあることから、地元を知る周辺市町村の住民に対象を絞り、ボランティアを募集した。現地に即した形で、被災住民に寄り添った活動を展開するには地元の力が大きい。もう1つ、注目すべきは、今回の地震では早い段階から、プロの建築家が被災者ニーズに即した専門的アドバイスを行うなど、支援活動を展開したことだ。
地震の場合、住まいを修理するか、解体するか、住み続けるかなど、その選択に対する被災者の悩みは大きい。
堀之内地区で出会った1人暮らしの女性は築30年に満たない住宅が、応急危険度判定で赤紙を貼られ「知り合いの建設業者に相談したら、修理するには基礎から取りかえるなど、大掛かりな工事が必要で莫大な資金が必要と説明された」と肩を落としていた。
こうした中、新潟市内の建築士らで活動する「建物修復支援ネットワーク」では、早い段階から、建物の修理に関する相談会を開くなど、支援を本格化させた。
地震の被災地では、行政などが損壊住宅を応急判定し、危険度の高い順に、黄、赤、緑の表示を貼るが、これは、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や、外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としたもの。しかし、赤紙判定を貼られた人の中には、修復不能と誤解されてしまうこともあるという。

建物修復支援ネットワーク代表の長谷川順一氏は、「大切なのは、被災した建物を再生するのにどのような手法があるのか、トリアージをして処方箋を示してあげること」と話す。その上で、かかりつけの工務店や建築士とも相談して、「予算に応じて化粧部はあきらめてもらう」「構造補強だけはしっかりやる」など、被災者の状況に応じた対策案を出してあげることが大切だとする。
今回の地震で長谷川氏は、降雪による二次被害の拡大も懸念されたことから、2段階での対策を提案した。まずは、雪下ろしができる程度の応急補強対策をすること。「家がつぶれないで済めば、春になってからでも、どうするかゆっくり考えることができます」(長谷川氏)。
被災建物の修復は、責任が伴うため、建築士や工務店も金額を大目に言ってしまうなど、正しい状況判断がしにくい。長谷川氏は「建設事業者と住民の間に立って、対策の方策を検討してあげることが大切。今回は早い段階からいい形で関わることができたのでは」と話している。
誌面情報 vol47の他の記事
おすすめ記事
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/01/06
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/01/05
-
年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する
サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。
2026/01/04
-

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25
-

-

-

-

-









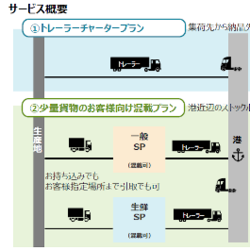














![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方