企業を取り巻く社会的価値観が大きく変化している。企業はまずその変化の本質を把握しなければならない。なぜなら、企業活動と社会の価値観にギャップが生ずれば企業の存続を揺るがし、持続的成長は望めないからである。
経営環境の変化に呼応して、企業はどのように組織の舵取りを行なってゆけばよいのであろうか。変化の方向性を先取りし、持続的成長に向けた中長期戦略を策定し、組織を持続的成長へと統治してゆくための経営管理体系はいかに構築してゆくのであろうか。
サステナブル経営には、社会的価値の向上と企業の経済的価値の向上を両立させる企業統治(ガバナンス)の発揮が必要となる。そしてそこで示された目標の実行性を担保するためには、経営管理の基本事項(企業倫理・理念、組織の指揮・統制、戦略とリスクの統合管理、リーダーシップと組織文化など)を見直し、新たな方向性への舵取りのため、組織的活動を修正し管理の強化を図ってゆかなければならない。
社会的価値の向上と経済的価値の向上の両立を意識し社会課題のビジネス化に取り組む企業のガバナンスについて考えてみたい。マクロ、ミクロの両面からの見直しが必要となってこよう。
まず、取り組むべき対象となる社会課題に関して、社会的価値観を形成する各ステークホルダーの価値観と企業の活動が整合的であるかについてマクロ的に確認し、企業としてとるべき活動方針を明確にしなければならない。その視点として、企業全般に期待されている共通の社会課題(例えば、SDGsで標榜された課題など)を認識する必要がある。このような課題を前提に、社会から向けられた企業への期待に対し、自社としてどのような対応方針を立てるのか、その役割と具体的な事業活動との間の整合性に注意を払わなければならない。具体的には、課題解決と想定する企業活動の貢献の意義や関係性について、重要なステークホルダーの視点から、その適合性の検証が必要となろう。ここで注意を要することは、この時点で確認できることは、現時点で顕在化している社会的価値観との整合性であるという点である。なぜなら、社会課題のビジネス化の実現を想定した時間軸は長期に及ぶため、この間に社会的価値観の変化が想定されるためである。つまり、企業の貢献のあり様は時間とともに変化する。そのため、このような動態的な環境変化への対応力を発揮しうるようガバナンスを効かせてゆく必要がある。
次に、マクロ的な整合性を踏まえ、ミクロの視点から、個別企業が所属するセクターの個別性や特定の企業自身が進めようとしている具体的な戦略を前提により細部にわたる企業活動のあり様を検証してゆく必要がある。
これまでの気候変動に伴う変化に対する企業の対応事例を振り返ってみると、まずパタゴニアやイケアなどの比較的規模が小さい非上場企業が、持続可能性を重視する革新的な対応を進めてきた。その後に規模の大きい上場企業が後を追いかける展開となっている。
サステナビリティ戦略の成果は、その価値を証明する有効なデータが集まるまでにタイムラグが存在することを考慮するなら、リーダーは、一歩先の世界を見据えてガバナンスを発揮してゆかなければ、歴史の流れに取り残され、パートナーや顧客が大挙して離れていく危機に直面する可能性がある。






















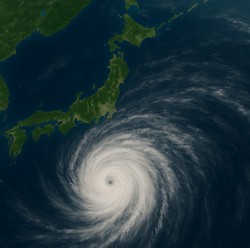












![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方