自然災害
-

内閣府、仮設住宅の設置費用基準を倍増
内閣府は1日付で仮設住宅に関する告示を行った。仮設住宅の明確な分類・定義を行ったほか、広さに柔軟性を持たせ1戸当たりの設置費用基準を倍以上に見直し。生活環境の改善につながる見通しだ。
2017/04/19
-

空気呼吸器を付けたドッジボール訓練
空気呼吸器をつけたドッジボール訓練 「Firefighters and dodgeball training」(出典:YouTube)複雑な構造の建物火災で要救助者が複数逃げ遅れ、黒煙が充満している中での検索・救助活動時、さらに空気呼吸器の残圧が低くなり、退出開始を教える警報が鳴り響いたとする。
2017/04/19
-

防災コンテンツ「+ソナエ」に英語版
アールシーソリューションは11日、同社が開発した緊急地震速報アプリ「ゆれくるコール」の機能の1つで、防災知識を紹介するコンテンツ「+ソナエ」の英語版をiOS、 Androidともに提供開始したと発表した。また、日本語版・英語版ともに新たに「避難生活」「備蓄」「女性の視点」の特集ページを追加し、それぞれのテーマに合ったコンテンツを表示する。
2017/04/19
-

【第5章】 災害救護 1(前編)
読者の方もご存知だと思うが、あの震災では自助・共助により命が助かった割合はなんと95%にも上る。(下グラフ参照) 一体この数字から何が読み取れるのだろうか? 筆者はこの数字を“人間が本能的に持つ善の心がもたらした勇気ある行動の結果”だと思っている。つまり、一旦災害が発生し自分の命が助かった者は、好む・好まざるに関わらず、自発的に救助活動を始めるということである。しかしその側面では大変な悲劇を招きかねない危険が潜んでいる。
2017/04/18
-

都水防計画、河川の要注意箇所が微増
東京都は17日、東京都水防協議会を開催。今年度東京都水防計画案を承認した。都が管理する一級・二級河川における水防上の要注意箇所について、2016年の台風9号の影響から前年度比4カ所増の260カ所とした。洪水や河川工事施工で増加した。
2017/04/17
-

国交省、災害時民間物流施設利用を推進
国土交通省は11日、災害時対応の「広域物資拠点開設・運営ハンドブック」の見直しなど災害に強い物流システム構築の取り組みについて発表した。民間の物流施設のリストアップや災害時活用の推進、物流事業者団体との協力推進といった取り組みを行っていく。
2017/04/17
-

「想定内」の中の「想定外」が問題~熊本地震から感じたこと三題~
4月8日、福岡大学で開催された地区防災計画学会で発表する京都大学防災研究所巨大災害研究センター教授・センター長 矢守克也氏私の母は熊本市東区で一人暮らしをしており、昨年の熊本地震で被災しました。
2017/04/17
-

小型いすのリアルな震度7体験装置
白山工業株式会社は、地震の揺れを再現する自走式の可搬型地震動シミュレーター「地震ザブトン」の販売に注力する。体験者が座った状態で地震が起きた時のような揺れが起き、地震動と合わせた室内被害映像を同時に見ることで、よりリアルな状況を体験できる。販売価格は、本体と操作台、コンテンツ、映像・音響装置 一式で1600万円(税抜き)。
2017/04/17
-

東京都、降雨情報サイトをスマホ対応
東京都は14日、下水道局のホームページで公開している降雨情報システム「東京アメッシュ」のスマートフォン版を15日から提供すると発表した。小池百合子知事は14日の記者会見で同サイトの使いやすさをアピールしたほか、熊本地震からちょうど1年のこの日、改めて防災への取り組みを推進する方針を示した。
2017/04/14
-

連続通話国内最長9時間の衛星電話
ソフトバンクは、防水・防じんで、耐衝撃性能を備えた衛星電話「SoftBank 501TH」の販売に注力する。片手で持ちやすいコンパクトサイズで、大容量バッテリーを搭載しているので約9時間の連続通話ができる。災害時などの際、従来の一般携帯電話は圏外となるような場所や状況でも衛星回線を介して通信が可能だ。
2017/04/14
-

熊本地震、LINEでの情報収集が4割
総務省は13日、「熊本地震における情報通信の在り方に関する調査結果」を発表した。調査は三菱総合研究所に委託。2016年の熊本地震で震度6強以上あった熊本県熊本市、益城町、宇城市、西原村、南阿蘇村で実施。被災居住者862件のアンケートでは、2011年の東日本大震災後にリリースされた比較的新しい通信ツールであるLINEの活用が約4割と目立った。
2017/04/14
-

関連死166人孤立死14人という数字は非常に重い。熊本地震が投げかけた課題と地区防災計画のあり方
熊本地震では直接死が55人に対し、関連死が自殺も含めて166人でした。本来だったらこの166人は救える命。さらにみなし仮設や応急仮設に避難していた方などで孤立死してしまった方が14人も(※2017年4月12日現在)出てしまい、今後もっと出る可能性もあります。これは絶対に曖昧にしてはいけない数字です。
2017/04/14
-
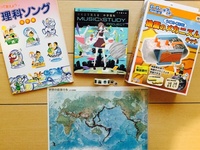
春の新生活におすすめ!子どもと一緒に遊ベる。学べる。驚きの防災教材♪
熊本地震から1年、東日本大震災から6年が過ぎました。残念ながら震災の報道が増える時期だけ思い出して、あとは防災への関心が薄れた方もいるのかもしれません。でも、「忘れないように意識する!」という決意だけでは、心許ないですよね。日々の生活に追われてしまいますので。
2017/04/14
-

この度、防災士をとる事を決意したかんね!
リスク対策.comの読者の皆さん、初めまして!茨城出身の女芸人、赤プルです!この度、防災士になる事を決意したかんね!さて、どうして芸人の赤プルが防災士に?と疑問ですよね。まずは、その辺の経緯から綴っていこうと思います!
2017/04/14
-

両国船着場に帰宅困難者用避難施設
東京都は11日、隅田川の両国防災船着場に隣接する都有地と墨田区有地において、防災拠点やカフェ・レストランなどを整備する民間事業者を募集すると発表した。帰宅困難者の一時避難機能を備えた複合拠点施設を民間事業者が整備する。船着場と一時避難施設が組み合わさることで、船で移動した帰宅困難者受け入れといった防災機能強化を見込める。
2017/04/13
-
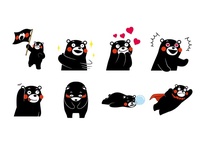
LINE、熊本市と防災で協定
LINEは12日、熊本市と「情報活用に関する連携協定」を締結した。防災情報の受配信や防災に関する研究といった取り組みを行う。市民間のみでなく、市役所職員間や市役所と市民の情報交換ツールとしてのLINE活用を目指す。
2017/04/13
-

木耐協「地域防災ステーション」を始動
木造住宅の耐震化を推進する日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協、本部:東京・千代田区)は11日、「地域防災ステーション」プロジェクトを始動した。木耐協に在籍する全国の組合員・賛助会員(工務店・リフォーム会社)1300拠点が「地域防災ステーション」となることで、地域の防災力の向上を図り、大規模災害時の拠り所となる環境づくりを進めるもの。
2017/04/12
-

流砂からの脱出術
近年、世界中で大水害が増え続けているが、日本でも河川の氾濫や地震による液状化などで、地盤が水で緩み、場所によっては流砂状になる可能性が高い。もし、流砂状の地面に落ちた人、または、自分が落ちたらどのようにして助けるだろうか?流砂に体が取られてしまい、抜け出せなくなっている間に津波や河川等の溢水で水かさが増して溺れる前にどうやって脱出したら良いのだろうか?潮干狩りで膝くらいまで土泥状の中に足を取られたことがある人はいるかもしれないが、ウエストまで入ってしまったら、どうやって脱出するのか?
2017/04/12
-

防災基本計画、ICTや輸送で見直し
政府の中央防災会議が11日、首相官邸で開催され、防災基本計画の見直しを行った。2016年の熊本地震や台風10号被害をふまえてのもの。物資輸送の改善やICTの活用などが盛り込まれた。
2017/04/11
-

国・自治体・民間で災害情報共有推進
政府の中央防災会議は10日、「国と地方・民間の『災害情報ハブ』推進チーム」の第1回会合を開催した。国と地方自治体、民間が持つ災害時の情報をICTの活用により共有し、利用しやすい仕組み作りを行う。今年度末までに施策の取りまとめを行う。
2017/04/11
-

IoT活用しスマホで見守りや熱中症予防
ミサワホームは10日、同社の新築住宅向けに「LinkGates」(リンクゲイツ)と題したIoTを活用したサービス機能の販売を開始する。センサーやコントローラーを用い、住宅内での熱中症予防や防犯、家族の見守りなどをスマートフォンで行うことができる。
2017/04/10
-

「減災への取り組み~荒川下流域のタイムライン~」
タイムラインは自然災害に対処する「人類の知恵」である。災害が想定される数日前から、発生やその後の対応まで、関係機関が災害時に何を優先して取り組むかを時系列的に定めた行動計画表のことである。被災住民、自治体、国、自治会、消防団、鉄道会社、電力会社、教育機関などのとるべき行動が一覧票にまとめてあり、各組織の動きや連携関係が一覧できる。
2017/04/10
-

熊本地震損壊家屋の公費解体は5割完了
政府は7日、「平成28年熊本地震復旧・復興支援連絡調整会議」の第2回会合を首相官邸で開催した。2016年の熊本地震からの復旧・復興の進捗状況や地震をふまえた主な取り組み状況について報告が行われた。また6月中旬ごろに熊本県や市町村との現地意見交換会も開催する。
2017/04/10
-

知事会と市長会、九州で全国初防災連携
九州地方知事会と九州市長会は7日、防災についての連携で合意した。5月に覚書を正式に締結する。ブロック内の知事会と市長会の防災での連携は全国初となる。知事会は九州8県と山口県で、市長会は九州の118市で構成する。主な内容は1.支援体制2.受援計画マニュアルの策定支援3.合同人材育成・訓練。
2017/04/10
-

東京都、特区活用ドローン災害対応実験
東京都は7日、国家戦略特区を活用したドローンの実証実験を行うと発表した。多摩地域で土砂災害が起こったことを想定。4~5月にかけて3回行う予定。
2017/04/07


















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



