2017/04/11
防災・危機管理ニュース
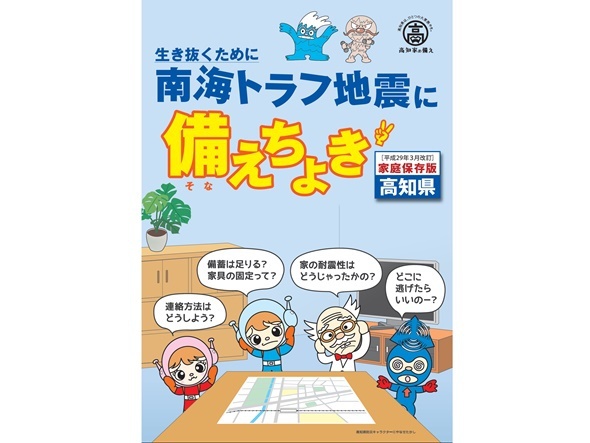
高知県は4月10日、防災啓発冊子「南海トラフ地震に備えちょき(平成29年3月改訂)」を発行したと発表した。県内全戸およそ35万世帯に4月から順次配布するほか、県のホームページからもダウンロードできる。
改訂版では発災直後の「命を守る」取り組みから、助かった「命をつなぐ」ための備えに加え、復旧や復興に向けて「生活を再建する」までを掲載。住民が災害発災後の各場面で自分が何をしなければいけないかをイメージしやすくした。第1章の「我が家のMy備えちょきを作ろう」では、自分の家の備えや家族の連絡先など、住民自らが書き込める仕様にした。
改正した啓発冊子のもう1つの大きな特徴は、「被災後の生活を立ち上げる」ことに着目した点だ。東日本大震災や熊本地震における被災者の法律相談内容をもとに、り災証明書の発行や災害後の国による支援制度を解説するほか、被災後に起こりやすいトラブルについても例示した。
例えば東日本大震災の石巻市では被災して亡くなった人が多かったため、相続関係の相談が多かった。一方で熊本地震では2回の本震と多数の余震により建物被害の数が多く、不動産貸借関係の相談が多かったという。また、住宅や車などのローンの問題も浮上する。
監修にあたった銀座パートナーズ法律事務所の岡本正弁護士は「災害で命が助かっても、その後には生活再建という重い課題が被災者にのしかかってくる。しかし国による当面の生活資金を給付する「被災者生活再建支援制度」や、ローンの返済ができなくなった場合の「自然災害債務整理ガイドライン」など活用することで、被災者は生活再建に大きく一歩を踏み出すことができる。冊子を通じてあらかじめこれらのことを知っておくことで、災害を「自分ごと」にしてほしい」と話す。

岡本氏は、東日本大震災後に弁護士が各地で実施した無料法律相談で集まった4万件以上の被災者の声を、日弁連災害対策本部のメンバーとしてデータベース化した経験をもとに「災害復興法学」という新たな分野を開拓した。今回の冊子の改定は、同氏の災害復興法学を活用した「自分ごと防災プログラム」を高知県危機管理部南海トラフ地震対策課が取り込んだ形だ。
埼玉県和光市でも、3月31日に発行した「防災ガイド&ハザードマップ」で「災害時のお金・住まい・契約」について取り上げた。岡本氏は「生活再建のための法律は認知度が低い。冊子を活用した市民への知識の普及と、ほかの自治体への波及が今後の課題」としている。
■ニュースリリースはこちら(高知県)
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/sonaetyoki-pumphlet.html
■防災ガイド&ハザードマップ、避難所一覧(和光市)
http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/bousai/bousaitaisaku/sei_2_3_5.html
(了)
防災・危機管理ニュースの他の記事
おすすめ記事
-

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25
-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/12/23
-

-

-

-

-


























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方