2015/01/25
誌面情報 vol47
(2)検証結果

ICSの観点から大阪市消防局と海外救助隊との活動を検証しましたが、ほとんどの項目についてクリアしていました。これは大阪市消防局が昭和62年から海外の研修生を10名受け入れる「救急救助技術研修」を行っていること、国際消防救助隊(International Rescue Team of Japanese Fire–Service 以下「IRT」という)の登録市として海外救助隊との活動を想定した訓練を常に行っていること、さらに4名の指揮支援隊員の中には、IRTとして海外派遣を経験した隊員がいたことも大きな要因の1つだと思いますが、何より不断の努力の賜物であると考えます。
なお、今回誌面の関係で触れておりませんが、宮城県南三陸町で海外救助隊と活動した緊急消防援助隊鳥取県隊の鳥取西部広域行政管理組合消防局(以下「鳥取西部消防」という)の活動についても同じ検証結果でした。鳥取西部消防でも、US&R隊(Urban Search & Rescue Task Force)の仕組みやマーキング方法などについての冊子を作成し、それをIRT登録隊員だけでなく全隊員で共有するなど不断の努力の結果が、海外救助隊との円滑な活動につながったのではないかと考えられます。
(3)検証を終えて
これまで、の観点から大阪市消防局と海外救助隊のICS活動について検証してきましたが、ICSの考え方というのは、本稿をご覧の危機対応部門の皆様にとってなんら特別なものではないと感じられたのではないかと思います。それは、国や機関は違っても消防、警察、海上保安庁などの危機対応部門における基本的な対応というのは変わらないからです。
例えば「事案規模に応じた柔軟な組織編制(Modular Organization)」における指揮(Command)、事案処理(Operation)、計画・情報(Planning)、後方支援(Logistic)、財務管理(Finance)という役割は当然必要ですし、「目標による管理(Management by Objectives)」における目標を定めることも当然必要です。もちろん、監督限界(Manageable Span of Control)のように新しい概念もありますが、ほとんどの異なる部分は、それを表す言葉とか表現、様式などであり、根本というか基本の対応方法は変わらないのではないでしょうか。
そうであるなら、ICSと日本の危機対応について比較し、同じ所は標準化し、統一用語(Common Terminology)や監督限界(Manageable Span of Control)などの異なるところ(新しい概念)については、知識として覚えておけば、今後ICSを採用している国との活動を更に円滑にできるのではないかと考えます。もちろん、知識として覚えるだけでなく様式などについては、危機対応部門の共通の制度として標準化できればいいのですが。
7 おわりに
前号で寄稿させていただきましたが、災害対策の標準化の1つの動きとして、平成26年4月22日に消防庁から、「大規模災害時の検索救助活動における統一的な活動標示(マーキング)方式の導入について」という通知が発出されています。
これは、東日本大震災での経験を踏まえ、今後、国内で発生した大規模災害時において、消防機関が自衛隊、警察、海上保安庁などの関係機関と連携して活動する現場で使用する統一的な活動標示方式を統一するという通知です。
大規模災害時、この通知を知らなければ、救助活動に支障が出ることになります。そのような意味でも今後、これら災害対策の標準化の動きについて、引き続き注目していく必用があります。
<参考文献>
(1)3・11以後の日本の危機管理を問う(神奈川大学法学研究所叢書)務台俊介(著),小池貞利(著),熊丸由布治(著),レオ・ボスナー(著),Leo Bosner(原著)
(2)近代消防No.612 「海外からの救助隊受入」合田克彰(著),辻美都利(著),赤川紀夫(著)
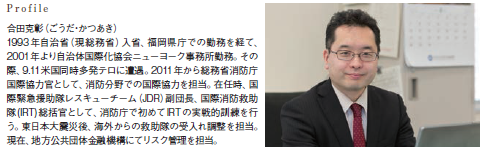
誌面情報 vol47の他の記事
おすすめ記事
-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05


























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方