第5回 介護施設選びの正解
~後悔しない選択のために~
施設のアセスメントを行う

八重澤 晴信
医療機器製造メーカーで39年の実務経験を持つ危機管理のプロフェッショナル。光学機器の製造から品質管理、開発技術を経て内部統制危機管理まで経営と現場の「翻訳者」として活躍。防災士として国連グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンDRR分科会幹事も務める。
2025/05/06
忍び寄る親の介護リスク

八重澤 晴信
医療機器製造メーカーで39年の実務経験を持つ危機管理のプロフェッショナル。光学機器の製造から品質管理、開発技術を経て内部統制危機管理まで経営と現場の「翻訳者」として活躍。防災士として国連グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンDRR分科会幹事も務める。
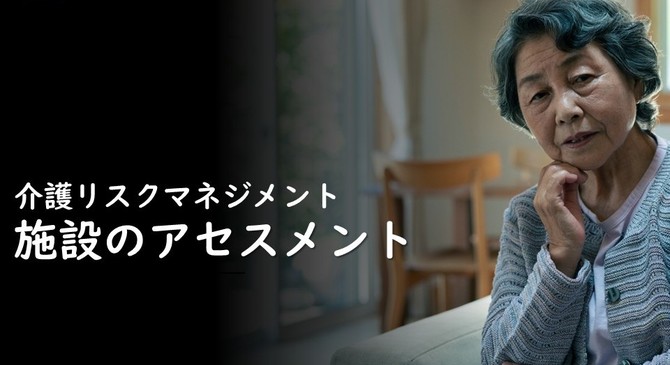
「お母さんを施設に入れるなんて、できないわ」
「親の面倒は子どもが見るのが当たり前じゃないの?」
こうした言葉を、私は施設探しを始めた頃、周囲から何度となく耳にしました。そして、私自身の中にも、そんな声が常にありました。これまでの連載を読んでくださっている方なら、私が東京で働きながら長野の母親を介護するという"遠距離介護"を選択したことをご存知でしょう。
しかし、多くの方が疑問に思われるはずです。
「なぜ母親を東京に呼び寄せて同居しなかったのか?」
「東京近郊の施設を探さなかったのか?」
今回は、多くの方が直面するこの難しい決断—「同居か施設か」「どこの地域の施設を選ぶか」について、私自身の経験をもとにお話ししたいと思います。そして、実際に施設を選ぶ際のポイントや注意点も詳しくご紹介します。
母の認知症が進行し始めた頃、まず最初に考えたのは、やはり「東京で一緒に暮らす」という選択肢でした。仕事をしながらでも、自分がそばにいれば安心できるだろうと。実際、私は本気で同居の可能性を検討し、以下のような準備まで進めていました。
・都内の不動産情報を調べ、母と住める広さの物件を探す
・家賃や引っ越し費用、生活費の試算
・東京都内の介護サービスの情報収集
・職場近くの病院や診療所のリストアップ
しかし、具体的に検討を進めるうちに、様々な現実的な壁にぶつかりました。
| 理由 | 具体的な状況 | 現実的な問題点 |
| 住環境の制約 | 東京の一般的な3LDKマンション(都心ではさらに狭い2LDK、1LDKも多い) | 認知症の母親に新しい環境への適応を強いる難しさ |
| 仕事との両立 | 残業や出張が多い職務 | 日中の見守りや急な対応が困難 |
| 専門的ケアの必要性 | 認知症の進行と専門知識の欠如 | 素人である私に適切なケアが提供できるか不安 |
| 母親の意向 | 慣れ親しんだ長野の家への愛着 | 「家に帰りたい」という強い気持ち |
| 介護者(私)の限界 | 精神的・肉体的な負担 | 仕事と24時間介護の両立によるバーンアウトのリスク |
特に大きかったのは、東京での生活環境の変化が母の認知症症状を悪化させる可能性が高いという点でした。認知症の方は、慣れない環境に置かれると混乱が増し、症状が悪化することが多いのです。長年住み慣れた長野の家から引き離すことが、母のためになるのかという疑問が常にありました。
また、私自身も仕事と介護の両立に不安を感じていました。前回の記事でも触れたように、私は仕事に関わる責任も持っていました。日中一人で留守にすることの不安、突発的な対応が必要な場合の難しさなど、現実的に考えると「同居しながらの介護」は理想通りにはいかないことが予想されました。

実は、一度だけ試みた「短期同居」の経験が、私の決断に大きな影響を与えました。COVID-19が5類に移行した頃、「母を一人でお正月を過ごさせるのは可哀そう」という自分勝手な思いから、医療機関からの「環境を急に変えることはリスクがある」という指導にも関わらず、母を東京のマンションに連れてきたのです。
その結果、あっという間の7日間で私たち家族は精神的に限界を迎えました。認知症における「情動(感情をコントロールできない)」の症状が顕著になり、以下のような出来事が立て続けに起こりました:
・夜中に突然起き出し、各部屋を回る
・「あなたは勉強しないからバカなの」と息子に罵声を浴びせる
・私たち夫婦にニコニコと話しかけていたかと思えば、突然そこにいない「幽霊家族」に話しかける
これまでカメラ越しに見ていた姿が目の前で起こり、私たち家族は「やさしく接する」というよりも、「治ってほしい」という一心で、母の言動を問いただしたり、混乱した発言を訂正しようとしたりと、今思えば認知症の母親を追い込んでばかりいました。
長野の家に送り届けた車中は、全員が疲弊し切って誰も話しかけられないほどの重苦しい空気に包まれていました。そして何より悲しかったのは、母が自宅に戻った後、この環境変化に適応できずに認知症がさらに進行してしまったことです。医療機関からも厳しく注意され、自分の自己中心的な判断が、母にとってもこれまで支えてくれた方々にとっても大きな負担になったことを痛感しました。
忍び寄る親の介護リスクの他の記事
おすすめ記事
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方