2025/07/09
危機管理ポッドキャスト「日本における人道支援のリスク」
対話と信頼の重要性
ジョエル:支援に夢中になると、相手の状況を見失いがちです。
チャールズ:その通りです。私のマインドセットが間違っていた。「助けに来た」という思い込みが、現地の現実を見えにくくしていました。
ジョエル:職員にとっても、初めての経験だったかもしれません。
チャールズ:そうです。災害対応は多くの場合、職務記述書に明記されているものではなく、「誰が何をすべきか」が明確でない状況です。
能登半島地震での教訓
ジョエル:能登半島地震では、NGOやNPOが受け入れられる状況はどうでしたか?
チャールズ:非常に困難だったと聞いています。行政の中でも指示が食い違い、JVOADの報告によれば、5月5日時点で300以上の団体が活動していたそうです。これは行政側にとっても圧倒的な数で、調整は非常に難しい状況でした。
日本では、軍による封鎖のような障壁はありませんが、高速道路通行証など、技術的な面は災害ごとに変わります。最も重要なのは、「私たちが誰で、どう備え、どう対話するか」という姿勢です。アクセスとは、技術ではなくマインドセットです。
ジョエル:外部支援者が日本で受け入れられるためには、どんな優先事項がありますか?
チャールズ:まず法制度です。あなたが翻訳した法律は、誰が責任を持つのかを明確にしています。特に医療や建設などの分野では、認可を得る必要があります。
ジョエル:赤十字や国連のような組織も同様ですよね。
チャールズ:そうです。例えば、日本赤十字が要請しなければ、他国の赤十字の資金は使われません。国連も日本政府からの要請がなければ入国・活動できません。政治的・実務的な理由もありますが、「今は自力で対応できる」という判断も含まれているでしょう。
ジョエル:日本の災害対応文化では、自立性と法制度が重視されるため、外部アクターが入りにくいですね。
チャールズ:そのとおりです。日本では、官僚が「コミュニティの利益のために働く」と信頼されています。これは第二次世界大戦後の占領時代からの歴史でもあります。地方自治体を住民が信頼し、NGOよりも頼りにする傾向があります。
ジョエル:しかし、実際には災害対応の経験が乏しい担当者も多く、異動で知識のギャップが生じています。
チャールズ:日常業務では優れた官僚も、災害時には柔軟性が求められ、それが裏目に出ることがあります。「公平性」を優先する気持ちは理解できますが、緊急時には優先順位の明確化が求められます。
危機管理ポッドキャスト「日本における人道支援のリスク」の他の記事
- 災害時の人道アクセスを考える
- 必要な資源を必要なタイミングで必要な人々に届ける
- 東日本大震災での支援におけるリスク
おすすめ記事
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/01/06
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/01/05
-
年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する
サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。
2026/01/04
-

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25
-

-

-

-

-










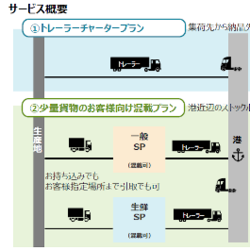














![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方