2025/09/10
防災・危機管理ニュース
米大統領令への署名で日本に課している関税率の引き下げが確定的になり、今後は有力な交渉カードとなった対米巨額投融資の実行に焦点が移る。政府は日米で投資案件を協議する場を設け、日本にとって有益か精査すると説明する。ただ、最終的な選定は米側に委ねられている。日本側が拒否すればトランプ大統領が関税を再び引き上げるリスクは拭えず、運用を注視する必要がある。
対米投融資5500億ドル(約80兆円)に関する覚書によると、大統領への投資先候補の提示はラトニック商務長官を議長として米側の委員で構成する「投資委員会」が決める。ラトニック氏は投資先の選定について「大統領に完全な裁量がある」と述べており、日本への野放図な資金要求につながりかねないとの懸念も持ち上がっている。
これに対し、赤沢亮正経済再生担当相は9日の閣議後記者会見で「法律に基づき、大赤字のプロジェクトに出資・融資・融資保証はできない」と否定。日米両政府の指名で構成する「協議委員会」が投資委員会と事前に協議することで、日本の戦略や法律との整合性を保てると訴えた。
ただ、覚書には、日本は資金提供しない選択もできるが、その場合は決定前に日米で協議すると明記。最終的に日本が資金提供しなかった場合は「大統領が定める率で関税を課すこともできる」との文言もあり、今後、投資案件の選定の過程で、日本側が実際に「拒否権」を行使できるのか検証が不可欠だ。
また、合意に基づいて関税が引き下げられても、幅広い品目に15%という高い関税率が課される。経済産業省は来年度予算の概算要求で、設備投資減税の拡充や自動車購入時に燃費性能に応じて課税する「環境性能割」の廃止を要望し、自動車業界を中心に国内産業の下支えに全力を挙げる。
短期的にはトランプ関税で影響を受ける企業の資金繰り支援などの機動的な対応も必要。石破茂首相の退陣表明による「政治空白」で、企業への支援が停滞しないよう万全の対応が求められる。
〔写真説明〕トランプ米大統領=8日、ワシントン(EPA時事)
(ニュース提供元:時事通信社)

防災・危機管理ニュースの他の記事
おすすめ記事
-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/03
-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26
-

-











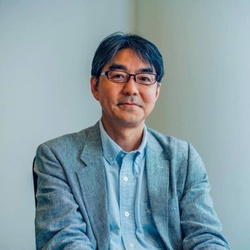












![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方