日本で最も著名な経営者の一人である新浪剛史氏の、サントリーホールディングス代表取締役会長辞任のニュースが駆け巡ったのは9月2日。しかも麻薬取締法違反の疑いで家宅捜索の映像付きでした。記者会見は組織においてダメージを最小限にして信頼回復の第一歩の位置づけになりますが、果たして辞任した人の場合にはどうなるのでしょうか。今回は、新浪氏個人のダメージコントロールとメディア戦略に焦点を当てて考察します。
肝は経過説明
クライシスコミュニケーションの肝は、クライシス発生後の経過についての説明責任です。サントリーホールディングスと経済同友会、それに新浪氏個人を比較すると違いが明らかになります。
サントリーは9月2日に記者会見を行い、会社として事態把握から、どのような形で結論を出したのか時系列で説明しました。8月21日に事態を認識し、22日夜、外部弁護士による新浪氏へのヒアリングを実施。26日に開かれた臨時取締役会で、新浪氏本人がリモートで参加し事情を説明。28日に新浪氏をのぞく全取締役と監査役で話し合い、全会一致での辞職勧告を決めたところまでを公表しました。
経済同友会は、事実を知った翌日の9月3日に会見を行っています。まず、代表幹事である新浪氏が事実関係を説明。その後、筆頭副代表幹事から同会のガバナンス機構としての会員倫理審査委員会による審査を説明。2回目の会見となった9月30日には、同委員会から新浪氏が「辞職勧告が相当」と報告を受けたことを公表しました。
そして新浪氏から事情などの説明を受けたうえで同日に開催した臨時理事会で意見が二分して、その状況を新浪氏に説明したところ本人から辞任の申し出があったことを、記者会見で経緯を説明しました。この会見にも新浪氏は同席しています。
サントリー、経済同友会はいずれも事態を知った直後からの組織としての対応の経過を説明しました。その意味でクライシスコミュニケーションにおける初動は適切だったといえます。
初動の間違い
一方、新浪氏はクライシスコミュニケーションの観点から説明責任を果たしていません。9月3日の経済同友会での会見によれば、当人がクライシスを認識したのは8月9日。CBDサプリを購入したニューヨーク在住の知人から「弟が逮捕された。送付先リストに新浪氏の住所がある。捜査が行くかもしれない」と一報をもらった時点となります。
しかしながら、サントリーに報告する8月21日まで、つまりクライシス発生後の経過について何も説明していません。新浪氏がするべき準備としては、8月9日以降の説明でした。なぜなら、通常はそこに質問が集中するからです。ただ、今回の会見ではその点への質問はでませんでした。
新浪氏のメディア戦略の特筆すべき点は、9月3日の記者会見の直前にNHKと週刊文春の単独取材に応じている点です。一般的に危機発生時には、記者会見の前に個別取材の対応は他のメディアからの反感を生じさせてしまうので避けます。組み合わせてよい場合は、ある一定の期間の中で世論形成の下準備をしたい時です。今回は直前ですからほぼ意味はないといえるでしょう。
では、なぜ組み合わせたのでしょうか。記者会見では言えないことを主張したいからです。サントリーホールディングスの社長である鳥井信宏氏から、取締役会での退任決定を伝えられたことについて、新浪氏は以下のように語っています。
「……私が『これは納得できない』と言ったら、『納得できないなら解任です』と。取締役会は創業家でやっていますから、そう言われたら別に抵抗したって無理かなと思いました。ただ、出張中に結論を出すのはどうなのかと。私も取締役会に参加して議論したかったです。……この10年のアメリカでの私の仕事を、取締役会にはご理解いただけていなかったのかなと」
(週刊文春オンライン 2025年9月2日)
<記者会見研究/研究対象:新浪剛史氏>
























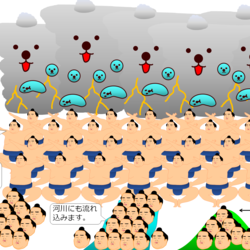














![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方