契約の解除とは
契約の解除の種類、要件・方法、効果等

山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。
2025/11/19
弁護士による法制度解説

山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。

契約は、当事者の意思表示の合致(合意)によって成立します。そして、ひとたび契約が成立すると、当事者は契約が終了するまでその契約に拘束されることになります。ですので、例えば雇用契約・労働契約では、労働者は労務を提供しなければなりませんし、それに対し使用者は報酬(賃金)を支払わなければなりません。
このように、契約は当事者に対する拘束力を有するものですが、この契約の拘束力から当事者を解放する制度のひとつが、契約の解除です。
解除という言葉は、一般的にもよく知られ、使用されているものであるといえます。しかしながら、法律相談を受けていると、「業務委託契約を解除すると伝えたのに、仕事を辞めさせてくれない」などというお話を伺うことがあり、もしかすると、契約の解除についての誤解があるのかなと感じることがあります。
そこで今回は、契約の解除とは何かについて取り上げてご説明したいと思います。
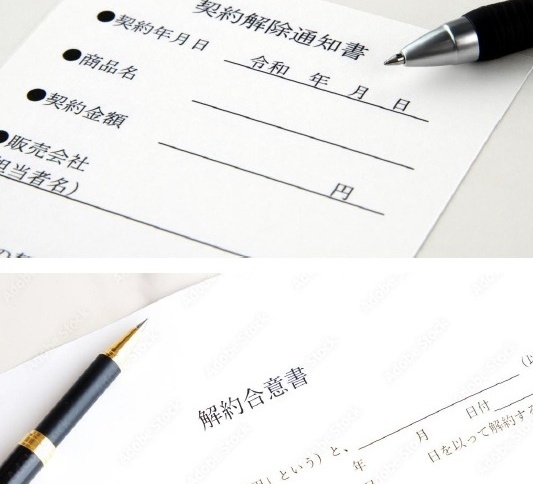
契約の解除は、①解除権を有する当事者の一方的な意思表示(解除の意思表示)によって契約を解消させるものと、②当事者双方の合意によって契約を解消する合意解除との2つに大別されます。
そして、前者(解除権に基づいて、一方当事者の意思表示により契約を解消するもの)はさらに、㋐解除権の根拠が民法等の法律にある法定解除と、㋑解除権の根拠が契約にある約定解除とに分けられます。
法定解除(㋐)の例としては、「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる」(民法541条本文)に基づく催告解除や、「債務の全部の履行が不能であるとき」などの場合の「債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる」(民法542条1項)に基づく無催告解除などがあります。
約定解除(㋑)の例としては、例えば契約書中に一方当事者による契約違反があるときに、他方当事者が解除できる旨の規定がある場合に、当該規定に基づいて解除をするものが挙げられます。約定解除は、原則として、当事者が自由に定めることができます。
●契約の解除の種類

おすすめ記事


中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/17





今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12



海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方