連載
-

学生の人気は「シャープ」から「わかさ生活」へ
大学の講義で、知っている企業公式アカウントの印象を答えてもらう回を設けています。長い間、学生があげる企業公式アカウントは圧倒的にXの「シャープ株式会社」が多かったのですが、今年度は「わかさ生活」がトップとなりました。人材不足が叫ばれる時代、採用広報としての企業公式アカウントの可能性を考えます。
2024/10/11
-

出張中のホテルや車中で地震が起きたら
企業の危機管理担当者はさまざまなリスク対策を講じ、それらをどう社員へ伝えるべきか日々悩んでいると思います。なかでも地震、特に首都直下地震や南海トラフ巨大地震において本当に社員を守り切れるだろうかと考えている方も多いでしょう。社員は常に自社の建物にいるとは限りません。外出中も身を守るにはどうすればよいかを考えます。
2024/10/10
-

多面的な移行リスクの対応が経営を左右
気候変動による2030年最悪のシナリオを描くこの連載。今回は「移行リスク」の影響について説明します。対応次第で、企業の明暗はどのようにわかれるのでしょうか。
2024/10/08
-

第11回 カーボン・オフセット製品の取り組み
国内の地球温暖化削減が計画通りに進行していないため、新たな対策方法により温暖化防止を拡大し認識させる目的で考案されたものが「CFP (Carbon Footprint of Products)を活用したカーボン・オフセット製品 」です。温暖化防止促進を担う「CFPを活用したカーボン・オフセット製品」について紹介いたします。
2024/10/05
-

競争力を維持・向上させる上でのAIリスクマネジメント
人工知能(AI)およびこれに関連する最新技術を活用することは、企業の競争力を維持・向上させるためには不可欠となっている。それゆえに、それらを活用するときには法的そして規制上の課題を検討して、陥りやすい落とし穴を回避しなければならない。そうしたリスクを回避するためには、少なくとも3つの包括的な原則に焦点を当てて、リスクマネジメントを実行する必要がある。
2024/10/04
-

ルール至上主義が社会の秩序を乱す
法規制、ガイドライン、さまざまなルール、これらを守ることは安全で平穏な生活の基盤です。しかし、それらがなぜ必要とされ、何を実現しようとしているのかを見失うと、むしろリスクが増大することはあまり知られていません。実際、理由や目的を見失ったルール至上主義の事例は世の中に多くあります。今回から、その弊害を考察していきます。
2024/09/30
-

第12回: 地域との対話:グラウンド利用再開に向けて
紅葉山FCが利用している市営グラウンドが、近隣住民からの苦情によって使えなくなってしまいました。他の利用団体や関係者と議論を進めた結果、利用団体による「市営グランド利用者協議会」を設立し、協議会としてグラウンドの利用ルールを作ることや、住民苦情への対応窓口を設けることなどについても合意が得られました。
2024/09/30
-
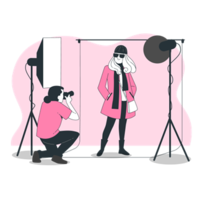
エクソンモービルとシーインに学ぶESGコミュニケーションの落とし穴
最近、石油大手のエクソンモービルや急成長中のファストファッションブランド、シーインが、その環境への取り組みをめぐって批判を浴びています。これらの事例は、ESGコミュニケーションの難しさと重要性を改めて考えさせられる出来事と言えそうです。本稿では、世界的な大企業が直面している課題を通じて、リスク管理担当者が学ぶべき教訓を探ります。
2024/09/28
-

リスクマネジメントを企業文化とするために
リスクマネジメントにおける最大の課題は、中身のある取り組みを維持することにあると言っても過言ではありません。今回は、継続的な活動を実現するために、リスクマネジメントを企業文化として根付かせる具体的な方法を、事例をもとに紹介します。
2024/09/26
-

ERMにおける実行性の強化
企業は、リスクに対する組織の適切な行動を管理するためにオペレーショナルリスクとコンダクトリスクといったリスクカテゴリーを設定し管理を実施していることが多い。オペレーショナルリスク管理は、過去の操業上の失敗事例を分析して同種の事例の再発を予防するための管理である。換言すれば、過去・現在の状況を踏まえ、それを将来に延長して対応するフォワードルッキングなアプローチの一種といえる。他方、コンダクトリスク管理は、将来の環境が必ずしも過去と同様ではないことも踏まえ、組織行動の特徴を理解した上で、組織行動を律する根底の部分(組織文化と表現することもある)を意識して、不測の事態を招かないための制御を行う活動といえる。
2024/09/25
-

三重県の豪雨災害――9月の気象災害――
2004(平成16)年9月28日から29日にかけて、三重県地方は豪雨に見舞われた。折から、台風第21号が接近中であった。紀伊長島町(現・紀北町)三戸(さんど)では、28日15時から29日21時までの30時間に1180ミリメートルの降水量が観測された。この豪雨により、付近一帯では土砂災害が多発し、浸水害も発生した。この豪雨による三重県内の被害は、死者・行方不明者10人、負傷者2人、建物の全壊流出25棟、家屋浸水6149棟などにのぼった。
2024/09/25
-

内部公益通報対応体制
地方自治体で知事に関する告発がなされたものの、それが本人や側近に知られ、不適切な対応がなされたのではと問題になっています。現行の公益通報者保護法施行から2年以上経ちますが、皆様の組織において内部公益通報対応体制は適切に機能しているでしょうか。今回は組織の長や幹部に関する内部通報について、備えと心得をお伝えします。
2024/09/19
-

2030年の物理的リスク顕在化
気候変動による2030年最悪のシナリオを描くこの連載。今回は、「物理的リスク」である異常気象による企業への影響について説明します。物理的リスクは、2030年に、どのような形で顕在化するでしょうか。
2024/09/19
-

南海トラフ地震臨時情報の大失策
この夏、筆者視点で大失態と感じる事案が発生しました。それは南海トラフ地震臨時情報にかかる政府の対応であり、またそれを受けた周辺の反応です。つまり、危機コミュニケーションの大失策。ある意味、日本の危機管理における最大のウイークポイントにも思えます。今回は、あえてこの件に言及します。
2024/09/17
-

避難からBCPまで一気の訓練をしてみては?
BCPの計画と現実とのギャップを、多くの企業に共通の「あるある」として紹介、食い違いの原因と対処を考える本連載。現在は第2章「BCPの実効性、事業継続マネジメント、発生コスト」のなかに潜む「あるある」を論じています。今回は、多くの企業が抱える訓練の予定調和と形式化の問題について。どのように解決できるかを考えます。
2024/09/17
-

第4回 ニセ銀行詐欺
ショッピングや銀行等の手続きもできる、便利なインターネット。だけど、ご注意を!便利さの裏にはさまざまな危険が潜んでいます。ネット詐欺被害に遭わないために、正しい対処法を身につけましょう。第4回は、ニセ銀行詐欺の主な手口と対処法をわかりやすく説明します。
2024/09/13
-

本当にできてる? あたり前のセキュリティ
企業の危機管理担当者は、さまざまなリスクのうちどれを、どのように従業員へ伝えるべきか、日々悩んでいるのではないでしょうか。災害への注意、安全運転の励行、マスクの着用など、あたり前に思えることでも実際にできていないことは多々あります。本連載は「これだけは社員に伝えておきたいリスク対策」をテーマに話題提供します。
2024/09/12
-

暴力的なデモが起きると業務環境はどうなる?
海外では政治や経済、社会問題等さまざまな理由を背景に暴力的なデモが起き得ます。その影響は直接的な暴力だけでなく、政府による外出禁止令の発令、通信環境の悪化、犯罪の増加など多岐にわたります。渡航者はどう安全を確保し、業務を継続すればよいでしょうか。7月から8月にかけて起きたバングラデシュのデモを例に検討します。
2024/09/12
-

不確実性の類型とリスク管理
将来に対する意思決定においては不確実性が存在する。このような状況においてわれわれはいかにして合理的な意思決定をすべきなのか。この問題は「不確実性下の意思決定論」として長らく学問の対象となってきた。そして、これはまさにリスク管理の実践そのものに関わる課題と言える。
2024/09/11
-

「フリーランス新法」の施行まで、あとわずか
「特定受託事業者適正化等に関する法律」(フリーランス新法)が、2024年11月1日に施行されます。組織に属さずに個人として活動するフリーランスの保護を目的にしたこの法律。業務委託を行う事業者は、新法により課される義務を把握し、理解することが大切です。
2024/09/09
-

第11回: 新たな体制:地域とのより良い関係のために
紅葉山FCが利用している市営グラウンドが、近隣住民からの苦情によって使えなくなってしまったため、他の利用団体や関係者の協力を得ながらグラウンドの利用再開を目指しています。これまでの取り組みの中で問題の所在や近隣住民の意向がある程度分かってきましたので、監督の高宮と渉外担当の近藤、野球チーム代表の松嶋、県サッカー協会の藤崎と市役所OBの茅森、市の担当者の日吉が市役所の会議室に集まりました。
2024/09/08
-

自社に適した人権方針・目標をつくり込む
自社だけでなく、サプライチェーンなどの事業に関連する幅広い範囲における人権上の欠陥を発見し、それを根絶・是正するための行動を明示化することが必要になってきている。多くの組織は、この必要性をESGの一環として捉えることが多いかもしれない。しかし、これを独立した、個別的なものとして取り組み、それを表明することは、組織が人権に対して真摯に組んでいることを示すだけでなく、実際に社会の要請に応じて、人権問題に取り組む態勢を強化することにもつながる。
2024/09/07
-

第10回 カーボンフットプリント(CFP)マークの付与手順と算出・表示方法
CFP (Carbon Footprint of Products) は、商品の一生(原材料調達から廃棄・リサイクルまで)に排出されるCO2量を商品に表示して、「見える化」するしくみです。CFPマークの「見える化」は、事業者と消費者の間で「気づき」を共有するためのツールであり、究極的には、地球温暖化の原因であるCO2を減少させる1つの手段として設定され、脱炭素社会の実現に貢献すると期待されています。第8回と第9回に引き続き、CFPマークの付与手順と算出・表示方法、さらにCFP宣言認定製品の現状を中心に解説いたします。
2024/09/07
-

自然災害に備える企業の人事労務管理対策
今年は、1月の能登半島地震に続き、8月には南海トラフ地震臨時情報の発表や大型台風が上陸するなど、災害が相次いでいます。近年、日本では大規模な自然災害のリスクが高まっています。このような予期せぬ事態に備えることは、企業の事業継続を確保するだけでなく、従業員の安全と健康を守る上でも重要です。
2024/09/04
-

温室効果ガス削減の停滞による、2030年最悪シナリオを描く
今回から始まる第二部では、私たちの社会や経済が既存の枠組みから抜け出すことができず、これまで通りのペースで大気中に温室効果ガスの放出を続けた2030年を描きます。どのようなリスクが顕在化し、ビジネスに降りかかるのか。さまざまな影響を見ていきます。
2024/09/04



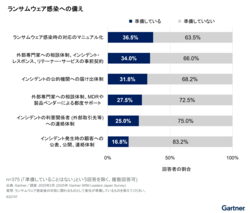









![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)





