避難からBCPまで一気の訓練をしてみては?
第13回:予定調和と形式化を打破する

荻原 信一
長野県松本市出身。大学卒業後、1991年から大手IT企業に勤務。システム開発チームリーダーとして活動し、2005年にコンサルタント部門に異動。製造業、アパレル、卸業、給食、エンジニアリング、不動産、官公庁などのコンサルティングを手がける。2020年に独立。BCAO認定事業継続主任管理士、ITコーディネータ。
2024/09/17
ざんねんなBCPあるある―原因と対処

荻原 信一
長野県松本市出身。大学卒業後、1991年から大手IT企業に勤務。システム開発チームリーダーとして活動し、2005年にコンサルタント部門に異動。製造業、アパレル、卸業、給食、エンジニアリング、不動産、官公庁などのコンサルティングを手がける。2020年に独立。BCAO認定事業継続主任管理士、ITコーディネータ。

BCPの計画と現実とのギャップを、多くの企業に共通の「あるある」として紹介、食い違いの原因と対処を考える本連載。現在は第2章「BCPの実効性、事業継続マネジメント、発生コスト」のなかに潜む「あるある」を論じています。今回は、多くの企業が抱える訓練の予定調和と形式化の問題について。どのように解決できるかを考えます。
③訓練のあり方
・訓練は盛大な朗読会(中京地区大手・製造業・事業部門)
壁の一面にびっしり貼られている一枚を見ると、次のように書かれています。
「製造部製造〇課から報告いたします。人員に被害なし、〇〇装置は被害なし、△△装置は地震の揺れにより調整が必要で復旧までに□時間が必要です。以上、報告を終わります」
どの紙を見ても同じようにセリフ仕立ての被害報告になっていました。
わざわざ仕事を止めて会議室に集まり、事前に用意されたセリフを読み上げ「BCP発動」と高らかに宣言し、事前に用意された結果の報告が行われ、それをみんなで聞いて帰る。このイベントは、何のために行うのでしょうか。
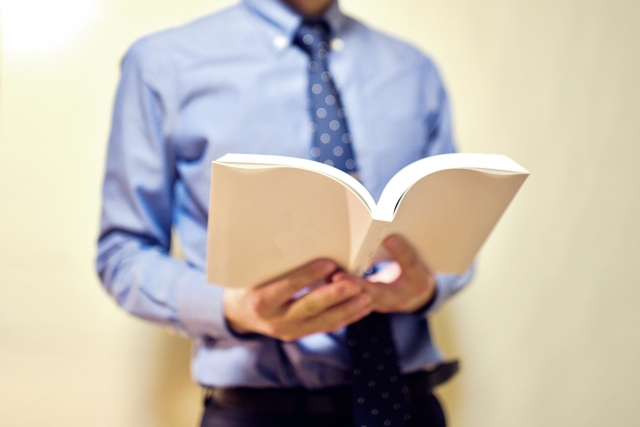
時間に合わせて会議室に素早く集合する訓練か、大きな声でハキハキと報告をする訓練か、報告すべきリソース項目を反復して記憶しておく訓練か、「BCPを発動する」ことを脊椎反射的にちゅうちょなく言えるように慣れさせておく訓練か。この訓練を終えた後、どんな振り返りができるのでしょうか。これを繰り返すことで何が得られるのでしょうか。
時々刻々と状況が動き、少ない情報しかない(本当に被災しているところからは報告がない)状況の中、限られたリソースを駆使して(それさえ情報が届かない場合がある)、どのような判断を下すのか、誰がその判断を下すのか、知恵を絞ることに慣れていくこと、振り返りで出た課題に対策を講じること、「ああしておけばよかった」「こうしておくと便利」というアイデアを日常業務に組み込んでいくことが訓練であり、これを繰り返すことで危機に対応する力を磨いて高めていくことが必要だと考えます。
ざんねんなBCPあるある―原因と対処の他の記事
おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10


海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05





発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方