-

待ったなし!マルチハザードBCPの探求
気候変動と電力の脆弱化が2重のリスクに
電力の確保は今後、国内企業が避けて通れない課題になりそうです。理由の一つは気候変動が与える電力インフラへの影響ですが、もう一つはエネルギー革命に乗り遅れた日本の構造的問題です。多くの国が再生可能エネルギーによる分散型電力網を整備する中、日本だけ旧式の電力システムに頼り続ければ、電気を取り巻く環境が脆くなるのは明らか。今回は将来を見据えた有事と平時の電力確保のあり方を考えます。
2022/01/13
-

危機管理で学ぶ英語
たくさんの日本人がジャブを打ちました!
レジリエント、エクスポージャー、ブースター…。危機管理の英語は専門的で難しそう…。ちょ、ちょっと待ってください‼ リスクの英単語は、海外のニュース番組でバンバン会話に飛び交う時事英語の宝庫なんです。理由は簡単。ニュースの大半は事件や事故、有事のことだから。危機管理を勉強しながら、時事英語も身につけちゃいましょう。Kill two birds one stone(一石二鳥)!
2022/01/13
-

中小企業をめぐるサイバー情勢と対策
「Emotet」と呼ばれるウイルスへの感染を狙うメールに注意!
世界中に大きな被害をもたらしたマルウェア「Emotet」が、2021年11月14日頃から攻撃活動を再開し、ウイルスに感染させる手口に変化が確認されたことから、情報処理推進機構(IPA)等は注意を呼びかけています。
2022/01/12
-

ウイズコロナ時代の健康経営
企業が目指すべきは自社型雇用の構築
新型コロナ流行の結果、テレワークの導入など企業の働き方には大きな変化がありました。国はこの変化を後戻りさせず働き方改革を加速させるとし、メンバーシップ型からジョブ型への雇用形態の転換を目指しています。しかし、単にジョブ型雇用を導入しても望む結果が出るとは限りません。それぞれの企業の事業戦略や社風などを踏まえた自社型雇用の構築が望まれます。
2022/01/12
-

気候変動の危機、社会的格差の拡大などがトップ
2022年版の「グローバルリスク報告書」が、世界経済フォーラムで発表された。新型コロナウイルス感染症の世界的大流行が続く中、気候変動の危機、社会的格差の拡大、サイバーリスクの高まり、そして不均衡なグローバル経済の回復などが、懸念される主なリスクとして取り上げられた。長期のトップリスクは気候変動関連である一方、短期のトップリスクは社会的分裂、生活破綻の危機、そしてメンタルヘルスの悪化などが挙げられている。
2022/01/12
-

タレント防災士・時東ぁみが厳選した防災ポーチ
「防災専門店MT-NET」を運営するMT-NETは、“元祖タレント防災士”の「時東ぁみ」氏とのコラボブランド「mlitB×MT-NET」(ミリットビー・バイ・エムティーネット)の第1弾商品として、時東氏が自ら厳選した防災グッズをスマートに収めた「防災ポーチ」を販売する。
2022/01/12
-

緊急事態を乗り越えるための勘どころ
第5回:バックアップ:練習場所の手配
この連載は、事故や災害など突発的な危機が発生した際にどう対応すべきかを、架空の地域サッカークラブが危機に直面したというストーリーを通して、危機対応のポイントを分かりやすく紹介していきます。第5回は
2022/01/12
-

台風21号教訓に大規模停電時も自立する経営
電気設備工事のタカミエンジは2018 年9月に関西圏を襲った台風21号をきっかけにBCPを策定。従来から運用しているチャットアプリを使い、日常業務のなかに緊急時の連絡・指示を標準化して社員に浸透させています。また、グリッド電源の喪失後も会社を72 時間自立運営することを目標に非常用電源を確保、BCPセミナーを企画・開催して知識の普及にも努めています。取り組みを紹介します。
2022/01/11
-

レトルトとアルファ化米の12食セット
アルファ化米を主軸に加工米飯の製造・販売などを行うアルファー食品は、電気・ガス・水道といったライフラインが停止した場合にも対応できるよう、調理不要のレトルトタイプと、お湯や水を注ぐだけで食べられるアルファ化米(安心米)を組み合わせた長期保存食『備えて安心 お米の12食セット』を販売する。
2022/01/10
-

BCPの実効力を高めるために
これまで7 回にわたり、リスク対策.comが実施した企業の事業継続の取り組みに関する独自アンケート調査の結果を解説してきました。最終回となる今回は、主なポイントを振り返り、BCPの実効力を高めるポイントについて考察します。
2022/01/10
-

危機管理担当者が最低限知っておきたい気象の知識
大雪に備えるための気象情報の使い方(後編)
前回の記事では、大雪によって交通障害の発生が見込まれるときに発表される大雪警報などを取り上げました。今回の記事では警報の発表基準を大きく上まわるような降雪の時に追加的に出される情報や、リアルタイムの降雪量予測の見方を紹介します。また、ライブカメラで雪道の様子を確認する時に押さえておきたいポイントも取り上げます。
2022/01/10
-

企業をむしばむリスクとその対策
事故発生のメカニズムを理解した上で有効な事故防止策を
2014年、労働安全衛生法が改正され、重大な労働災害を繰り返す企業に対し、厚生労働大臣が「特別安全衛生改善計画」の作成を指示することができるようになりましたが、労働災害の連鎖は完全には無くなっていません。前回は、ジェームズ・リーズンやシドニー・デッカーなどのリスクマネジメントの専門家たちの理論をもとに、「事故発生のメカニズム」として、3つの事故モデルを解説しましたが、今回は、各産業の特徴に基づき「どの事故モデルを採用すれば、自社の事故防止に役に立つか?」について考えてきます。
2022/01/10
-

東日本大震災 当時から現在の対応、そして将来に向けて(その2)
国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第3回研究会が10月29日に開催され、東北大学災害科学国際研究所所長・教授の今村文彦氏が講演した。第2回は、東日本大震災後の復興プランについて。
2022/01/10
-

世界に通用するBCP資格取得のための研修講座【2023年】
DRI(Disaster Recovery Institute)ジャパンは、BCM(事業継続管理)教育の専門組織で、世界に通用する事業継続専門家の育成のため、DRIIが開発した研修と資格取得のための試験を実施しています。リスク対策.comは運営事務局として、2022年開催分の研修講座の受講者を募集しています。
2022/01/06
-

止水高最大2000ミリのシステム止水シート
安全衛生機器などの企画・販売を手がけるサンリョウは、水害・浸水対策システム止水シート「GENTI SANWRAP(ゲンチ・サンラップ)」のシリーズ商品として、止水高700~2000ミリメートルに対応した「高水位シリーズ」を販売する。水の自重と水圧によって地面と構造物に密着し、シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで固定して浸水を止めるもの。「中水位シリーズ」(止水高100~700ミリメートル)とともに止水高と幅の自由度を高めることで、建物への水害・浸水被害対策を支援する。
2022/01/06
-

レジリエンスとオールハザードBCP
コロナ禍の収束はみえないながらも、巨大災害への備えを真剣に考えるべきときです。2022年年頭のインタビューは防災科学技術研究所の林春男理事長に登場いただき、昨年の災害を振り返りながら、日本社会の課題と企業が果たすべき役割、取り組みの方向性を語ってもらいました。事例紹介においても、巨大災害に備えるライフライン企業と自治体の取り組みをピックアップ、訓練の模様を中心に紹介しています。
2022/01/05
-

IoT化で防災活用可能な街路灯
屋外照明灯メーカーの日本街路灯製造は、IoTネットワーク化した多機能街路灯「スマート街路灯」を販売する。カメラ、サイネージ、エッジデバイス、センサー、LTE・5Gなどの通信機器の設置に対応した設計製造が可能なもので、スペックや外観デザインを各自治体の仕様にカスタマイズできる。カメラやセンサーなどから取得したデータを活用することで、防災やまちづくり、観光などの分野での地域課題の解決につなげられる。
2022/01/05
-

機能する災害対策本部
2022年2月の危機管理塾は、2月8日(火)16時から行います。発表者は、長野県飯田市危機管理室次長の後藤武志さんです。自治体における災害対策本部の工夫を、写真をふんだんに使いながらご紹介していただきます。
2022/01/05
-

世界のリスクマネジメントの潮流
保険加入を自社のセキュリティ対策に生かせ
サイバーセキュリティに対する攻撃が激増している。激増の理由としては、この攻撃が効率のいいビジネスになっていることがあげられる。ハッカーは侵入することで身代金を払わせるのだが、その脅しはコンピュータシステムをロックして機能させるだけでなく、身代金を払わなければ機密情報を公開する、ないしは完全に使えなくするということまで含まれる。システムを回復すればいいということでは済まされない。
2022/01/05
-

気象予報の観点から見た防災のポイント
三八豪雪―1月の気象災害―
1963(昭和38)年1月23日、新潟駅を夕刻に出発した急行「越路」(こしじ)は、順調に走れば、同夜のうちに東京・上野駅に到着するはずであった。しかし、大雪と吹雪のため新潟県内で数回にわたり立ち往生。満身創痍の列車が上野駅に到着したのは、5日後の28日朝であった。急行「越路」だけでなく、新潟県内の信越本線は、1月24日から28日まで全面不通となった。これを含め、1963年1月の一連の豪雪で運休した列車は、当時の国鉄の旅客と貨物合わせて約1万9500本、立ち往生7400両、減収約30億円に達した。これによる社会経済への影響・損失は計り知れない。
2022/01/04
-
東日本大震災 当時から現在の対応、そして将来に向けて(その1)
国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第3回研究会が10月29日に開催され、東北大学災害科学国際研究所所長・教授の今村文彦氏が講演した。4回に分けて講演内容を紹介する。初回は、東日本大震災で津波を引き起こしたメカニズムについて。
2022/01/04
-

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!
第167回:これまでのパンデミック対応からいかに教訓を学び取るか
新型コロナウイルスは完全に消滅しないものの、従来のパンデミック(世界的大流行)から風土病のような状態に移っていくことが想定される。今回紹介するのは、そのような状況変化に対応していくためのヒントや提言をまとめた報告書だ。新型コロナパンデミック対応からどのような教訓を学び、今後に生かしていくかという点を中心に内容を紹介する。
2021/12/28
-

2021年から2022年へ 進化するサイバー犯罪リスクとその対応
本セッションでは、2021年に最も注目を集めた脆弱性と、サイバー犯罪者がそれらをどのように悪用したかを探るともに、2022年に何をするべきか、その対策の方向性を解説します。
2021/12/28
-

省配線・省スペースのパッケージ型自動消火設備
消火器や消火設備等の開発・製造・販売を手掛けるモリタ宮田工業は、多重伝送化によって大型物件に対応し、施工性を向上させたパッケージ型自動消火設備I型「スマートスプリネックス」を販売する。「スプリネックス・シリーズ」の特長である高い防火安全性能はそのままに、施工・点検にかかる負担を軽減し、柔軟性のあるシステム設計を可能にしたもの。
2021/12/28
-

非IT部門も知っておきたいサイバー攻撃の最新動向と企業の経営リスク
そのリンクをクリックする前に
コロナ禍に伴う働き方の変化によって、より多くのサイバー犯罪被害が発生した。LINEなどのメッセージングアプリで情報を守るためにはどうしたら良いのか?怪しいメールに騙されないためには? 再三語られていることではあるが、いま一度紹介していきたい。
2021/12/28
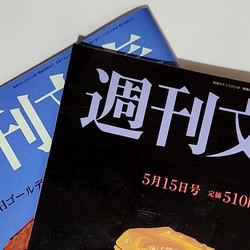



















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



