2025年版の「中小企業白書」と「小規模企業白書」が4月25日に閣議決定されました。円安・物価高、金利上昇、構造的な人手不足など、激変する経済環境の中で中小企業・小規模事業者が直面する課題と、それに対応するための戦略を多角的に分析しています。白書には特徴的な分析テーマが盛り込まれています。今回は「価格転嫁」と「デジタル化」を実現するための第一歩を説明します。
■事例:価格転嫁とデジタル化を成し遂げたい
製造業を営むAさんは、先日公表された「中小企業白書2025年版」を読み込んでいます。創業35年。かつて20人を超える職人が働いていた父親から引き継いだ工場は、社員は10人になっています。仕事はあります。むしろ忙しいほどです。しかし、利益が出ない現状に苦しんでいます。電気代や原材料などの資材コストは上がっても、得意先に対して価格を上げられないからです。
Aさんは白書にある価格転嫁の推進やデジタル化という文言に目を奪われました。白書には、「価格交渉促進月間」「下請かけこみ寺」「IT導入支援事業」など、さまざまな制度や取り組みが記載されています。Aさんは内容を読めば読むほど、自社にぴったりだと思っています。
しかし、同時にAさんは「では、いったい何から始めればいいのか?」と思ってもいます。社内のパソコンはしばらく買い替えていない状況です。見積書はいまだに手書きで出していますし、社員にデジタルが得意な者もいません。「DX」という言葉を聞いたところで、頭の中は真っ白になるばかりです。
先日も若い社員から「業務管理アプリを導入しませんか?」と提案されたのですが、「うちはそういうのは、まだ早い」と答えてしまいました。実際には、どう使えばいいのか、わからなかっただけです。
Aさんは「相談窓口に行ってみよう」と思い、商工会議所のホームページを開いてみましたが、専門用語が多く書いてあり、内容をよく理解できないままでした。
先日、同業者の集まりで、ある経営者が言った「結局、最初の一歩が踏み出せないんだ。誰かが背中押してくれないと」という言葉が、そのまま自分にも当てはまると感じています。
「自分の背中を押してくれる人がいれば、進めるかもしれない。だが、誰に聞けばいい。そもそも聞いていいのか。恥をかくだけじゃないのか?」
Aさんの悩みは深くなるばかりです。


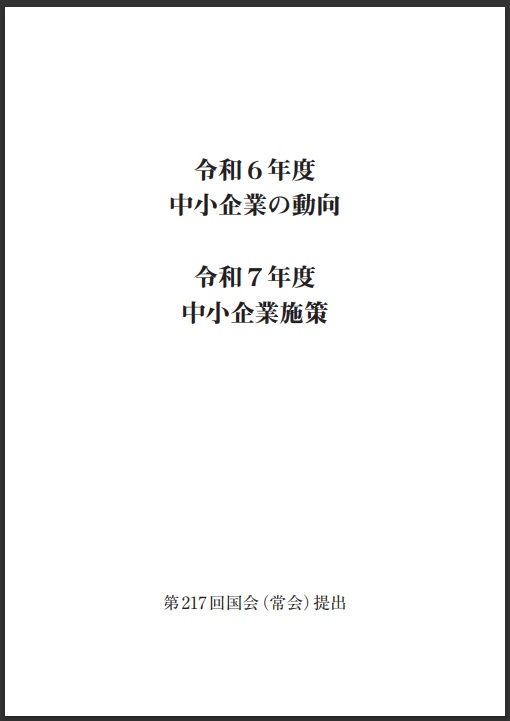


































![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方