中小企業であっても、求められるガバナンス領域は確実に広がっています。ただし、ガバナンスの全てを社長が引き受けるのは、制度的にも精神的にも適切な方法ではありません。ひとたび不祥事が表沙汰になれば大規模に拡散され、ときに会社の存続に関わる時代。会社も社長も救える、ガバナンス着手について解説します。
■事例:中小企業のガバナンス
Aさんは地方で製造業を営んでいます。創業から20年で社員は30人ほどの企業で、大企業の下請けとして地道に信頼を築いてきました。最近、Aさんの心に強く引っかかったニュースがありました。
机の上に置かれた一枚の新聞記事。見出しには「フジテレビ、前社長らに50億円の損害賠償請求」と書かれています。Aさんはその記事を何度も読み返しました。「大企業の話だ。自分には関係ない」、そう思おうとしていました。しかし、記事にあった「ガバナンス放置」「善管注意義務違反」の言葉が、重くのしかかっています。
Aさんは、最近起きた社内トラブルを思い出しました。「俺は、しっかりと見ているつもりだったのだが…」。実は、若手社員が上司の言動が不満で退職しました。その後、若手社員が投稿したと見られるSNSで会社の体質が批判され、取引先からも「御社の対応は大丈夫ですか?」と確認が入りました。
中小企業であっても、求められるガバナンス領域は広がる一方です。しかし、担当者を置くほどの余裕はありません。「コンプライアンスや人権の重要性は承知しているが、うちのような小さな会社がどう取り組んでいけばいいのか?」。社員の行動や取引先との関係、SNSでの評判、そして会社としての信用など…。すべての責任は社長のAさんに降りかかります。
しかし、具体的に何をどうすればいいのかがわかりません。専門家に相談するにも費用がかかり、社員に任せようにも、知識を持つ者は見当たりません。
Aさんは、社長という肩書きがいつの間にか「すべての責任を背負う者」になっていると気づいています。ふと、先代の社長であった父親の言葉を思い出しました。「社長というのは最後に責任を取る人間だ。でも、責任を取るということは、起きたことを知っていなきゃいけない」。その言葉の重みを、今になって実感しています。
「ガバナンスというのは、結局、社内が見えているかどうかの問題なのだと思う。けれども、現実の私は社内で何が起こっているか見えていない」
Aさんには、ガバナンス対策の答えがまだ見つかっていません。























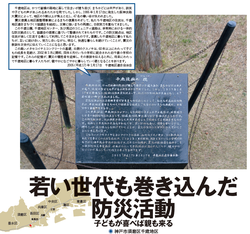














![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方