AIと著作権【前編】
AI生成物の「著作物」該当性

山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。
2025/08/07
弁護士による法制度解説

山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。

現代社会のあらゆる分野においてAI(人工知能)が活用されるようになってきました。そうした中で、AIに情報を学習させる際に著作権を侵害しているのではないか、AIで生成したコンテンツ(以下「AI生成物」)が著作権を侵害しているのではないか、AI生成物の著作権を侵害されているのではないかといったことが、産業界を中心として急速に関心を集めるようになってきました。
このようなAIと著作権を巡る問題点については、従来は、法的紛争化した後に、最終的には裁判所による審判を仰ぐ形で、個別具体的な決着が図られてきました。この過程で数々の裁判例が積み上げられ、また、他の事案にも適用可能な一般論を示した「判例」も生み出されてきたところです。

本来であれば、AIと著作権を巡る問題も従来のような形で司法判断が示されていくのを待つということになるのですが、これを待っていたのでは、現代社会におけるAIの急速な発展・利用とこれに伴う社会の急速な変容に耐えられない諸問題が噴出することは明白です。
そこで、「生成AIと著作権の関係に関する懸念の解消を求めるニーズに応えるため、生成AIと著作権の関係に関する判例及び裁判例の蓄積がないという現状を踏まえて、生成AIと著作権に関する考え方を整理し、周知すべく取りまとめられた」(考え方3頁)のが「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日・文化審議会著作権分科会法制度小委員会)(以下「考え方」)です。
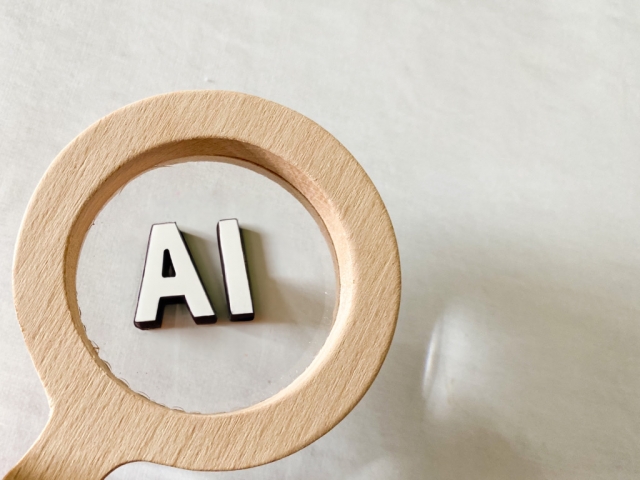
考え方は、「生成AIと著作権の関係についての一定の考え方を示すものであって、本考え方自体が法的な拘束力を有するものではなく、また現時点で存在する特定の生成AIやこれに関する技術について、確定的な法的評価を行うものではない」(考え方3頁)とされていますが、AIと著作権について検討する際には必読といえる、極めて重要な資料です。
考え方では、➊開発・学習段階、➋生成・利用段階、➌生成物の著作物性という、大きく3つの段階・論点に分けて検討された上で、それぞれに詳細な考え方などが示されています。今回は、著作物とは何かという、過去の記事でご説明した点の振り返りも兼ねる趣旨で、上記➌を取り上げて、AI生成物の「著作物」該当性について、考え方を踏まえながら、ご説明したいと思います。
おすすめ記事

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05



中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/03



発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26


※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方