代表取締役等住所非表示措置とは
代表取締役等住所非表示措置の概要、メリット・デメリット等

山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。
2025/11/07
弁護士による法制度解説

山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。

会社の登記事項証明書(かつての登記簿謄本)を取得し、ご覧になられたことはありますでしょうか。会社が融資を受ける際、新たな取引先と大きな契約をする際、訴訟提起をする際などに、登記事項証明書を取得なさると思います。
登記事項証明書に記載されている事項としては、例えば、株式会社の履歴事項全部証明書には、会社法人等番号、商号、本店、公告をする方法、会社成立の年月日、目的、発行可能株式総数、資本金の額などがあります。
そして、このような登記事項の中には、役員に関する事項も含まれており、代表取締役については、氏名のみならず、(自宅の)住所も記載されています。登記事項証明書は、誰でも取得することができるものですので、代表取締役の方については、その会社の大小や有名無名を問わず、住所が一般に公開されているということになります。

住所というのは、プライバシー性の高い情報ですので、公開されてしまうことに強い抵抗感がある方も多くいらっしゃるものと思います。とりわけ、インターネットやSNSが普及した現代社会において、代表取締役の住所が「晒される」というリスクもあり、従前どおりの登記制度であると、起業の躊躇(ちゅうちょ)、ストーカー等の被害等の誘発につながりかねないという懸念が指摘されるようになっていました。
こういった社会情勢や懸念などを受けて、商業登記規則等の一部を改正する省令により、代表取締役等住所非表示措置が創設され、令和6年10月1日から施行されています。
この代表取締役等住所非表示措置の施行から1年超となりましたが、私自身の経験として、訴訟提起等のために登記事項証明書を取得しても、ほとんどの株式会社で代表取締役の住所の全部が記載されているように思われ、まだ同措置が十分に利用されているとは言い難いのではないかと感じています。
そこで今回は、代表取締役等住所非表示措置について取り上げ、概要やメリット・デメリットなどをご説明してみたいと思います。
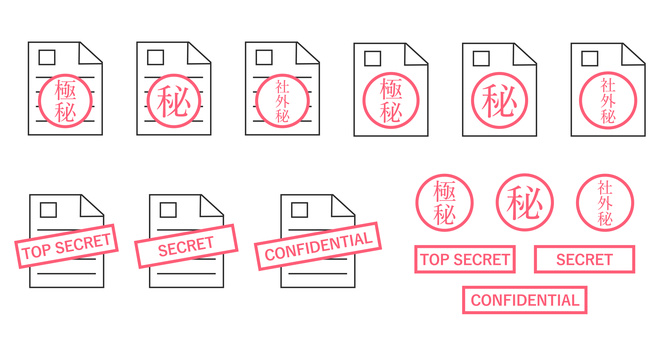
代表取締役等住所非表示措置は、要件を充たした場合に、株式会社の代表取締役等(=代表取締役・代表執行役・代表清算人)の住所の一部(=住所の行政区画以外の部分)を登記事項証明書や登記事項要約書などに表示しないこととする措置のことです。ここで、重要なポイントとしては、以下のとおりです。
第一に、株式会社のみに適用されます。持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)、各種法人(社団法人、財団法人、NPO法人等)、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、限定責任信託等は適用対象外です。また、会社法上は株式会社として扱われている有限会社(いわゆる特例有限会社)も適用対象外です。
第二に、住所の全部が非表示になるのではなく、住所の行政区画以外の部分が非表示になります。住所として、市区町村まで(東京都は特別区まで、指定都市は区まで)は表示されます。
第三に、住所の非表示の制度であって、住所が登記事項でなくなるものではありません。代表取締役等の住所については、代表取締役等住所非表示措置が適用される場合であっても、登記義務があります。このため、例えば住所変更の場合には、変更登記が必要です。
おすすめ記事

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05



中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/03



発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26


※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方