AIと著作権【中編】
AI生成物の生成・利用段階における著作権侵害

山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。
2025/08/27
弁護士による法制度解説

山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。
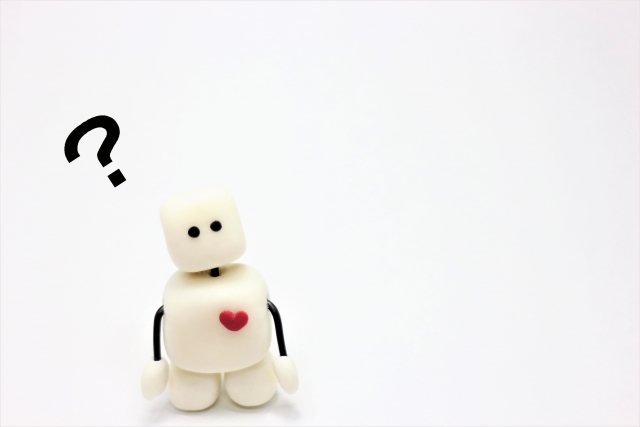
前回、「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日・文化審議会著作権分科会法制度小委員会)(以下「考え方」)をご紹介する形でAI生成物の著作物該当性につき、ご説明しました。
今回、AI生成物の生成・利用段階における著作権侵害について、同じく考え方をご紹介する形でご説明してみたいと思います。

著作権とは権利の束である、などとよく表現されます。それは「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」(著作権法21条)とされる複製権、「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する」(著作権法22条)とされる上演権・演奏権といった諸権利を総称して著作権と呼ばれているためです。
そして、これらの諸権利を侵害する行為が著作権侵害ということになります。つまり、著作者が「その著作物を」複製等する権利を侵害することが著作権侵害ということになるのです。
このため、著作権侵害の要件として、既存の著作物との①類似性と②依拠性が導き出されます。
これにつき、考え方においても、著作権侵害の要件については、「生成AIにより生成物を出力し、その生成物を利用する段階(略)では、生成物の生成行為(著作権法における複製等)と、生成物のインターネットを介した送信などの利用行為(著作権法における複製、公衆送信等)について、既存の著作物の著作権侵害となる可能性があり、この場合においては、従前の人間がAIを使わずに行う創作活動の際の著作権侵害の要件と同様に考える必要がある」(考え方32頁)とされており、AI生成物の生成・利用段階における著作権侵害の要件についても、従来と同様であることを前提としています。
その上で、生成AIの特殊性を踏まえた考え方が示されています。
著作権侵害が認められるためには、既存の著作物と少なくとも類似性が認められる必要があります。これが類似性の要件です。

そして、著作物の類似性は、著作物中の「創作的表現部分が共通している場合に限り肯定される」(愛知=前田=金子=青木『【LEGAL QUEST】知的財産法〔第2版〕』2023年・有斐閣、292頁)ことになります。これに関し、判例・裁判例においては、表現上の本質的な特徴を直接感得することができるか否かという判断基準が用いられてきました。
これにつき、考え方においても、「AI生成物と既存の著作物との類似性の判断についても、人間がAIを使わずに創作したものについて類似性が争われた既存の判例と同様、既存の著作物の表現上の本質的な特徴が感得できるかどうかということ等により判断されるものと考えられる」(考え方33頁)とされ、従来と同様の判断基準により判断されるものであろうとされています。
おすすめ記事
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方