2025/09/24
カムチャツカ半島地震
7月30日、ロシア・カムチャツカ半島付近の地震による津波が日本列島に到達。太平洋沿岸部を中心に広い範囲で津波警報が発表された。今回、大きな被害はなかったが、南海トラフ地震では短時間でより大きな津波が襲う。教訓として残ったものは何か。企業の振り返りと専門家へのインタビューを通じ、津波対策の課題と改善点を探る。
南海トラフ地震に生かす教訓は?
揺れの体感がともなわないまま影響が長時間にわたった遠地津波はどのように引き起こされたのか。より大きな津波が予想される南海トラフ地震にどのような教訓を残したのか。津波工学を専門とする東北大学災害科学国際研究所の今村文彦教授に聞いた。

1961年山梨県生まれ。89年東北大学大学院工学研究科博士後期課程修了。東北大学工学部助手、同大学院工学研究科附属災害制御研究センター助教授、教授を経て、2014年~23年同災害科学国際研究所所長。主な専門は津波工学、自然災害科学。中央防災会議専門調査会などのメンバーを歴任し、現在、復興庁復興推進委員会委員長、一般財団法人3.11伝承ロード推進機構代表理事などを務める。
長時間の警報による負荷大きく軽減策必要
――この7月、カムチャツカ半島地震による津波で、日本でも太平洋岸に警報が発表されました。この津波とその対応をどう振り返りますか?
日本に影響を与えた最近の津波をあげると、直近では2022年のトンガ噴火による津波、11年の東日本大震災、前年のチリ中部の地震、04年のインドネシアスマトラ島沖地震、その前は64年のアラスカ地震、60年のチリ地震、52年のカムチャツカ地震がある。
結構頻発しているうえ、過去のデータを見ると巨大地震は50年ほどの間隔で一定の時期に集中。そのため今回の第一報に触れたとき、巨大地震が再び活動期に入ったのではないかという感触を最初に抱いた。
津波に対する避難行動については、日本はやはり3.11の経験が大きい。多くの犠牲者を出したことで、啓発活動に力を入れてきた。そのため住民や企業、自治体もかなり知識を身につけている。
ただ、今回のような遠地津波は揺れの体感がなく、危機を実感しにくい。体感がないまま注意報・警報だけが発表される状況は、おそらく戸惑いが大きかっただろう。しかも真夏の炎天下という条件が重なり、避難行動のハードルは高かったと思う。
警報は適切も予測は限界
――気象庁の津波警報は適切だったでしょうか?
妥当だったと思う。観測記録による最大の津波高は1.3メートルだが、観測点のないところまでフィールド調査したなら、おそらく数メートル以上の場所もあるであろう。実際、北海道では浸水があった。また海域に目を向ければ、養殖施設や船舶などで被害は確実に起きていた。
揺れがともなわず危機を実感しにくい特徴があった半面、気象庁の発表は、情報として正確だったと思う。注意報から警報への切り替えも観測データにもとづいている。遠地津波ではこのような客観的な情報を入手し、常にアップデートすることが重要だ。
ただ、今回のように複雑に挙動する遠地津波は、最大波がいつ来るのか、影響がどのくらい継続するかがわからない。警報の状態が長時間に及ぶ可能性があるということで、そのため一次避難場所は1カ所でなく、複数箇所を用意したい。
さらに炎天下で、屋根もない高台しか避難場所がない状況では、避難者は体調を崩してしまう。安全確認のうえで別の避難場所に移動するといった柔軟な選択肢を取れるようにしておくことが必要だ。
――気象庁の警報は妥当だったとのことですが、遠方からの津波の情報をどのように得ているのですか?
まず、港や沿岸部には海面水位を観測する検潮所がある。これは世界中にあり、リアルタイムで情報を共有できるようになっている。加えて、日本では「S-net(エスネット)」システムというが、比較的深い海でも、地震に加え津波を観測できる装置がある。
しかし、遠地津波はさまざまな方向とスピードで到達する。天皇海山列に反射したり、フィリピンやニュージーランド、果てはチリまで行って反射したり、浅瀬で速度が落ちたり。それらが重ね合わさることで最大波が遅れ、長時間にわたり影響が続く。この複雑な挙動を予測するのは、いまの解析技術では困難だ。
インタビューの他の記事
おすすめ記事
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/03
-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26
-








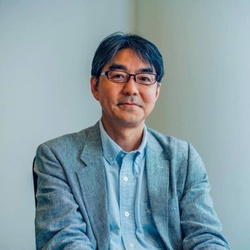
















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方