パンデミック時の感染者公表をどうする?
第37回:オールハザードBCPの課題

林田 朋之
北海道大学大学院修了後、富士通を経て、米シスコシステムズ入社。独立コンサルタントとして企業の IT、情報セキュリティー、危機管理、自然災害、新型インフルエンザ等の BCPコンサルティング業務に携わる。現在はプリンシプル BCP 研究所所長として企業のコンサルティング業務や講演活動を展開。著書に「マルチメディアATMの展望」(日経BP社)など。
2025/09/19
企業を変えるBCP

林田 朋之
北海道大学大学院修了後、富士通を経て、米シスコシステムズ入社。独立コンサルタントとして企業の IT、情報セキュリティー、危機管理、自然災害、新型インフルエンザ等の BCPコンサルティング業務に携わる。現在はプリンシプル BCP 研究所所長として企業のコンサルティング業務や講演活動を展開。著書に「マルチメディアATMの展望」(日経BP社)など。
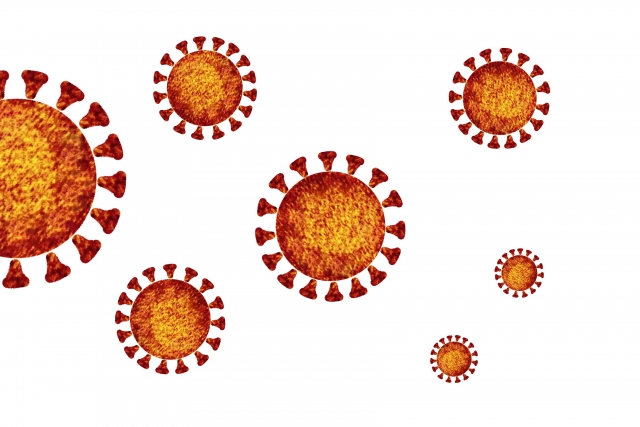
2009年に発生し、後に豚インフルエンザとして知られる新型インフルエンザウイルスによる世界的なパンデミック、2019年12月31日に発生したとされる新型コロナウイルスによる世界的なパンデミック。
このように、10年ごとに新興・再興ウイルスによるパンデミックが発生すると仮定すると、次なるパンデミックの発生は2029年。あと4年(!?)で次の忌まわしいパンデミックがまた発生することなどと考えたくもない一方、サステナビリティ報告書に記載しなければならない上場企業のBCP対策においてはどうでしょうか?
首都直下地震や南海トラフ地震などの震災BCPだけでは十分とはいえず、水害、気候変動・地球温暖化対策、サイバーセキュリティ対策、そして感染症対策を含めなければならず、この数年、BCP担当者は経営陣からの指示に対し大いに混乱しているのではないでしょうか。
限られた企業内のBCP策定リソースを考えると、これらのオールハザードに対する BCP 対策として優先度が高いのは、まずはそれぞれの行動計画(タイムライン)策定だろうと考えられます。
パンデミックにおいては、2024年に政府行動計画(新型インフルエンザ等対策政府行動計画)が改定され、自治体などと連携した対策が整理されました。これをそのまま企業の行動計画に展開するのは難しいものの、考え方の端々に参考にすべき内容を見出すことができます。

パンデミック発生時、特に企業の頭を悩ますのは、自社内で感染者が発生した場合の広報(外部公表)です。新型コロナのケースを思い出してください。自動車メーカーやコンビニでは、1人の感染者が出たとして速やかな公表と事業所や店舗の閉鎖を行いました。その対応は社会的責任が大きい企業の行動と広報のモデルとして、他の企業も倣い、追随しました。
しかし、これらの企業の広報は「包み隠さず速やかに」という原則の一方、広がりをみせるパンデミックのケースにおいては、社会的混乱を助長したことも事実です。そのことを踏まえ、企業における感染者発生時の公表に対する考え方の例として、次のような整理をすることができます。
下表は、これらの方針を踏まえ、政府の主な取り組みと企業の広報方針等をまとめたものです。この範囲では、企業の広報方針にとってこれまでと大きな変更はないでしょう。
●政府の主な取り組みを踏まえた企業の広報方針
しかし、政府によるリスクコミュニケーション等、広報に関するステートメントに従うと、以下のような考え方になると考えています。
●リスクコミュニケーションまでを踏まえた企業の広報方針
ここでのポイントは、初動期、感染者が発生しても原則は「非公表」であることです。また「公表」に際しては、感染拡大の状況を鑑み、次ページのようなタイミングと内容が求められます。
企業を変えるBCPの他の記事
おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/01/27


発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26



報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点
ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。
2026/01/26

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン
家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。
2026/01/23



※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方