2025/11/11
定例セミナーダイジェスト
「うちに関係ない」はもはや通用しない
炎上の構造変化で高まる経営リスク
テクノロジーリスク勉強会 10月17日
Japan Nexus Intelligence ヘッドアナリスト
竜口七彩氏
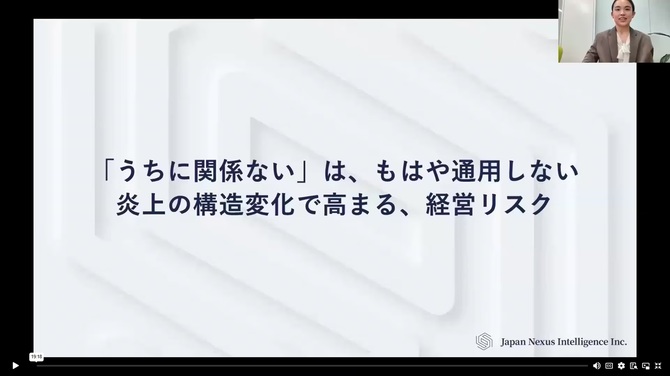
炎上の前兆はオンライン空間上の負のナラティブ
テクノロジーリスク勉強会は10月17日、オンラインで開催した。Japan Nexus Intelligence ヘッドアナリストの竜口七彩氏が、オンライン言論空間上の経営リスクとして「炎上」をピックアップ。従来の対策が及ばないほど影響が大きくなっていると指摘し、企業がどう向き合うべきかを解説した。
オンライン言論空間における偽情報やデマ、誹謗中傷のリスクは、政治家や有識者からも再三指摘されるところ。うち、炎上との向き合い方について竜口氏は、企業の発信や評判などの「情報」、情報に対する反応の「動機」、動機を引き金とした投稿拡散などの「集団的活動」という3つの視点で考えるべきと話した。
竜口氏は「この3つがネガティブに拡大すると炎上になる」とし、典型的な事例として昆虫食メーカーと大手家具販売会社の炎上を紹介。特に注意する点として「ナラティブ(物語)化」をあげ「単なる事実の列挙ではなく物語として語られると、政治的・社会的な善悪の意味が付与され、客観性が乏しくても受け入れられやすくなってしまう」とした。
そのため企業は最低過去1年をさかのぼり、オンライン空間上に負のナラティブがないかを調査・分析したうえで定期的なモニタリングを行うことが必要と指摘。もし発見したら「どういう人がどういう情報を、どういう動機で集団的活動に展開しているのかを把握したうえで、ナラティブに打ち勝つ対策を実施する必要がある」と話した。
参加者の声
・今の炎上が昔の炎上と違っている点、炎上のメカニズムに関してよく理解できました。
・とても興味深いお話しでした。オンライン空間の言説の分析に取り組んでみたいと思います。
・手を打つタイミングがよくわかりました。
・ナラティブ化することで特定の範囲以外にも拡散し、理解(誤解)が定着してしまうことに対するシンプルな解はないこと、ケースバイケースで対応を検討すべきである点を理解しました。
PRO会員(ライトは除く)のアーカイブ視聴はこちら。2026年1月31日まで。
- keyword
- リスクマネジメント
- 炎上
- 危機管理産業展2025
防災・危機管理ニュースの他の記事
おすすめ記事
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/17
-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05

























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方