2016/08/30
奥はる奈のロンドン大学危機管理講座
コミュニティ形成を狙ったアプローチ
このアプローチでは、日本の事例が話題になりました。テレビなどのメディアにも何度か取り上げられている、兵庫県加古川市にある加古川グリーンシティです。阪神・淡路大震災をきっかけに、加古川グリーンシティでは住民約2000人の自主防災組織が形成され、独自の警報システムや無線ラジオ、防災井戸といった設備が整備されたほか、月刊の防災ニュースレターの発行や住民への防災セミナーの開催、独自の防災ゲームの開発、さらに、日常的な挨拶運動により、暮らしの中に知らず知らずの間に防災知識や活動が増えるなど、多彩な住民参加型の防災活動が行われています。
注目すべき点は、夏祭りや餅つき大会といった、子どもからお年寄りまで楽しめる年間行事に合わせて、防災訓練を実施していることです。このような年間行事(イベント)+防災訓練にすることで、参加者の負担を下げ参加率向上を図りつつも、楽しく訓練に参加できるようになります。他にも、イベントの景品を防災用品や地域振興商品券にする、清掃などの他の地域貢献活動と併せて訓練もポイント制にして、ポイントに応じて景品を与えるなどの方法も面白いかもしれません。
以前、本誌でも取り上げられていましたが、湾岸タワーマンション「プラウドタワー東雲キャナルコート」でも、入居世帯の6割にあたる370世帯が参加する防災訓練が行われているとのことでした。防災訓練を行うことを目的にするのではなく、出身県ごとのの県人会、ママ友会など入居者コミュニティをつくり、それを防災力に生かせるようにした結果、多くの賛同が得られるようになったということです。
加古川グリーンシティでは、大西賞典さんという優れたリーダー(防災会長)の存在が大きいと言われています。このアプローチはリーダーとなる人材の存在、地域住民の意識などに左右されることから、全ての地域ですぐに同じことができるというわけではないでしょう。ですが、防災や危機管理の意識を根底から培うことができます。加古川グリーンシティの公式ホームページには、たくさんの取り組み例や防災マニュアル等が掲載されています。企業や組織の防災管理者や避難訓練企画者の方が参考にできるような事例が盛りだくさんですので、ご活用されてはいかがでしょうか。
訓練のハードルを下げるアプローチ
訓練実施には当然、時間やお金がかかりますし、企画側への負担も相当なものになります。ですから、多くの人が持続的に参加できるようにするためには、もう少しハードルを低くして、より多くの人が気軽に参加してもらう工夫も必要です。そこで考え出されたのが「シェイクアウト」という訓練です。この訓練は、日本の小学校の防災訓練をヒントに、2008年にアメリカで開発され、「誰でも、どこでも、気軽に(最短1分間)」をコンセプトに、世界中に広がりを見せています。日本では2014年の参加登録者数が445万人以上と言われています(日本シェイクアウト提唱会議調べ、2014年12月現在)。
訓練内容は「低く(Drop)、頭を守り、(Cover)、動かない(Hold on)」の安全確保行動が中心で、家庭や職場、学校等の日常の場で気軽に参加することができます。
身の安全確保という簡単なものに留まりますが、その後、個々の家庭や企業の状況に応じて、避難訓練や救助訓練、BCP訓練に繋げることもできます。このような訓練を繰り返すことで、いざという時の適切な危険回避行動がとれるようになりますし、少しずつでも住民や従業員一人ひとりが考え、日常の防災対策を確認する機会になるという意味ではぜひ活用していきたい訓練です。
質をどう兼ねるか
さて、これまで訓練の参加率を上げるためのいくつかの方法を先行事例を含めご紹介してきました。どのアプローチがいいというわけではもちろんありません。3つのアプローチを組み合わせて、できることから取り組んでいくことが大事だと思います。
また、形式的に訓練に参加しました、訓練を実施しましたというだけでなく、訓練の内容や結果を分析することで、参加者の意見を次の訓練に反映することができるようになりますし、ニュースレターや掲示板等に成果を掲示することで参加できなかった人へのフォローアップにもなります。
つまり、紋切り型の訓練ではなく、それぞれの実情に合わせ、問題解決に繋がる訓練を実施し、自主性やコミュニティを育むことが大事です。企業に置き換えれば、部署を超えた人材のネットワークの形成に繋げることもできます。そうした組織づくりの目的を達成する手段として訓練を活用することもできるでしょう。
おわりに
世界の中でも飛び抜けて地震の多い国、日本。軽い地震なら頻繁に体験している私たちは、地震に対して危機感を持たなかったり関心が薄かったりと、変に慣れてしまっているところがあります。東日本大震災を受け、チリやペルーなどの他国で国民の防災意識が高まっているのに対し、日本の防災の日の訓練参加率は年々下がっていると聞いています。例えば、国レベルで防災の日の訓練を強化して、官庁、企業、自治体、国民の全員が防災訓練をすることを規則で定めてもよいかもしれません。つい先日、毎年3月11日を「東日本大震災の日」と定める法案が提出されました。その日に、シェイクアウトでも、お祭り的な訓練でも、法律に定められた訓練でも、皆が何かしら防災のために訓練をする日が1年に1日ぐらいあってもいいのではないでしょうか。
訓練の目的は人々を怖がらせるのではなく、万が一の場合に備えて生き抜く自信を身に付けることにあります。各家庭で「万が一の時の災害対策」を話し合うとともに、近所にも声をかけ、個々人が日頃の危機管理コミュニティを築くことに目を向けてほしい、と強く思います。
(了)
- keyword
- 奥はる奈のロンドン大学危機管理講座
奥はる奈のロンドン大学危機管理講座の他の記事
- 最終回 ロンドンオリンピックのBCP・危機管理対策とは
- 第5回 世界で最も危険な火山 –ヴェスヴィオ火山の噴火対策–
- 第4回 キューバから見る真のレジリエンス
- 第3回 プランではなく、プランニングが重要
- 第2回 訓練の参加率を向上させる方法とは?
おすすめ記事
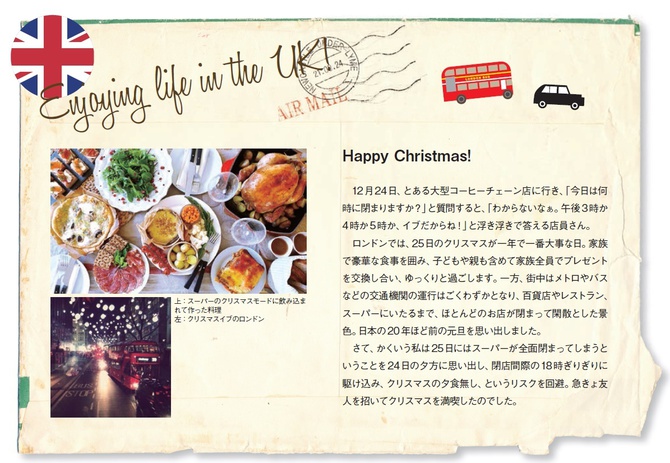


































![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方