2016/11/13
誌面情報 vol49

在日フランス商工会議所が首都直下地震を想定しBCPマニュアルを策定した背景には、今後30年で70%の確率で地震が発生することへの強い危機感がある。一方、商工会議所の会員企業の多くは中小企業。日本でも、中小企業へのBCPの普及は大きな課題となっているが、今後、同商工会議所が、どのようにBCPを普及させていくかは大いに注目したい。海外企業のBCPから学ばされることも多い。事業継続マネジメント委員会の委員長でマニュアルを策定したピエール・スベストル氏に聞いた。
Q.なぜこのようなマニュアルを作ったのか?
日本では今後30年で70%の確率で首都直下地震が起きると言われている。多くの在日フランス企業はとても強い危機感を持っているが、どうしたらいいのか、何から始めたらよいかが十分に理解されていない。
私は、2010年まで10年間にわたり日産自動車の内部監査役として同社のリスク管理に携ってきたが、そこで得た経験を基に、最低限、すべての企業と従業員がやらなくてはいけない対策をマニュアルにまとめれば、商工会議所の会員企業のような中小企業にとっても参考にしていただけるのではないかと考えた。
商工会議所の会頭で日本ミシュランタイヤ株式会社の社長であるベルナール・デルマス氏も事業継続の必要性を感じ、今回のプロジェクトを応援してくれている。
Q.今回のBCPマニュアルの特徴は?
策定を始める前に、BCPを既に策定している比較的大きな企業に集まってもらいミーティングを開き、どのような内容で、どう運用しているかなどについてヒアリングを行った。その際思ったことは、大企業のような細かなグラフや組織図を中小企業に書かせても、多くの企業には理解されないということ。そこで、とにかく重要なことだけに的を絞り、なぜその項目が必要かを把握した上で、実際にそれが達成できているか否かを、自分でチェックできるようなものが必要だと考えた。
したがって、マニュアルの前半には、首都直下地震が起きるとどのような状況になるのか、企業は何に困るのかを簡潔に説明し、その後で、従業員として、企業としてどう備えるべきかをチェック項目としてまとめている。
単にチェックをするだけでなく、従業員向けの項目なら、一人ひとりの事情に応じて、家族の居場所、避難所、近くの病院、複数の通信方法などをそれぞれ書き込んでもらうようなスペースも設けている。企業向けの項目なら、リーダーやサブリーダーの名前、顧客対応や取引先対応の責任者の名前、安否確認などの方法、教員の教育状況、ITのバックアップ状況、目標復旧時間など、各社がBCPを発動する上で不可欠な項目を書き込んでもらえる。ただし、このマニュアルは基本項目だけを簡潔にまとめたもので、これだけで不十分なら、さらに内容をグレードアップしていけばよい。
Q.日本でも中小企業へのBCPの普及は非常に難しい。どのように普及していくか。
中小企業の場合、BCPの必要性は理解していても、時間も費用なく、コンサルティング会社などにお願いができない企業が多いため、まずはできることから始め、それをPDCAで見直していく形を作ることが大切だと考えている。
ただし、大企業でも、BCPを本気で作りはじめたのは最近のことだ。必要なことが分かっても、手間がかかる、費用がかかるなどの言い訳をして、いつも先送りにされてしまう。本来なら、国が策定を義務化して、策定の有無によって株価に影響がでるなどの仕組みにすれば、BCPへの取り組みは一気に加速するだろうが、こうした方法にしたとしても、中小企業が大企業と同じように取り組むことは難しい。 逆に、中小企業にとっては、BCPを国が認証して公開できるような制度にするなど、何らかのインセンティブになる方法を考えた方がいいのではないか。
Q.計画を策定するだけではなく、実際にどれだけ被災時に動けるか実効力が問われている。
紙の計画を作ることよりは、体で覚えられるようにすることが大切だ。それは、階段を上から下に降りるような避難訓練を繰り返し行うという意味ではなく、階段で逃げる必要があるのか、留まって事業を継続すべきなのか、状況を判断し、どうするか意思決定するようなことを体で感じ取る「訓練」が必要ということ。例えば、安否確認の方法を繰り返すだけでなく、帰宅途中で大地震があって、すべてのコミュニケーションが途絶えた場合、どうやって家族と連絡を取り合うのか、どこに行くのか、どこで待つのか、そのような状況判断や意思決定の必要性を体感していく訓練が求められると思う。
Q.東日本大震災ではフランス人は比較的多くが国外退去をしたと報じられている。
確かにフランスは、チェルノブイリ原子力発電所事故の経験もあったことから、福島原子力発電所の事故後、飛行機で国民の帰国支援をするなど国外退避を呼びかけた。しかし、これは一般市民への話で、基本的に政府が企業の行動を抑えつけることはできない。
3.11では一時的に通信がつながりにくくなったり、交通が麻痺したが、大パニックに陥ったわけではなく、ライフラインは比較的早く復旧した。もし近い将来、首都直下地震が本当に起きれば、当分の間、東京から外に出ることはまずできないだろう。企業は、それぞれが置かれている状況の中でどう耐えるかを事前に考えておく必要がある。
Q.欧米の企業は、地震や新型インフルエンザの大流行、火災など、事象に応じたBCPを作るよりは、むしろ、建物が使えなくなったらどうする、スタッフが集まれなくなったらどうする、ITが使えなくなったらどうするなど、災害によって引き起こされるリソース(資源)の状況に対応するBCPを作る傾向にあると聞いている。首都直下地震を対象にした理由は?
東京の場合、首都直下地震のリスクが大きすぎる。理想としては、リソースベースでBCPを作ることが重要だろうが、前提として、地震が起きた時に地域や企業の内部、周辺環境がどのようになるのかを把握することは不可欠。ただし、今回のマニュアルを見てもらえばわかるように、例えば、会社に来られない場合は自宅から仕事ができるようにしておくなど、地震以外の脅威が起きても有効に機能する内容にはなっていると思う。
Profile
ピエール・スベストル
1977年にミシュランタイヤの業務で初来日。以来、メガネレンズのエシロール、エアバスの業務で日本に滞在。2000年から日産自動車の内部監査に携る。2010年に退職し、現在はコンサルタントとして活躍する。
(了)
誌面情報 vol49の他の記事
- 市民によるトリアージで町を救え
- 仏商工会議所が首都直下地震のBCP
- 避難訓練だけを繰り返しても意味がない
- 『分かりやすい』伝え方 防災では定義が広すぎる
- なぜルールは破られる?気付きと動きで安全文化を構築
おすすめ記事
-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/01/27
-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26
-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点
ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。
2026/01/26
-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン
家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。
2026/01/23
-

-

-








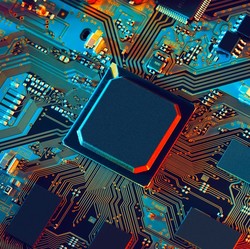

















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方