2016/11/08
誌面情報 vol49

「ルールを決めても守られない」「取り組みが継続しない」…、防災やBCPを組織全体に浸透させることは簡単ではない。安全文化を根付かせるには、従業員一人ひとりの危機意識とモチベーションが不可欠である。株式会社インターリスク総研災害リスクマネジメント部安全文化グループ上席コンサルタントの小山和博氏に聞いた。
(編集部注:この記事は「リスク対策.com」VOL.49 2015年5月25日掲載記事をWeb記事として再掲したものです。2016年11月9日)
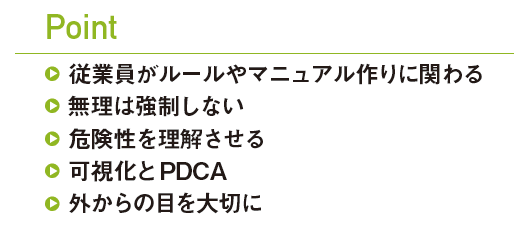
・労働安全の分野では、早くから「安全文化」という言葉が使われていますが、組織の文化にするとはどういうことなのでしょうか?
労働安全にしても防災やBCP(事業継続計画)にしても、組織文化にするということは「誰も何も言わなくても組織を構成する従業員一人ひとりが自ら正しく行動できるようにする」ということ。「文化」は英語ではカルチャー(Culture)ですが、その語源はカルティベート(Cultivate)で、「耕す」「根付かす」という意味。組織全体に安全意識、あるいは防災・BCPの意識と行動を根付かせることが求められます。
世界で最初に安全に関する組織文化の必要性が言及されたのが1986年のチェルノブイリ原子力発電事故です。1991年に国際原子力機構(IAEA)が同事故の調査報告書をまとめ、その中で事故の最終的な原因が「安全文化の欠如」と指摘しました。この時、初めて安全文化=セーフティカルチャーという言葉が使われたのです。
この報告書では、「原子力発電所の安全の問題には、その重要性にふさわしい注意が最優先で払われなければならない。安全文化とは、そうした組織や個人の特性と姿勢の総体である」と定義がなされました。
・必要性は理解できても、それを達成することは容易ではありません。
あらゆる組織には、安全にかかわらず、独特な文化が存在します。和気藹々(あいあい)とした文化の組織もあれば、ガチガチのトップダウン文化を持つ組織もあります。重要なことは、こうした組織文化は良かれ悪しかれ、構成員の行動に必ず影響を与えるということです。
例えば、私が以前勤務していた飲食業界について考えてみますと、ある外食チェーンでは、次のように手の洗い方をマニュアルで決めていました。「指輪などは雑菌が繁殖する恐れがあるので外して、手首を露出して30秒石鹸をつけて洗い、しっかり流水で流す。手荒れ防止の観点からお湯は使わない…」
手荒れは、黄色ブドウ球菌という食中毒菌の温床となることから、外食産業にとっては大きな問題となります。この会社では、全店にマニュアルを配布し、手洗い場などに貼り出していましたが、各店によってサブカルチャーが発生して、このルールが徹底されていないことがありました。
こうしたサブカルチャーは、上司の指導を通じて生じるケースもあるし、下から自然に湧き上がってくる場合もあります。上からの例は、管理監督者が、会社の方針を無視して「長時間、手を洗っている時間は無駄だからもっと早く手を洗え」など勝手にルールを変更してしまうようなケース。下からの例は、声が大きい人が「こんな面倒なことやめてしまおう」「冬は手が冷たいからお湯を使おう」など、やはり勝手にルールを無視してしまうケース。こうしたサブカルチャーの影響を防ぎ、よい組織文化を根底から創り上げていくことが重要な経営課題と言えます。
誌面情報 vol49の他の記事
- 市民によるトリアージで町を救え
- 仏商工会議所が首都直下地震のBCP
- 避難訓練だけを繰り返しても意味がない
- 『分かりやすい』伝え方 防災では定義が広すぎる
- なぜルールは破られる?気付きと動きで安全文化を構築
おすすめ記事






































![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方