2016/11/10
誌面情報 vol49

防災やBCP(事業継続計画)担当者の頭を悩ますのが、従業員の危機意識を高める方法だ。どんなに重要性を説明しても聞き流されてしまうのはよくあること。しかし、ひょっとしたら、「伝え方」を変えるだけで、社員の防災意識が変わるかもしれない。
『今までで一番やさしい経済の教科書』(ダイヤモンド社)『カイジ「命より重いお金の話』!」(サンマーク出版)などを執筆し、難解な経済の理論をわかりやすく届けているベストセラー作家・木暮太一氏に、人を動かすことができる「伝え方」について聞いた。
(編集部注:この記事は「リスク対策.com」VOL.49 2015年5月25日掲載記事をWeb記事として再掲したものです。)
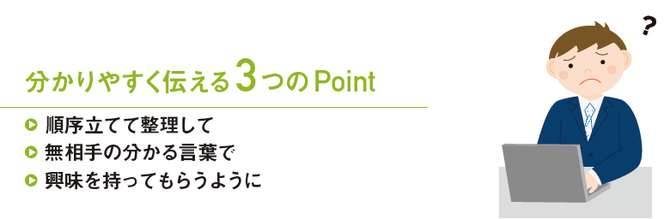
・従業員の防災意識を高めるには、どのような説明の仕方が求められるのでしょうか?
防災に限らず、物事を分かりやすく説明するには、3つのポイントがあります。1つ目は、伝えたいことを相手が理解しやすいように順序立てて整理して伝えるということ。説明がバラバラで散らばっていたら相手は何を言われているのか整理できないので、目的と対策を箇条書きにしてみるなどの工夫をしてみる。2つ目は、相手が分かる言葉で伝えるということ。
いきなり、新入社員に専門用語で「BCPが大切」などと伝えても、当然理解されません。「BCPって何ですか」と聞き返せない人もいるはず。理解できていないことが、行動に移せるはずがありません。ですから、相手が分かる言葉に置き換え、かみ砕いて伝えることが大切です。
3つ目が一番重要で、興味を持ってもらうように説明するということです。どんなに整理して、分かりやすい言葉で伝えても、そもそも興味を持たないことを、人は聞き入れようとはしません。
例えば、既婚の中高年の方に対して、ウェディングの話題を分かりやすく説明したところで、聞いてくれる人は少ないでしょう。興味を持ってもらうためには、「自分にその事がどのように関係してくるのか」ということを理解してもらう必要があります。
中高年にウェディングの話を聞かせるなら、子どもや孫が結婚する場合をイメージさせるような手法が有効でしょう。同じように、防災についても、あなたがどのように関係しているのかを示してあげる必要があります。これら3つのポイントを満たすことが大切です。
・この3つを順序立てて伝えればいいのでしょうか。
いいえ、違います。「伝えたい」対象によって、順番も重きも異なります。相手に応じて、課題となっているポイントを見極め、伝え方を変えてください。例えば、ある程度防災の知識を既に持っている人に対して伝えるなら、3番の「興味を持たせる方法」が特に求められるでしょうし、小さなお子様を持つ母親で防災の意識はとても高いのだけれども、何をやっていいのか理解できていないような方に対しては、1番の「整理して伝える」や2番の「分かりやすい言葉を使う」ことを重視して伝えるべきでしょう。
・特に3番は難問のように思います。
理由は2つあるように思います。1つは、防災の定義が広すぎて、何を指しているかよく分からない。東日本大震災のような大災害をイメージしているのか、ちょっとした火事なのか、もしくは電車が止まったときの社内対応なのか、説明を聞いている立場からすると、何に備えろと言われているかが理解しづらいのです。
もう1つは、今の話に聞こえないということです。特に大災害をイメージしろと言われても、「今でしょ」ではなく、「今じゃなくていいでしょ」ということになってしまう。
「災害は忘れたころにやってくる」とはよく言ったもので、“災害に備えるのが大事です”と言われて反論する人はいませんが、では、いつ来るかと問われれば、たぶん「今じゃない」と皆が思っている。防災対策が必要なことは、誰でも理解できるでしょうが、今の問題と受け止めてもらえなければ、結局、自分とは関係のない、興味の持てないことにされてしまいます。
誌面情報 vol49の他の記事
- 市民によるトリアージで町を救え
- 仏商工会議所が首都直下地震のBCP
- 避難訓練だけを繰り返しても意味がない
- 『分かりやすい』伝え方 防災では定義が広すぎる
- なぜルールは破られる?気付きと動きで安全文化を構築
おすすめ記事
-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/17
-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05



























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方