2020/01/19
インタビュー
常に幅を持った行動を
ただし、気象庁や観測体制の指摘をしても仕方がない。それは、観測に十分な予算を投じていない日本政府の問題であり、予測を受け取る側の市民は、こうした現実も踏まえ、災害が全て正しく予測できていると考えるのではなく、少し幅を持って行動をするにようにしなくてはならない。
今の災害は、計画想定と最大想定の2つのレベルで想定を考えるようになっているが、実際にはその中間もあるだろうし、どのような被害になるかは起こるまで分からないということを改めて認識する必要がある。
「自分はこうだから大丈夫」という過信も禁物だ。例えば、増水した川の堤防を車で走ることは極めて危険だが、中には「自分は運転がうまいから絶対に川に落ちたりしない」と誇らしげに話す人がいる。増水した川の堤防が危ないのは、雨の中運転を誤る可能性が大きいからではない。水を含んだ堤防は柔らかくもなかのようにアスファルトの下がふにゃふにゃになり、走っているうちに路面が落ちるようなことが起きやすいからだ。路面が落ちればどんなに運転がうまくてもハンドルを取られ、川へ転落する。こうしたことは経験しないと分からないことだが、経験した時ではすでに遅い。カーナビの精度が高くなり、どこでも簡単に行けるようになったが、カーナビは堤防がもろくなっているようなことまで教えてくれない。
地震についても、家具の転倒防止をしているから大丈夫という人がいるが、南海トラフ地震のようなプレート型の大地震では、マグニチュード8以上で1分以上、9なら3分以上も強い揺れが続く。3分も強い揺れが続けば、どんな転倒防止をしっかりしていても大抵のものは倒れる。転倒防止というのは倒れるまでに多少の時間が生まれる意味であり、その間にしっかり安全を確保しなくてはいけない。さらに、直後に津波が襲ってくることを考えると、家具が転倒して家から外にすら出られない人が多数発生する。特に車いすを使った障がい者や高齢者は、避難がより困難になる。そうした事態も考えながら、地域全体で協力しながら安全な対策を考えていく必要がある。つまり、1つの対策を講じて、それに甘んじるのでなく、常に対策を見直し向上させていく必要があるということだ。
生活スタイルの変化とともに、災害による被害の出方も変わっていく。これまでこんな被害出てないから大丈夫というではなく、常に新しい知識を入れて、何が起こり得るのか想定を膨らませていく必要がある。
災害文明だけでは被害は減らせない
科学技術の発展により防災分野でも、緊急地震速報やハザードマップなど防災に役立つツールは次から次へと生まれているが、こうした災害文明だけがどんどん進んでいる一方で、避難などの行動が文化になっていない。避難情報を出しても逃げないというのは、避難が文化になっていないということ。社会の防災力を高めていくには、災害文明(装置)の上に災害文化(機能)が来なくてはいけないが、それが逆転して、小さく未熟な文化の上に大きな文明がアンバランスに乗っかる主客転倒の状態になっている。
古来から日本はさまざまな海外の文化を取り入れ、独自のものにアレンジしてきた。文明を生み出すことは下手だが、文化へと洗練するのは得意だった。それが、高度経済成長の時に所得が増え物があふれ、日本文化はつぶれてしまった。残念ながら、災害文化もその時一緒に捨て去られた。
あまり知られていないことだが、1959年の伊勢湾台風では平均30~35%もの人が避難をした。しかし高潮が迫りくる中、暴風雨で行き場を失い、多くの人の命が奪われた。当時は学校も木造で全てが指定避難所にはなっていなかったから、自分で安全と思う場所に逃げるしかなかった。当時に比べれば、今は家の構造も比べ物にならないほどしっかりしているが、逆に避難をする人は少なくなっているだろう。しかし洪水と違って、高潮は危険な状況になった時には最も雨風が強く、逃げることすらできないということが理解されていなければ、文明だけで被害を減らすことはできない。
文化は人間の知恵から生まれた行動を習慣化したもので、それを作り出すのは教育以外ない。今の学校で教えているような数字を覚える教育ではなく、命を守る教育が求められる。
例えば、明治維新で命を落とした人は3万人。一方、1861年から始まった南北戦争アメリカでは82万人が亡くなっている。人口は両国とも当時約3000万人だった。もっとさかのぼれば、太平洋戦争を除いて日本で一番多くの犠牲者を出したのは島原の乱(1637年)で、3万7000人が死んだとされるが、同じ1600年代に神聖ローマ帝国を舞台に繰り広げられた30年戦争では750万人が死んでいる。つまり、日本人はとても賢く無駄な血を流すことを避けてきた。こうした優れた文化を持ちながらも、災害については多くの死者を出してきた。
1894年から1895年まで続いた日清戦争で命を落とした日本兵は1万3300人。一方、戦勝ムードに包まれる中、翌年1896年の6月14日、戦勝パレードを全国的に行っていた夕方に明治三陸地震が発生し2万2000人の命が奪われた。こうした歴史を知らなければ災害文化は生まれない。
今、首都直下地震や南海トラフ地震起きれば、国がつぶれる。そんなことを言っても、皆本気で信じようとしない。目の前の河川が決壊するということすら、発生するまで誰も信じなかった。今こそ歴史が示してきたことに真摯(しんし)に向き合い、災害文化を築いていく必要がある。

【プロフィール】
河田 惠昭(かわた・よしあき)氏
関西大学社会安全学部・社会安全研究センター長・特別任命教授(チェアプロフェッサー)。工学博士。専門は防災・減災・縮災。現在、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター長(兼務)のほか、京大防災研究所長を歴任。京都大学名誉教授。2007年国連SASAKAWA防災賞、09年防災功労者内閣総理大臣表彰、10年兵庫県社会賞受賞、14年兵庫県功労者表彰、16年土木学会功績賞、17年アカデミア賞、18年神戸新聞平和賞受賞。現在、中央防災会議防災対策実行会議委員。日本自然災害学会および日本災害情報学会会長を歴任。
(了)
インタビューの他の記事
おすすめ記事
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/01/06
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/01/05
-
年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する
サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。
2026/01/04
-

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25
-

-

-

-

-









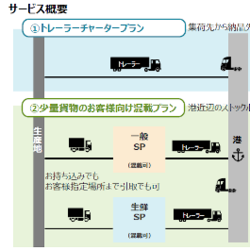














![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方