2020/04/17
ロックフェラー財団100RCに見る街づくりのポイント
オンラインサービスを強化
公共サービスへのアクセスの向上
ここでいう「アクセス」とは、物理的な意味ではなく、デジタル世界でのオンラインアクセスを指しています。オンラインで提供される公共サービスはパブリックデジタルサービスと呼ばれ、サンフランシスコ市民のみならず観光客やビジネス利用者などもターゲットとして、テクノロジーの活用による利便性向上を目指しています。
レジリエント戦略では、パブリックデジタルサービスの使い勝手をユーザーからフィードバックしてもらうこと、どんなデバイスからも容易にアクセスが可能なウェブサービスをもとに、使いやすさ向上のため常にアップデートすることを明記しました。従来フェイストゥフェイスのコミュニケーションを重視していた市役所において、ターゲットとなる市民などが気軽にオンラインで市にコンタクトできる土壌を作ることが目的です。これまでの考え方を抜本的に変える必要性が指摘されています。
同様の文脈で、各種公共手続きの簡略化も進めるとしています。従来市役所内で必要となるステップが複雑化していることから、利用者が「次に何をすればよいのか?」分からなくなっているとして、行政内部でのワークフローの見直しが掲げられています。承認システムをオンラインに移行することで、プロセスの透明化とステップの明確化を目指します。
エネルギーの地産地消
市役所が位置するエリアは、毎日数千人が訪れるサンフランシスコの中心地となっています。パレードやフェスティバル、時にはデモが行われ、にぎわいのあるエリアです。気候変動や干ばつといった不測の事態に備え、このエリアの持続可能性を高めるプロジェクトが進行しています。
水資源を遠くから持ってくるのではなく、地下水を利用した、オンサイトで再利用可能な水道システムの構築、同様にエリア内の電力消費を再生可能エネルギーに移行(太陽光パネルや廃物の活用)、サスティナビリティの考え方を市民に教育する、といった計画があります。これらのエネルギーシフトは、サンフランシスコ市内を走る公共交通機関にも適用する考えです。
パートナーシップづくり
テクノロジー活用を後押しするパートナーシップづくりも重要です。サンフランシスコ市のレジリエント戦略策定には、他の多くの市と同様に、多数のステークホルダーが関わっています。海面上昇による経済的インパクトは、民間のコンサルティングファームが計算しました。このように、民間企業の専門性を上手に活用することを重視しています。
リスク計測のほかに、オンラインでのコミュニケーションプラットフォームを提供する民間企業や、オープンデータの可視化を行う企業――オープンデータの可視化により地域のアセットや資源、脆弱性を共有することができます――との協働を強化する計画です。
市内企業とのパートナーシップに加えて、市外の地域単位や州単位でのパートナーシップ作りにも力を入れています。このときの窓口になるのが、レジリエンスオフィサーと、新設されるレジリエンス・リカバリーオフィスです。隣接するオークランドやバークレー、ロサンゼルスのレジリエンスオフィスとの連携がうたわれています。これらの市は、カリフォルニア州の中でもレジリエンスに熱心な都市であり、それぞれレジリエント戦略を定めています。
従来の考え方を変える
新型コロナウイルスの影響で、これまでのように外出がままならなくなると、重要となるのがオンライン上でのサービスです。サンフランシスコ市では、レジリエント戦略においてオンラインサービスの強化をうたっている点が素晴らしいと思います。特徴的なのは、従来の紙と対面による行政内部の承認プロセスを、「Outdated permit processes」(時代遅れの承認プロセス)と呼び、テクノロジー活用と市民教育により、「当たり前」を変えようとしているところです。
例えば災害発生後、人々が家にとどまるシチュエーションを想定して、人々のロケーションに関係なく生活に必要な手続きができることが大切であると記載があります。まさに今、新型コロナウイルス拡大の環境下でこの想定が現実になっています。
加えて、企業とのパートナーシップを明記している点も重要です。日本ですと、行政と企業、あるいは企業同士の関係は「委託―受託」の関係にとどまる場合が多いと思います。そういった関係性を超えて、レジリエンス実現に向けたパートナーとして、対等の関係性を構築する姿勢は、私たちも見習うところがあると思います。
ロックフェラー財団100RCに見る街づくりのポイントの他の記事
おすすめ記事
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/01/06
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/01/05
-
年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する
サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。
2026/01/04
-

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25
-

-

-

-

-








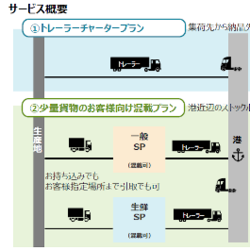

















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方