2020/10/30
2020年10月号 BCPビジネス
建築×防災 何が変わるか
摂南大学理工学部建築学科 池内淳子教授
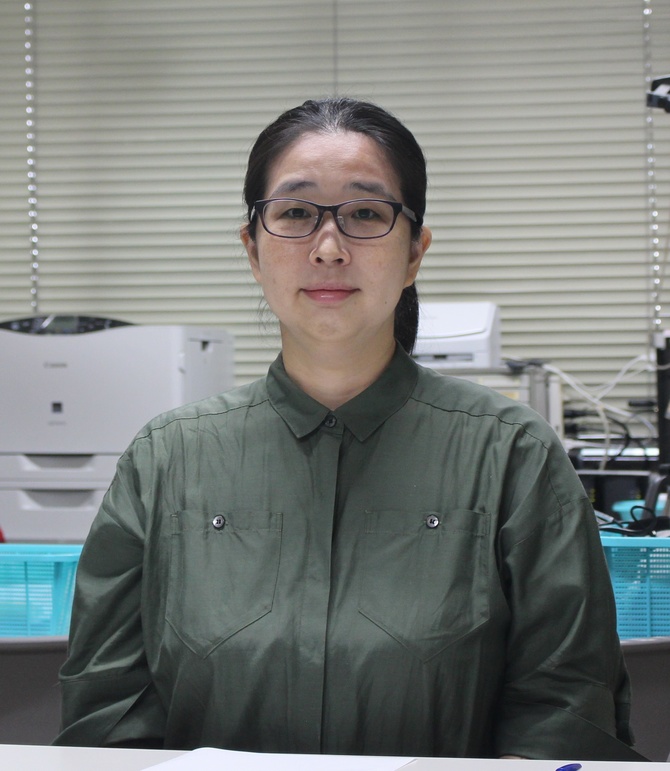
新型コロナウイルスの影響から脱し切れない日本社会。感染流行下の列島をたびたび豪雨が襲い、各地は複合災害への対応を余儀なくされている。近い将来の発生が予測される首都直下地震や南海トラフ地震も、抜本的な手が打たれないまま。だが、社会が変わろうとしている今は、これまでの防災を見直し、そのあり方を変えていく好機でもある。建築分野から都市防災や災害医療に携わる摂南大学の池内淳子教授に、現在の住まいや街が抱える課題と解決策を聞いた。(本文の内容は9月17日取材時点の情報にもとづいています)
https://www.risktaisaku.com/feature/bcp-lreaders
建物の「使用レシピ」が利用者に伝わっていない
――建築分野で防災に携わる立場から、今何が問題とお考えですか。
日本列島は他国に比べ地形・地質条件が厳しく、しかも地震や台風がひんぱんに襲いますから、建築の技術は世界有数です。加えて、建築基準法もある程度しっかりしている。一方で都市の中に古い建築が多く残っていますから、相応の被害は出るわけです。
都市が生まれ変わっていく中で、建築の被害の大小が混在してあらわれるのは仕方ありません。しかし総じてみれば、日本の建築は自然災害に強い。ただし問題は、建築を作るまでにリソースを注ぎ込み過ぎて、そのあとに目が行き届いていないことです。
その結果、昨年の台風19号で浸水した武蔵小杉のタワーマンションのように、住民と業者、行政との間にしばしば齟齬が生じる。要するに、災害時にどんなことが起こり得るか、何に留意しないといけないのか、どうすればよいのかといった情報が、利用者に伝わっていないのです。
電気製品でも薬品でも、玩具でも、いわゆる「使用上の注意」がくどいほど書いてあります。しかし建築には、そうした「使用レシピ」がない。「このマンションは水につかる可能性があります。その場合エレベーターは使えなくなります」なんて、普通いいませんよね。
引き渡したら、メンテナンスはするけれど、あとは知りませんといった売り方になっているので、利用者との間にかい離が生じる。建築側として、建物の使い方をもっと伝えていかないといけないでしょう。そうした視点が欠けているところに自然災害が頻発しますから、必然、被災者の数も多くなるのです。
――コロナ禍での問題という点ではいかがでしょうか。
同じです。例えばコロナ禍によって避難所の感染症対策が注目されましたが、ノロウイルスやインフルエンザ、あるいはエコノミークラス症候群といった健康問題は以前からあります。だから想定はできている、しかし一般の利用者には伝わっていない。
戸建て住宅もそうで、玄関で手洗いできる家が売れているそうですが、これは花粉症の時からいわれていたこと。玄関は広めにとか、外に水まわりをとか、今に始まったことではありません。敷地面積やコストの問題などから、これまで根付かなかったのです。
逆にいえば、コロナが流行したことで、問題を解決するチャンスが来たともいえる。技術はあるわけですから、それを柔軟に組み合わせていけば多様性のある建築ができます。感染症が来ても、自然災害が来ても、ある程度対応できるオプションを付加し、なおかつ、利用者に使い方を説明する。そこを今やらないといけないでしょう。
――ハザードマップで、自宅や職場のリスクを確認する人などは増えているのではないでしょうか。
おそらくもう一歩踏み込んで、具体的に想像しておかないといけない。確かにハザードマップで建物の揺れやすさや浸水度合いは分かりますが、それを自分の家や職場に当てはめて「これが倒れる」とか「これが動く」とか、起きることを一回想像してみたら、脆弱(ぜいじゃく)性が分かると思います。
例えば、赤ちゃんがいるお母さんであれば、赤ちゃんのベッドの近くにタンスがあるなら壁に打ち付けたいでしょうし、上には絶対に物を置かないですよね。じゃあタンスを打ち付けるときはどう打ち付ければいいのか。こうしたことを含めて、建物の使用レシピです。瑕疵責任上の説明とは次元が違います。
ですから、建物の使用レシピとは利用者と対話できる手段であり、建築の付加価値になるはずです。建築業界の新ビジネスという観点からみても、こうしたソフトは必須でしょう。引き渡したら終了何かあったら電話くださいという程度では、成熟社会のビジネスとして惜しい気がします。
2020年10月号 BCPビジネスの他の記事
- 建築の防災的課題はハードでなくソフトにある
- コロナで成長する組織とビジネス
- 【令和元年東日本台風から1年】日本社会は災害とどう向き合うのか
おすすめ記事
-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/01/27
-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26
-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点
ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。
2026/01/26
-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン
家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。
2026/01/23
-

-

-























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方