2016/11/10
誌面情報 vol49
・なぜスモールステップが重要なのでしょうか。
私は「やる気」というものは有限だと考えています。実際、目に見えないものですし、多くの人はそんなイメージは持たないと思いますが、本当は「使ったらなくなる」んです。3日坊主というのは、やる気を使い果たした結果起きる現象です。東日本大震災の直後なら、まだ防災に取り組むやる気があったかもしれませんが、それも時間経過とともに少なくなり、今では意識が薄れてやる気もなくなっている。
やる気が持続しないのなら、燃え尽きないうちに習慣化させることが重要です。やる気のあるうちに小さなことからコツコツと積み重ね、習慣化させるのです。こんな些細なことなのかと思うくらいでもいい。やる気が「0」でも当たり前のこととしてできるように習慣化できれば、対策のレベルは上がったことになります。できたら次の行動をプラスする。その積み重ねでやる気を消費せず習慣化させ、継続した取り組みにしていくのです。
・組織というものを考えれば、命令というのも有効な方法でしょうか?
トップダウンの命令で実行させることも、「伝え方」としては有効です。災害時の連絡手段の確保が目的なら、上司の命令で、全員に対して一斉にTwitterのアカウントを取得させるようなこともできるはずです。組織のコミュニケーションのあり方としては、上意下達のような命令は極めて効果があるのです。ただし、これに頼りすぎると、社員が疲弊し、一時的に整備された防災の仕組みも、知らず知らずのうちに形骸化するなんてことにもなりかねません。上からの命令と、下からの意識を変える、両方をうまく組み合わせることがポイントになるでしょう。
・説明する担当者が陥りやすいポイントはありますか?
タイプ別にみると、①専門用語を多用して話す学者タイプ、②説明する順序がバラバラで伝わらないタイプ、③アキバのオタクみたいに自分の話は面白いと思って熱中して話し、相手を置いていくタイプ、④自信がないからぐちゃぐちゃと話して、結論から言えない「迷える子羊タイプ」がいます。
それぞれに課題が違うので一概にここを直せばいいとは言えないのですが、元をたどれば冒頭に話した3つが抑えられていない。そこから派生していると思います。
経済ジャーナリスト、一般社団法人教育コミュニケーション協会代表理事
慶應義塾大学経済学部を卒業後、富士フイルム、サイバーエージェント、リクルートを経て独立。学生時代から難しいことを簡単に説明することに定評があり、大学時代に自作した経済学の解説本が学内で爆発的にヒット。現在も経済学部の必読書としてロングセラーに。相手の目線に立った話し方・伝え方が、「実務経験者ならでは」と各方面から高評を博し、現在では、企業・団体向けに「説明力養成講座(わかりやすく伝える方法)」を実施している。フジテレビ「とくダネ!」、関西テレビ「ゆうがたLIVEワンダー」レギュラーコメンテーター、NHK「ニッポンのジレンマ」、Eテレ「テストの花道」などメディア出演多数。『今までで一番やさしい経済の教科書』、『カイジ、「命より重い」!お金の話』など著書多数、、累計120万部。
誌面情報 vol49の他の記事
- 市民によるトリアージで町を救え
- 仏商工会議所が首都直下地震のBCP
- 避難訓練だけを繰り返しても意味がない
- 『分かりやすい』伝え方 防災では定義が広すぎる
- なぜルールは破られる?気付きと動きで安全文化を構築
おすすめ記事
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/01/06
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/01/05
-
年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する
サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。
2026/01/04
-

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25
-

-

-

-

-









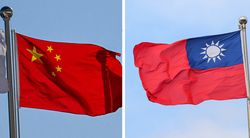















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方