新着一覧
-
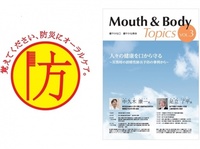
サンスター、災害時の口腔ケア情報
サンスターは1日の「防災用品点検の日」に合わせ、同社が運営するサイト「防災オーラルケア」にリーフレット「Mouth & Body Topics 人々の健康を口から守る~災害時の誤嚥性肺炎予防の事例から~」を掲載した。PDFでダウンロードできる。
2017/03/01
-

消防庁、防災アプリの外国人対応促進
消防庁は民間の出すスマートフォンなど避難支援アプリの外国語案内導入を促進する。3日開催予定の「避難支援アプリの機能に関する検討会」で取りまとめるガイドラインで取りあげる。訪日外国人が増加する中で、わかりやすさを訴求する。
2017/03/01
-

気象庁、緊急地震速報の予測に新手法
気象庁は1日、「緊急地震速報評価・改善検討会」の第7回技術部会を開催。緊急地震速報の予測に関し新手法を取り入れる方針を示した。従来手法と組み合わせたハイブリッド型による予測を、2017年度をめどに導入する。
2017/03/01
-

NEC、サイバー特化の経営コンサル
NECは21日、「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」に対応したコンサルティングサービスを企業向けに提供すると発表した。IT脅威に対する対策立案など「リスクアセスメントサービス」など計8のサービスを用意。価格はリスクアセスメントサービスで200万円から(税別)。販売目標は今後3年間で350社への提供。
2017/02/28
-

災害の危険度がわかるアプリ
株式会社ユースエンジニアリング(本社:愛知県春日井市)は24日、自然災害の危険度が確認できるスマートフォンアプリ「ここ大丈夫?」を開発し、21日より提供を開始したと発表した。確認したい場所を地図上でタップする事で、6種類の自然災害の各危険度を「安全・警告・危険」の3段階で表示する。iOS版、Android版とも価格は無料。
2017/02/28
-

山岳捜索活用へドローン講習会
公益社団法人・東京都山岳連盟(都岳連)は24日、山岳地帯における行方不明者捜索でのドローン活用のため「山岳捜索ドローン技術講習会」を開催すると発表した。5月20~21日に東京都あきる野市の秋川渓谷体験研修センターにて開催する。価格は2万5000円(税別)。
2017/02/28
-

「おふろですよ」にシトラス&石けんの香り
サラヤは、災害時など水が使えず入浴や洗髪ができない場合でも体や頭を拭いて清潔に保てる、全身清拭ぬれタオル「おふろですよ」の「シトラス&石けんの香り」の販売に注力する。高砂香料工業のTRANSODORという消臭技術を使用し、不快な汗の臭いを香りの一部として取り込み、快適な香りに変える。品質保持期限は製造日より5年。価格は1袋30枚入りで1000円(税抜き)。
2017/02/28
-

危機管理ソリューションセミナー(安否確認・情報共有システム編)
安否確認・情報共有システム比較大検証! 自然災害から海外拠点まで本当に必要なシステムとは?~3月22日水曜日、全国町村会館で開催~東⽇本⼤震災以降、多くの企業や⾃治体は安否確認の体制を⾒直してきました。
2017/02/27
-
内閣府が地区防災計画フォーラム開催
内閣府は3月25日、名古屋国際センター(ホール)で地区防災計画フォーラムを開催する。
2017/02/27
-

韓国向け地震速報アプリを開発
アールシーソリューションは21日、韓国の企業BRentWOOD(ブレントウッド)と提携し、韓国向けの地震速報アプリ『Kururung』(クルルン)を開発、20日にAndroid版、24日にiOS版、3月末には機能を追加したバージョンをBRentWOODより配信開始すると発表した。日本の気象庁が発表する緊急地震速報、同社が開発したアプリ「ゆれくるコール」の情報配信、それぞれの技術を活用したもの。「韓国初の地震速報アプリ」(同社)となる。
2017/02/27
-

無電柱化、軒下配線などヒアリング
国土交通省は27日、第2回「無電柱化推進のあり方検討会」を開催。関係団体からヒアリングを行った。災害時に倒壊など被害防止に効果のある無電柱化について、石川県金沢市や電気事業連合会(電事連)などからコスト削減などの事例が紹介された。
2017/02/27
-

-

防災アプリに寺院情報を掲載
ファーストメディア株式会社は24日、同社運営のスマートフォンアプリ「全国避難所ガイド」に寺院情報を掲載すると発表した。同日、宗教法人・日蓮宗と協定を締結。「災害時協力寺院」として、生活用水や避難場所の提供など、災害時に協力できる寺院情報を随時掲載していく。
2017/02/27
-

東京都、中小企業の防災技術開発に補助
東京都と東京都中小企業振興公社は23日、2017年度「先進的防災技術実用化支援事業」の概要を発表した。都内中小企業による防災関連や技術の開発・改良や普及に補助を行う。また4月に4回、同事業に関する説明会を開催する。
2017/02/27
-

-

-

-

KDDI、ドローンを携帯電話基地局に
KDDIは24日、災害時の一時的な携帯電話エリア復旧のため、ドローンに基地局機能を搭載させた「無人航空機型基地局」(ドローン基地局)を開発したと発表した。また同日、東京・江東区の東京臨海広域防災公園で同基地局を用いた訓練も行った。
2017/02/24
-

災害は平等に来ても、被害は不平等
「高齢者や障がい者は被災時にケアや食事、スペースについてほかの避難者より恵まれていると思われる方もいるかもしれない。しかし元の身体的・精神的体力は同じではない。災害は平等に来ても、被害は不平等。その解消をするべきなので、(高齢者や障がい者に対して)合理的配慮を遠慮してはいけない」と話すのは、熊本学園大学社会福祉学部の吉村千恵氏。
2017/02/24
-

日系企業も無関係ではないトランプ大統領令。影響を軽減するためのポイントは?
デロイト トーマツ 企業リスク研究所は24日、2017年2月分の海外リスクを紹介した。同研究所主席研究員の茂木寿氏は、「7カ国の入国制限に続いて、来週新しい大統領令が発表される。日本人も一時的に出入国が厳しくなり、日系企業も現地では混乱する可能性もある」とする。
2017/02/24
-

防災グッズの作り方やアイデア募集
NHKは身近なもので作れる防災グッズや、被災地で役立つアイデア「つくってまもろう」を募集している。オンライン投稿で、締め切りは3月3日。材料、作り方のほかアイデアについて動画やイラストを使い、いつ、どう使用するかなどの簡単な説明を添える。寄せられたアイデアは、専門家によるアドバイスのもと、動画にまとめてNHKのサイトなどで紹介する。
2017/02/24
-

地理院地図に指定緊急避難場所
国土交通省国土地理院と内閣府、消防庁は22日、国土地理院のウェブ地図「地理院地図」での指定緊急避難場所データの公開を開始したと発表した。災害種別ごとに検索できる。
2017/02/24
-

-

-

BCP策定を断念する企業も
NTTデータ経営研究所は20日、NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューションが提供する「NTTコム リサーチ」登録モニターを対象に実施した「東日本大震災発生後の企業の事業継続に係る意識調査(第4回)」の結果を発表した。現在BCPを策定済みの企業は約4割、策定中を含めると6割を超えるが、「BCP検討途中で策定を断念してしまっている企業も多い」(同社)などの結果が出た。
2017/02/23






















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



