2025/11/13
防災・危機管理ニュース
近年、世界各地で林野火災が相次いでいる。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が2022年に公表した報告書で、火災と気候変動の関係に言及。専門家は、出火後の大規模化にも注意を促している。
米NPO「世界資源研究所(WRI)」によると、23年と24年に林野火災によって排出された温室効果ガスは二酸化炭素に換算すると、それぞれ40億トンを超えた。これは世界3位の排出国であるインドの年間排出量と同じ水準で、さらに温暖化を加速する要因にもなる。国連環境計画(UNEP)は、温暖化のほか、農業開発をはじめとした土地利用の変化により、大規模な林野火災のリスクは50年末までに現状(10~20年)と比べて30%、今世紀末までに50%増えると予測する。
京都大学防災研究所の峠嘉哉特定准教授(水文学)によると、林野火災の発生リスクは、乾燥、風速、気温などの気象条件や樹木の燃えやすさが複合的に絡み合って決まる。今年、岩手県大船渡市で発生した大規模火災は、降水量が極端に少なかったことが一因となった。気候変動と個別の火災を関連付けるにはさらなる研究が必要だが、地表が雨によって湿って出火を抑制している状態が気温上昇で変化し、乾燥が進めば、火災が発生・大規模化しやすくなる可能性があるという。
そこで、峠氏は「出火させないことが第一義」と強調する。実際に、峠氏らの研究チームは、市町村ごとに林野火災の発生リスクを予測し、可視化するシステムを開発中。将来的には予報や警報への活用を目指す。
〔写真説明〕スペイン北西部、ポルトガルとの国境近くの村で起きた山火事の消火活動に当たる消防士=8月12日(AFP時事)
(ニュース提供元:時事通信社)

防災・危機管理ニュースの他の記事
おすすめ記事
-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-











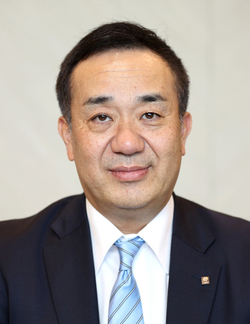















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方