2025/11/27
防災・危機管理ニュース
【カイロ時事】イスラエルとレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの停戦が発効してから27日で1年。ヒズボラは軍事力の回復を図っているとされ、イスラエルは「合意違反」を主張してレバノンへの散発的な攻撃を続けている。レバノン政府が進めるヒズボラの武装解除は見通しが立たず、停戦は有名無実化している。
◇壁建設、民間人も被害
「イスラエルへの脅威は許さない」。ネタニヤフ首相は23日、レバノンの首都ベイルート南郊に空爆を加えた後、こう強調した。標的となったのはヒズボラの軍事部門トップ、タバタバイ氏。イスラエル軍は、「戦争準備」を含む組織再建を同氏が主導していたと説明した。同国メディアは「停戦後、最も厳しい措置だった」と伝えた。
停戦合意ではレバノン南部からヒズボラとイスラエル軍双方が撤収し、レバノン軍が展開することになっている。しかし、イスラエル側は、合意に含まれるヒズボラの武装解除が進んでいないと指摘し、連日のようにヒズボラに関連する標的を攻撃。イスラエル軍はレバノン南部の5カ所の拠点に依然駐留し、レバノンとの間の暫定的な境界線を越えてコンクリートの壁を建設しているとされる。
停戦監視を担う国連レバノン暫定軍(UNIFIL)は、過去1年間で、合意違反は約1万件に上ると報告。国連によればイスラエル軍の攻撃で民間人少なくとも127人が死亡した。
◇報復控え立て直し
ヒズボラ側はタバタバイ氏殺害を受け「敵に屈服しない」と反発したが、イスラエルへの報復攻撃には出ていない。同国軍による昨年の攻撃で、カリスマ的存在だった前最高指導者ナスララ師ら主要幹部を失い弱体化したことが背景にある。反撃よりも組織の立て直しを優先しているもようだ。
米中央軍によると、レバノン軍は停戦合意に基づき、南部でこれまでにヒズボラのロケット弾約1万発、ミサイル400発などの武器を廃棄した。しかし、ヒズボラはドローンの国内生産に重点をシフトし、戦闘員を拡充しているとの報道もある。
こうした状況を受け、停戦の焦点だったヒズボラの武装解除について、レバノンの政治科学研究所のサミ・ナデル所長は「実現の見通しは全くない」と指摘。ヒズボラを含むシーア派勢力が反対する中、「内戦に発展することを恐れるアウン政権が、ヒズボラに対抗する決断を下していない」と分析する。
停戦後もイスラエル軍の攻撃にさらされるレバノン南部への帰還を断念する避難民は多い。時事通信の電話取材に答えた女性(40)は「ヒズボラが武器を引き渡してもイスラエルは攻撃を続ける」と強調。「武器は唯一の抑止力だ」と語った。ヒズボラが拠点としてきた南部では依然、ヒズボラを支持する声が根強い。
〔写真説明〕23日、レバノンの首都ベイルート南郊でイスラエル軍による空爆を受けた住宅街(AFP時事)
(ニュース提供元:時事通信社)

防災・危機管理ニュースの他の記事
おすすめ記事





















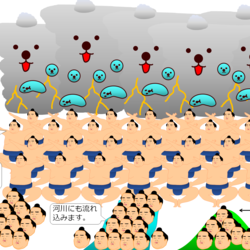













![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方