第1回:大規模災害対応のための「キャピタル概念」
6つの資本とシステム思考で災害が見えやすくなる
国際大学GLOCOM/
主任研究員・准教授、レジリエントシティ研究ラボ代表
櫻井 美穂子
櫻井 美穂子
ノルウェーにあるUniversity of AgderのDepartment of Information Systems准教授を経て2018年より現職。博士(政策・メディア)。ノルウェーにてヨーロッパ7か国が参加するEU Horizon2020「Smart Mature Resilience」に参画。専門分野は経営情報システム学。特に基礎自治体および地域コミュニティにおけるICT利活用について、レジリエンスをキーワードとして、情報システム学の観点から研究を行っている。Hawaii International Conference on System Sciences (2016)およびITU Kaleidoscope academic conference (2013)にて最優秀論文賞受賞。
櫻井 美穂子 の記事をもっとみる >
X閉じる
この機能はリスク対策.PRO限定です。
- クリップ記事やフォロー連載は、マイページでチェック!
- あなただけのマイページが作れます。
私たちの住む都市は、複雑で、ダイナミックなリビング・システム(生きたシステム)です」――と言っても何のことか分かりにくいですよね。ごめんなさい。
これは、世界的に有名な建築家のクリストファー・アレクサンダーが言った言葉です。彼は論文『A City is not a Tree』(都市はツリーではない)の中で、「都市は、リビング・システムを構成するさまざまな要素により成り立っている」と書いています。具体的には、そこに住む人々、生活インフラ、道路、商店などがそれぞれ独立して存在しているように見えていながら、実は相互に深く関係しあっていることをリビング・システムと言っているのです。こちらが動けば、あちらも動く、こちらが止まれば、あちらが止まる、それが1対1ではなく、とても複雑な関係で成り立っていると考えていただければ少しは分かりやすくなるでしょうか。
自然界で生物がお互いに依存しながら生態系を維持していく(例としては、樹木が光合成により酸素を作り出し、人間が酸素を吸いながら生きていく、など)「エコシステム」の考えに近いかもしれません。例えば、交差点の信号機が赤になると、交差点の角にあるキオスクに人々が立ち寄り物を買う可能性が高くなりますが、信号機が青であればそのまま通り過ぎてしまうようなことがありますよね? 複雑でダイナミックな都市の姿を理解するためには、私達の住む街が、このような動的な“システム”であるということをまずは認識することが重要だというのです。
災害対応やBCP策定の現場においても、このようなシステム的な観点は役に立ちます。災害対応は、非常に複雑で、高度な意思決定が必要になります。現場の担当者は、刻々と変わっていく、ダイナミックな状況に常に適応していかなければいけません。これは、リビング・システムが激しく変化しているような状況と例えることもできます。この連載では、災害対応にシステム的な考え方を導入するための枠組みとして、「資本(以下、キャピタル)の概念」というものを提案していきたいと思います。


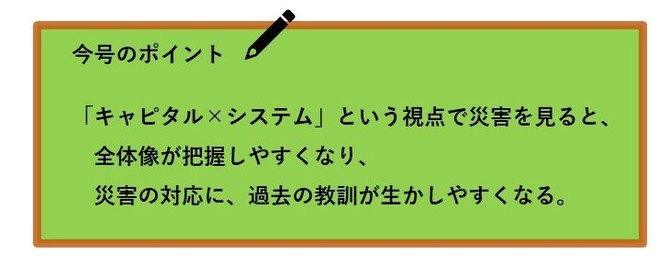


































![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方