2019/06/07
レジリエントな社会って何?
被害の程度や状況は多様
各事例を分析してみてまず分かることは、同じ地震や津波に見舞われたとしても、被害の程度や状況は多様である、ということです。3つの町の事例で、一つとして同じ状況はありませんでした。特に東日本大震災は事前に想定し得る被害規模をはるかに超えたものでしたので、災害対応に当たる現場で何が起こるのか、被害はどの程度なのか、事前に予測することは不可能でした。事例に登場した自治体の担当者たちは、個人的な経験に基づいて対応に当たったのです。どういうことかというと、いずれの地域でも、災害時の対応手順を具体的に定めた文書は存在せず、情報システムの復旧に関するノウハウも職員や管理業務を委託していたベンダーに分散していました。その場の状況を担当者個人の感覚や経験によって理解をし、その時に最善と思える対応(例えば、住民データをCSVに吐き出して避難するなど)を取っていたのです。このような対応を「創造的対応」と呼んでいます。
これからの災害対応を考えるに当たっては、現場での「創造的対応」をいかに誘発していくかが重要となります。なぜならば、今後起き得る災害について、仮に被害程度を予測できたとしても、実際にどのような環境下で災害対応業務に当たるのか、事前に見定めることは極めて難しいためです。

この「創造的対応」を可能にするための環境整備としてまず大切なのが、第5回で登場したドメインナレッジです。当該分野における知識、平たく言うと日常で培われる業務やシステムへの「慣れ」でした。災害対応をサポートする情報システムは、さまざま開発されています。このようなツールは、日頃使い慣れていなければいざというとき役に立たないというのは、前回申し上げた通りですし、一般的な同意が得られているように思います。事例の中で、双葉町と浪江町では、エクセルを使用して避難者のリストを作成していました。さまざまな事業者から提供されるツールの中でエクセルを選択したのは、実際にリスト作成に当たる職員が、日頃使い慣れているからでした。自治体の災害対応の事例においては、ドメインナレッジを有効に使えるような環境が重要となりました。
一方で、ドメインナレッジに沿ってツール(この事例においては避難者名簿)を作るだけでは、別々の場所(例えば異なる避難所)で作成されたツール間におけるデータの一貫性が問題となります。そこで、標準的なデータの取り扱いに関するルールがあれば、事後のデータ管理がスムーズにいくと考えられます。例えば前回、浪江町で避難者名簿を作成する際、住所氏名に加えて、氏名のよみがな(ひらがな)と生年月日のデータがあれば、のちのち住民基本台帳データとの突き合わせがしやすい、という担当者の振り返りをご紹介しました。このルールは、組織を超えた救援活動の際にも、組織間の情報交換をサポートします。
データの共通取り扱いルールを
避難者の確認といった業務は、企業での災害対応では実際には起こらない業務かもしれません。しかしながら、安否確認や、突発的な事象に関するレポートの作成の際に重要となるデータ(社員番号、事故の状況、事故のカテゴリー、場所、ビルの構造など)については、先に挙げた避難者名簿の事例と同じく、社内で共通の取り扱いルールを定める必要があると思います。また、有事の際の連絡手段や、災害時にのみ発生する業務を遂行するためのツールについても、日頃社員の方が使い慣れている方法(電話なのかスマホアプリなのか)を第一の手段として定めることで、現場におけるドメインナレッジの活用が進むことが想定されます。
ここまで来てお気付きの方もいらっしゃるかもしれませんが、ドメインナレッジを発揮するためには経済資本、組織資本、人間資本、そして場合によっては社会関係資本と、さまざまなキャピタルが必要となります。キャピタルは一度失われると元の状態に戻ることは難しくなりますが、その中でも経済資本の代替は他のキャピタルの喪失に比べると容易に行われる特性がありました。しかしながら代替された経済資本を使って災害対応を行おうとすると、さまざまな調整が必要なことも分かりました。事例では、町からの移転を余儀なくされた自治体の仮庁舎が見つかったとしても、自治体の業務を行うために建てられた建物ではない場合、情報システムをゼロから立ち上げる必要がありました。
次回以降は、これまでの連載の中で見えてきた各キャピタルの特性を踏まえて、引き続き過去の教訓を今後の対応に生かしていくための方策について考えていきたいと思います。
* A. Dean and M. Kretschmer, “Can Ideas be Capital? Factors of Production in the Postindustrial Economy: A Review and Critique,” Academy of Management Review, vol. 32, no. 2, 2007, pp. 573-594. および M. Mandviwalla and R. Watson, “Generating Capital from Social Media,” MIS Quarterly Executive, vol. 13, no. 2, 2014, pp.97-113. を改変。
(了)
レジリエントな社会って何?の他の記事
- 最終回:事例からの示唆と創造的対応への道まとめ
- 第8回:創造的対応への道 その2
- 第7回:創造的対応への道 その1
- 第6回:「創造的対応」が災害対応のカギを握る
- 第5回:BCPに不可欠な「ドメインナレッジ」
おすすめ記事
-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/17
-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05








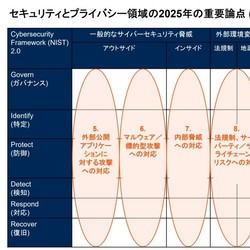

















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方