2019/07/29
安心、それが最大の敵だ

漱石と物理学の激動期
「漱石が見た物理学」(小山慶太早稲田大学教授)も注目すべき新書であり、知的刺激に満ちていて大いに参考になった。著者小山教授は理学博士であり文学者ではない。筆者(高崎)は物理学やその近現代史について語るだけの素養がない。そこで同書からの引用をお許し願いたい。
「<物理学の激動期>
漱石が生きた半世紀を、物理学の歴史で捉えてみると、それはまさしく激動の時代であったことがわかる。16世紀から17世紀にかけて起きた、近代科学の誕生に匹敵する『科学革命』の時代であったと表現しても決して過言ではないのである。そのありさまは、漱石と時代をともにする物理学者たちの名前を見てもらえばよくわかる。たとえば、漱石が慶応3年(1867)牛込馬場下横町(現在の東京都新宿区喜久井町)に生まれた年、ポーランドのワルシャワではキュリー夫人(マリア・スクロドフスカ)が産声を挙げている。また、漱石が松山中学に赴任した明治28年(1895)は、ドイツのヴュルツブルグ大学の実験室で、レントゲンがエックス線を発見した年でもある」。
「漱石がイギリスに留学した明治33年(1900)に目を向けると、ロンドンの王立研究所でケルヴィンが歴史に残る物理学の講義を行っているし、同じ年の暮れには、ドイツのプランクが量子仮説を提唱し、量子力学誕生のきっかけがつくられている。『吾輩は猫である』の発表年(1905)は、アインシュタインが特殊相対性理論の論文を発表した年と一致する。そしてアインシュタインが一般相対性理論を完成させるのは、漱石が息を引き取る1916年のことである」。
アインシュタインが一般相対性理論を完成させるのは、漱石が息を引き取る1916年のことである、とは偶然以上のものを感じさせる。
「漱石が文部省から贈られることになった文学博士の学位をかたくなに辞退して世間を騒がせ、『現代日本の開化』をはじめとする数々の講演で忙しかった明治44年(1911)には、イギリスのラザフォードが有名な原子の有核模型を提唱している。この業績は、それまで人間が垣間見ることの出来なかったミクロな世界の構造に光をあてる手がかりとなったのである。
このように、漱石の後半生は、微視的な対象を扱う量子力学が台頭し、時間・空間の新しい描像を与える相対性理論が確立されるという、物理学の大きな変革期と完全に重なっていることが分かる。従って、当然のことながら、今あげたアインシュタイン、ラザフォードといった物理学の天才たちの全盛期と漱石が執筆活動に励んだ時期も、これまた重なってくる」。
物理学の天才たちの全盛期と漱石が執筆活動に励んだ時期も、これまた重なってくる、ことも偶然以上の重大事と考える。
「話を19世紀後半に戻すと、漱石が生まれてから10年後の明治10年(1877)にはオーストリアの理論物理学者ボルツマンが熱力学第二法則(エントロピー増大の法則)に確率論にもとづく解釈を与え、統計力学を確立させている。また、それより4年前の1873年は、イギリスのマックスワェルが電気と磁気の現象を統一して扱う理論を完成し、電磁気学の体系化を行った年になる。さらにマックスワェルの理論の正しさを実験で証明することになったドイツのヘルツによる電磁波の検出は、漱石が大学予備門(このときは第一高等中学と改称されていた)を卒業する明治21年(1888)のことである」。
小山教授は<漱石の生涯は科学史上極めてエキサイテイングな時期>と結論づける。
「漱石の前半生は、ニュートン力学とマックスワェルの電磁気学を2つの柱とし、熱力学、統計力学などに補完される古典物理学、19世紀に完結し、人間の五感で捉えられる巨視的現象を体系的に記述できる物理学の総称が完成された時代に一致している。漱石の生涯は古典物理学(巨視的な世界)から、全く異質な20世紀物理学(微視的な世界)へと移り変わる、科学史上極めてエキサイテイングな時期に当っているのである。このエキサイティングな物理学の相貌を科学への関心を生涯持ち続けた漱石という近代日本が生んだ『知の巨人』の眼を通して眺める」。
鋭い指摘であり、門外漢の私には感服のほかはない。物理学に関心はあっても深い知識のない私にも深くうなずける分析である。漱石はやはり「天才」であった。
参考文献:「漱石 片付かない<近代>」(佐藤泉)、「漱石とあたたかな科学」(小山慶太)、「夏目漱石事典」(編者:平岡敏夫、山形和美、影山恒男)。
(つづく)
- keyword
- 安心、それが最大の敵だ
- 夏目漱石
安心、それが最大の敵だの他の記事
おすすめ記事
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/01/06
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/01/05
-
年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する
サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。
2026/01/04
-

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25
-

-

-

-

-









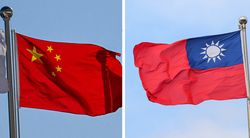















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方