2017/02/27
昆正和の『これなら作れる! 緊急行動の成否を分けるERP策定講座』
■「伝達」と「対処」でつまずかないために
風評リスクには、「予防的に対処するのがむずかしい」という特徴があります。この種の危機対応では、自社のうわさがネットに出回っていないか、日頃からモニタリングを欠かさないことが大切と主張する専門家もいます。しかしこの方法では雲をつかむような、あるいはいつ起こるか分からない地震を待ち構えるような虚しさがあることも確かでしょう。
風評被害の発生を予測的に捉えることはできませんから、ERPにおいてはいわゆるクライシスコミュニケーション(危機発生時のコミュニケーション戦術)の手順を取り入れることが賢明です。危機の察知の次のステップ、つまり「伝達」と「対処」はほぼ同じタイミング、同じ意味合いで捉えて差し支えありません。手順は次のとおりです(冒頭の商品クレームを例にとります)。
(1) まずネットなどに自社のうわさが出ているのを確認した時点でそのメッセージの意図をくみ取る。悪意があるのか、消費者としての率直な気持ちの表れか、問題の核心は何かを、会社としての防衛目線ではなく1ユーザーの立場で冷静に分析します(ただしあまり時間をかけてはいけない)。
(2)次に、問題の核心が自社の商品、サービス、顧客対応にあると思われる場合は、ただちに現場と連携してその問題の検証を進める。もちろんすぐには結果は出てこないでしょう。
(3)そこで、(2)と同時並行的に暫定的な「状況報告」のメッセージをツイッターやホームページから発信します。自社に本当に否があるかどうかはこの時点では分からないのですから、「お客さまにはご心配、ご迷惑をおかけしています。問題については鋭意調査中です」ぐらいでしょうか。若干のお詫びのニュアンスを交えたメッセージです。調査中の時点で「当社には否はない」とする断定的なメッセージを発信するのは避けなければなりません。
(1)~(3)で最もタイムリーかつ確実に実施したいのが(3)です。少し乱暴な言い方ですが、状況報告のメッセージはいわば「時間稼ぎ」に当たります。この間を通じて速やかに原因を究明し、必要に応じて法務部門等と連携して事態の収拾に向かうことになります。
■初動成功の鍵は経営者が戦略的な"水平目線"を持つこと
前セクションでは、風評リスクの発生を「予測的」に捉えることはできないと書きましたが、「予防的」な対処方法を模索することは可能でしょう。オーソドックスな対策としては、例えば次のような方法が考えられます。
・製造業などでは生産・出荷品の品質や衛生管理の徹底
・ホテル・旅館・観光関連業では風評リスク対応マニュアルの整備と地域連携方法の確立
・サービス業では社員教育の徹底(顧客対応マナー・モラルに関する倫理規定を作成して活用)
なお、風評リスクに対する企業の対応姿勢は、つきつめれば経営層や中間管理層の姿勢の表れでもあります。決して顧客との接点にある一担当者レベルの問題で片づけてはいけません。冒頭のストーリーのように、社長がネット上の風評を一蹴すればその態度が火に油を注ぐことになります。会社組織では、右肩上がりに業績が好調だったり、昇進や昇格を繰り返して偉くなったりすると慢心してしまい、現場やお客さまの顔が見えなくなることがあります。とくにSNSを介した風評リスクをこじらせる最大の理由は、ここにあると言っても過言ではありません。
対外的に会社の姿勢の是非を決める上層部の立ち位置としては、「相手を正しく見極めるための水平目線(相手と同じ目線)」を持つことが大切でしょう。むやみに上からの目線になれば、相手や現状を否定したり軽視したりすることになる。逆に下からの目線になれば、相手に見下されたり足元をすくわれてしまうかもしれない。とくに消費者には配慮が必要です。もちろん、むやみに消費者を警戒して神経質になる必要はありませんが、水平目線を忘れると、クレームなどが起こったとき「否認」に走りやすくなります。否認によって初動が遅れると、ソーシャルメディアなどを通じてあっという間に風評被害が広がってしまい、ブランドを失墜する事態となるのです。
(了)
昆正和の『これなら作れる! 緊急行動の成否を分けるERP策定講座』の他の記事
- 第12回(最終回):手のかからない維持管理
- 第11回:右も左も熱い人でいっぱいじゃござんせんか!
- 第10回:SNSのえじきになったらたまらん!
- 第9回:そのことは水に流して、といえない台風災害
- 第8回:揺れてこまるのはビルも心もいっしょです
おすすめ記事
-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-










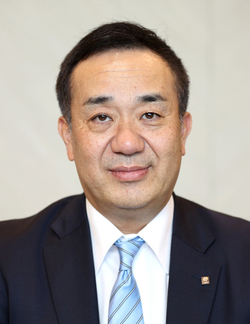
















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方