2017/04/14
熊本地震から1年

私は熊本地震が発生する直前にこちらに赴任いたしました。もともと内閣府で防災を担当していたので熊本地震後に現地のインタビューなどを行ったのですが、避難所の問題、備蓄の問題、耐震化の問題など、阪神・淡路大震災や東日本大震災と同じ問題が繰り返されていると感じました。そしてインタビューの中で「東日本大震災などを見て防災は大事だと思っていたが、まさか熊本に来るとは思わなかった」と多くの人が話していたのが印象的でした。
熊本地震の特徴
熊本地震は、直接死より間接死が多いのが一番の特徴です。特に、車中泊を重ねてエコノミー症候群で亡くなった方や医療機関が被災し、転院がきっかけとなって死亡した方も多いといわれています。発災直後の昨年の5月に開催した学会でもそのような指摘がありましたが、とても残念な結果になってしまいました。
■「震災関連死38人が車中泊 18人は転院後 熊本地震1年」(2017年4月6日付 西日本新聞)
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/319691
また避難所の調査を行っていると、もちろん子どもたちの自発的な素晴らしい活動も多く聞きましたが、最も多かったのは「発災した後、もっとうまくやれたのではないか」という住民たちの話でした。避難所の運営や備蓄、支援物資の配布など、もっと事前に計画を作って訓練をしていれば、もっとスムーズにいったのではないかということです。これは今後の大きな課題として残っています。

自助・共助の重要性
地区防災計画となんでしょうか。話は1995年までさかのぼります。6400人以上の死者・行方不明者を出した阪神・淡路大震災では、地震によって倒壊した建物から救出された人の約8割が、家族や近所の住民によって救出されました。消防・警察・自衛隊によって救出された人は2割しかいなかったのです。これは災害時の「公助の限界」と呼ばれています。
東日本大震災では、津波で流されて亡くなった人が多かったため「誰に救出してもらったか」という統計はありませんが、岩手県大槌町のように町長をはじめとして多くの幹部職員が津波で死亡するなど行政も大きな被害を受けたため、こちらにも「公助の限界」がありました。一方で、阪神・淡路大震災と同じく「自助・共助」の活動に注目が集まりました。日ごろから防災教育を受けていた子どもたちが率先して高台に逃げ、かつ途中で高齢者にも声をかけて一緒に避難することで皆が命をとりとめたという、いわゆる「釜石の奇跡」も自助の取り組みでありながら、結果として共助にもなった素晴らしい事例です。これらのように災害時には「自助・共助」の取り組みが非常に重要なのです。
地区防災計画の概要
そのような背景のなか、2014年4月に施行されたのが「地区防災計画」です。それまでは、簡単に言うと国の中央防災会議による防災基本計画があり、それを受けて都道府県や市町村が地域防災計画を策定するという、いわばトップダウンの流れでした。地区防災計画はそうではなく、住民や事業者などが自らボトムアップで防災計画を策定するものです。策定された計画は、「計画提案」という形で市町村に提案することができ、それがふさわしいものであれば、市町村の地域防災計画の中に組み入れることができます。
どのようなメリットがあるのかというと、それまで市町村は各地区がどのような防災活動をしているのか、状況を把握できていませんでした。当然ながら地区防災計画を地域防災計画に組み入れるということは、市町村が各地域のミニマムな計画を把握でき、住民たちときめのこまかい連携が可能になるのです。
地区防災計画の特徴は大きく三つあります。一つはいま述べたようにボトムアップで地域が自分たちの計画を策定し、自治体に計画提案できること。もう一つは地区の特性に応じた計画が策定できること。同じ町の中でも海と山や、雪の降るところと降らないところでは当然計画が変わってきます。そのようにきめ細かく地区の特性を反映することができます。最後は、訓練やコミュニティの活動を通じて継続的に実施されること。一度計画を策定してしまうと、それで終わってしまう計画も多いのですが、地区防災計画は、実際に災害が来た時に使える計画、実際に住民が「動ける」計画を目指しています。
ソーシャルキャピタルと地域防災力の活性化
内閣府が発行した「平成26年度版防災白書」では、「防災を起点にした地域コミュニティの活性化」を目指しています。簡単に言えば、防災がうまくいっていれば地域のコミュニティも活性化するということです。防災を起点にしてコミュニティが活性化すれば、自然と治安が良くなり、ビジネスにも貢献し、地区の実情に応じたきめ細かい町づくりにも寄与できる可能性がある。防災により地域コミュニティを活性化し、ソーシャルキャピタルを豊かにしていくことが、今後の地区防災計画の方向性であると考えています。
(了)
熊本地震から1年の他の記事
- 「想定内」の中の「想定外」が問題~熊本地震から感じたこと三題~
- 熊本地震、LINEでの情報収集が4割
- 防災を起点に地域コミュニティを活性化~地区防災計画の概要<熊本地震から1年>
- 関連死166人孤立死14人という数字は非常に重い。熊本地震が投げかけた課題と地区防災計画のあり方
- LINE、熊本市と防災で協定
おすすめ記事
-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/12/09
-

-

-

-
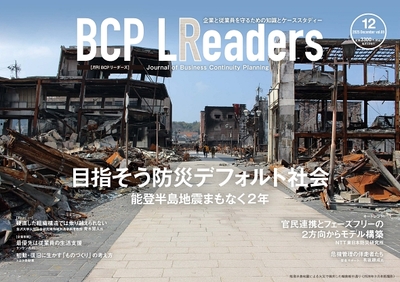
リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2025/12/05
-

競争と協業が同居するサプライチェーンリスクの適切な分配が全体の成長につながる
予期せぬ事態に備えた、サプライチェーン全体のリスクマネジメントが不可欠となっている。深刻な被害を与えるのは、地震や水害のような自然災害に限ったことではない。パンデミックやサイバー攻撃、そして国際政治の緊張もまた、物流の停滞や原材料不足を引き起こし、サプライチェーンに大きく影響する。名古屋市立大学教授の下野由貴氏によれば、協業によるサプライチェーン全体でのリスク分散が、各企業の成長につながるという。サプライチェーンにおけるリスクマネジメントはどうあるべきかを下野氏に聞いた。
2025/12/04
-

























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方