2013/07/25
誌面情報 vol38
1つのシステムだけに依存しない
東日本大震災以降、自社の安否確認システムを見直したり、衛星携帯電話を購入するなど、災害時における安否確認の確実性を高めようとする動きが目立つ。一方、東京都も今年4月に施行された帰宅困難者対策条例で、事業者に対し安否情報の確認手段の従業員への周知を努力義務として課すなど、安否確認の対策に乗り出している。安否確認の導入、見直しにおけるポイントをまとめた。
BCPにおける安否確認の目的

安否確認と一言で言っても、経営陣や従業員の安否確認、従業員の家族の安否確認、あるいは、支店や取引先の安否確認など、その範囲は多岐にわたる。BCP(事業継続計画)における安否確認の目的は、事業を継続させる上で、まず災害によってもたらされた自社の状況を明確にすることが挙げられる。
社員は全員無事なのか、社員の家族は無事で安心して勤務にあたれるのか、支店は無事か、取引先は…。これらの安否が確認できなければ、被災状況を正しく把握することができず、救援のために経営資源を投じるべきか否かの判断が困難となり、結果として意思決定が遅れて復旧までの時間も余計にかかることになる。
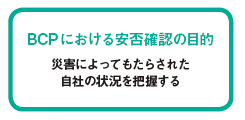
一方、こうした目的を理解し、安否確認の体制を整えていたとしても、それがスムーズに行えるかどうかは別問題だ。
矢野経済研究所が、東日本大震災直後の2011年5月に行った売上高1億円以上のユーザ企業に対するアンケート結果によれば、震災前に既に安否確認システムを導入していた企業のうち、24.6%が「大震災時にシステムが正しく機能しなかった」と回答した。その理由としてもっとも多く挙げられたのは、「携帯電話回線の不通によりシステムが利用できなかった」である。安否確認システムの多くは、携帯電話や携帯メールで安否を回答する仕組みになっているが、震災後、一時は携帯電話がほぼ全面不通となり、多くの携帯メールが不着となるなど、システムが正常に機能しなかった。
一方、従業員の対応も、家族の安否が確認できないため帰宅を急いだり、会社からの安否確認の連絡がないため、何日経っても会社に報告せず、会社が週明け後、何日間も社員の安否が確認できなかった事例も多数あった。
当然、固定電話も回線が混雑し、さらに広域な停電により被災地ではインターネットも使えない状況になり、本社がいつまでも支店や取引先などの状況がつかめない状態が続き、多くの会社や自治体が災害対応の出足をくじかれた。
誌面情報 vol38の他の記事
- 特集1 安否確認の手法大検証
- 知っておきたい安否確認のポイント
- 40万人に対応する安否確認 イオン
- 社員が自主的に連絡する NEC
- 震災後需要が伸びる衛星携帯電話
おすすめ記事




































![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方