2022/04/06
Joint Seminar減災・レジリエンス研究教育推進コンソーシアム 第2回共同シンポジウム
国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)とレジリエンス研究教育推進コンソーシアム(会長:林春男氏)の第2回共同シンポジウムが2022年2月14日に開催され、株式会社ウェザーニューズ航空気象チーム マーケティングリーダーの小山健宏氏と国立民族学博物館超域フィールド科学研究部教授の林勲男氏が講演した。シンポジウムのテーマは「地域性を考えた減災・レジリエンスのあり方」。小山氏は「航空気象(ドローンやヘリ等)から見た災害の地域性」、林氏は「災害文化の特徴とレジリエンスを中心に」をテーマにそれぞれ発表した。2回に分けて講演内容を紹介する。

災害脆弱地域
レジリエンスという言葉は、最初に物理学や生態学の分野で、システムの粘り強さや、変化・撹乱を吸収する能力を示す用語として使われ始めました。防災の分野では、外力に対して対応し得る能力、災害外力による人的・経済的・社会的被害を最小化し得る能力といった災害対応力を示す用語として使われています(図表1)。

災害を引き起こす外力に対し、地域社会はその影響を受けやすい脆弱な条件や要素を地域特性に応じて抱えています。例えば、浸水被害を受けやすい低地、地滑りの危険性がある急傾斜地などの地理的環境です。脆弱性を孕んでいる地域(被害リスクの高い地域)の中の社会的・文化的非均一性(多様性)について、二つの事例を見たいと思います。
図表2の左側は安政南海地震のときの和歌山県の広村(当時)の浸水域を示した地図です。多くの方がご存じのように、濱口梧陵をリーダーとしてこの後に堤防が造られ、昭和南海地震では被害がかなり抑えられたといわれています。その昭和南海地震ときの浸水域を示したのが真ん中の地図です。薄く赤い線で示しているのが広村堤防の名で知られている濱口梧陵が造った堤防です。この堤防があったことによって広村の中心地は守られたのですが、今度は地図の左下の江上川の方に波が集中し、その流域で22名の方が亡くなりました。地図の真ん中あたりに日東紡績と書かれていますが、ここに日東紡績の工場と宿舎があり、亡くなった22名のうち18名がこの工場の関係者ならびにその家族でした。彼らの多くはよそからここに来て働いていたので、土地勘や、津波の危険性、さらには避難についての意識があまり高くなかったのではないかと後になっていわれていますが、実態についてはっきりしたことは分かりません。

右側の地図は、2009年8月の台風9号による佐用町水害で死者が出てしまった場所の一つです。佐用町本郷地区にある町営幕山住宅の住民3家族11名が避難し、そのうち9名が途中で亡くなったという痛ましい事故です。本郷地区は農業を中心とした地域で、高齢化が随分進んでいるのですが、幕山住宅に入っている方は比較的若い家族が多く、同じ町内であっても他からここに住んで町場に働きに出ている人たちがほとんどだったということで、やはり土地勘がなく、地域的なつながりもそれほど強くなかったと聞いています。
このように、同じ地理的な条件・脆弱性を持った地域でありながらも、そこに暮らす人々には決してリスクが均等に配分されているわけではありません。当たり前と言えば当たり前ですが、それに対してどのような対応策を取るか、あるいは取れない場合にはどう改善していくかということが大きな課題だと思います。
災害文化の定義
6年ほど前に出版された『災害対応ハンドブック』という本の中で、私は災害文化の項目を担当しました。6年前なので今では考え方が少し変わってきていますが、文化というものをあえて広義と狭義で定義すると、「一定の地域社会に持続性をもって共有された価値、知識、行動様式およびそれらから生み出された技術やもの、さらには人間関係や組織の在り方」というのが広義の文化の捉え方です。一方、「政治や経済などと並置し、『文化・芸術』というように人間活動の一分野を示すもの」というのが狭義の文化の捉え方です(図表3)。一般的に私たちが生活の中で使っているのは後者の定義かもしれません。
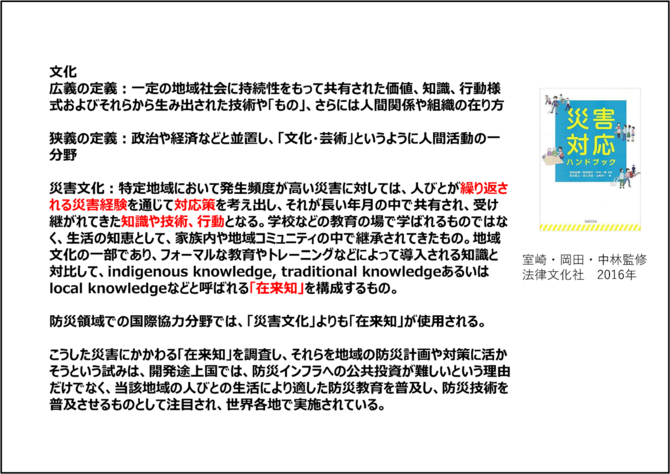
災害文化は、「災害常習地で住民によって共有化された文化的な防災・減災策」と定義されています。人々の生活の中で育まれ継承されるものですが、防災・減災策としての機能については、その母体である生活から切り離して捉えられ、他の地域に移植可能なものと見なされることもあります。もちろん同じ、あるいは類似した自然環境や社会条件の下ではそうした移植が可能です。水害対策で言えば、地域によって水山、水塚、水屋、上がり家と呼ばれる施設があるのがその例だと思います。
Joint Seminar減災・レジリエンス研究教育推進コンソーシアム 第2回共同シンポジウムの他の記事
- 航空気象(ドローンやヘリ等)から見た災害の地域性(講演1)
- 災害文化の特徴とレジリエンスを中心に(講演2)
おすすめ記事
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/03
-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26
-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点
ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。
2026/01/26
-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン
家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。
2026/01/23
-


























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方