SDGsやESGの広がりとともに、社会貢献活動は「やっておいたほうが良いもの」から、企業価値最大化のために「やるべきこと」となってきました。しかし、日本企業の取り組みに対する評価は相対的に高いとは言えません。
日本企業も取り組みをしていないわけではありません。ただ、コミュニケーション戦略に課題がある企業が多いと考えます。整理不足、開示不足、表現不足といった日本企業のESGに関する課題を踏まえると、コミュニケーション担当者が経営企画に近い機能を備える必要があります。
ESGを企業価値向上に結び付けるために大切なことは、ESGの活動を全社的な課題(目標)と捉え、企業文化として継続的なチェックと挑戦を間断なく続けていくことです。
一方、活動の推進役を担うリスクの専門家は、マイナス面を指摘するという役割から、組織から歓迎されないことが少なくありません。ESG活動においては、単なる「否定論者」としてではなく、コミュニケーション戦略のプロセスに不可欠な存在であるという意識を持つ必要があると考えます。つまり、リスク=機会というビジネス感度を持って臨むことが重要です。
本連載は、リスクの専門家を主な対象として、ESG/ERMに関するコミュニケーション戦略のポイントを紹介していきます。
今回は初回なので、ESG課題への取り組みを分かりやすくステークホルダーに発信するための、「攻める」リスクコミュニケーションについて、先行する海外の事例を紹介します。
NFTが森林から山火事を守る!?

911以降で、消防士の犠牲者を最も多く出した2013年アリゾナで起こった森林火災を描いた「オンリー・ザ・ブレイブ」がアマゾンプライムで公開されました。衝撃の実話をベースにした物語で、大きな話題をよんでいます。
アメリカでは近年、高温や乾燥した気候で大規模な山火事が相次いで起きています。テキサス州やアリゾナ州などでは40度を超える高温が報告されており、国立気象局は全米28州で高温警報などを発令する事態になっています。
そんな中、シリコンバレーのあるハイテク企業のYMLは、9月にカリフォルニア州の森林を守るためのNFTプロジェクトを立ち上げました。FIREWATCH と呼ばれるこのプロジェクトは、山火事を防ぎ、カリフォルニア州の森林再生を促進することを目的としています。
ユーザーはプラットフォームで、100ドルから 1万ドルまでの「カリフォルニア州のさまざまな地域を表現したNFTポップアート」を購入することにより、デジタルアートを所有できるようになります。
このプロジェクトで集まった全収益と二次販売の25%が、森林再生に取り組む非営利団体「One Tree Planted」に寄付されます。One Tree Plantedの創設者兼チーフ環境エバンジェリストであるマット・ヒル氏は、「私たちは皆、環境保護と気候変動対策に果たすべき役割を担っており、YMLの革新的な活動を賞賛しています」とAdweek誌の取材にコメントしています。
YMLが、このプロジェクトを行った背景には、NFTが仮想通貨(ビットコインやイーサリアム)の発掘に、大量の電力が使われるとして「環境に負荷を与える」と世の中から、しばしば揶揄されることがあるからだと考えられます。このプロジェクトは、NFTに関するイメージに、ポジティブな変化を促し覆そうとしている攻めた「リスクコミュニケーション」の参考になる事例といえます。

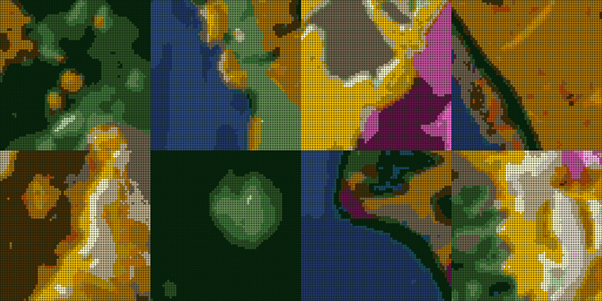





































![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方