連載
-

職場の熱中症対策
5月6日は立夏、夏の始まりです。政府では、毎年5月1日から9月30日までの期間に「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しています。地球温暖化の影響もあり、職場における熱中症による死傷者は年々増加傾向にあります。令和4年における熱中症による休業4日以上の死傷者は805人で、うち死亡者は28人となっています。事業者は、従業員に対して、労働契約に基づく安全配慮義務を負っており、従業員の命と健康を守るための対策を適切に行うことが求められます。熱中症による死傷災害を防止するにあたっては、主に次の対策の実施を徹底することが大事です。
2023/05/09
-

BCP事務局の個人スキルを高める訓練とは?
経営層の期待と裏腹に、危機管理担当者の多くがBCP 訓練の効果に不安を抱いています。災害時の状況を組織的に確認し、足りない点を明確にするのには役立っても、担当者自身の個人スキルを上げるものではないと感じるからでしょう。実は、この部分に焦点をあてたのがいわゆるモックディザスタ訓練です。今回はその進め方を説明します。
2023/05/08
-

今こそJアラート発動時の企業対応を考える
北朝鮮によるミサイル発射実験が続いています。昨年2022年には弾道ミサイルなどの発射回数は40回近くに上り、今年もペースは落ちそうにありません。4月13日には、Jアラートを通じて、発射されたミサイルのうち1つが北海道周辺に落下するとみられるとの情報が報じられました。今回はJアラートへの対応について考えてみます。
2023/05/02
-

サイバー空間の脅威に取り組む米国政府の戦略とは
サイバー空間の脅威が深刻化し続けるなか、米国政府は「国家サイバーセキュリティ戦略」を発表した。重要インフラの保護から国際協力の促進まで、国内外でのビジネスに影響を及ぼす脅威への対策についても考察していく。
2023/05/01
-

地震災害で使われる表現
今回は英検の問題に実際に出てきた単語を活用して、地震をテーマにした文章を集めてみました。できる限り、最近の時事ニュースから引用しています。
2023/04/30
-

仕事の学びを個人知ではなく組織知とすることが急務
人材不足が深刻になっている今、必要な人材を確保するという人材リスクが改めてリスクマネジメントの焦点になっている。採用はもちろんのことであるが、すでに雇用している人材の維持も大きな課題である。
2023/04/30
-

危機管理活動が「バカの壁」を突き崩す
企業の経済安全保障対応を阻害する情報の歪み。その発生構造を見ていくと、組織の縦割り問題に行き着きます。端的にいうと、全体最適思考の欠如。この弊害は欧米型企業より日本型企業のほうが現れやすく、ゆえに組織内の危機管理、ガバナンス担当部門の活動がより重要です。情報収集分析体制の強化に向けていま企業がなすべきことは何かを論考します。
2023/04/27
-

トレッキングポールに頼らない転倒・滑落対策は?
メリットとデメリットのどちらをとるかは、その時々のさまざまな条件に応じてケースバイケース。ハルトがトレッキングポールを持たないのは、いまの自分にとってはメリットよりデメリットが大きいと判断したからです。が、歩きやすさや転倒防止のメリットをただ捨ててしまうのもまたリスク。今回はハルトが考えた代替の工夫を紹介します。
2023/04/20
-

やまじ風――4月の気象災害――
岡山から松山行きの列車に乗って瀬戸大橋を渡り、香川県を経て愛媛県に入ると、間もなく進行方向左側の車窓に、屏風のようにそそり立つ急斜面が迫ってくる。四国山地のいちばん北側に位置する法皇(ほうおう)山脈の北斜面である。それは中央構造線の断層崖(だんそうがい)であり、標高差は約1000メートル、平均勾配はおよそ3/10にもなる。目に映る印象としては断崖絶壁のように感じられる。
2023/04/18
-
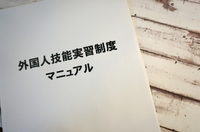
「外国人技能実習制度」廃止をめぐる議論
出入国在留管理庁は、令和5年4月10日に開催された「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第5回)」で提示された中間報告書(たたき台)を公表しました。中間報告書では、「技能実習制度を廃止し、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度の創設を検討すべき」とされており、今後の外国人技能実習制度の在り方について様々な議論がなされています。
2023/04/18
-

『フィッシングによる個人情報等の詐取』に注意!!
フィッシング詐欺とは公的機関や金融機関、ショッピングサイト、宅配業者等の有名企業を騙るメールやSMS(ショートメッセージサービス)を送信して、正規のウェブサイトを模倣したフィッシングサイト(偽のウェブサイト)へ誘導し、IDやパスワードなどの認証情報や個人情報などを入力させ詐取する手口です。
2023/04/17
-
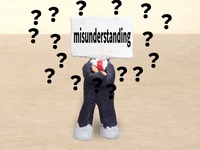
緊迫度を読み違う企業に欠けている姿勢
前回の掲載以降も、グローバル環境に数々の動きがありました。外交上の対立と経済は別だという時代が終焉に向かっているのは明らかで、もしまだそのような事態ではないと思えるとしたら、ことの緊迫度合いを読み違えている可能性が濃厚です。今回は、なぜそうした読み違えが起きるのか、それを防ぐにはどうしたらよいのかを論考します。
2023/04/13
-

健康管理に組織をあげて取り組む時代
健康経営は、企業が従業員の健康管理に投資することによってそのパフォーマンスを高め、結果として業績やイメージの向上につなげるものです。これまで、在宅勤務を中心とするテレワークや職場で増えている高年齢労働者など、さまざまな観点から健康経営を考えてきましたが、最終回となる今回は企業として押さえておくべきポイントを整理します。
2023/04/12
-

学生の4人に1人が就活中にセクハラを経験
あっという間の4月ですが、新卒採用活動の前倒しで大学4年生は就職活動まっさかりです。ここで気になるのが就活ハラスメント。いわずもがな、企業の評判を著しく毀損する可能性があるリスクです。上の世代なら受け流していた言動も、Z世代は「セクハラだ」と認識するかもしれません。今回は就活ハラスメントについて論考します。
2023/04/10
-

水害リスクマップや新たな水害情報をどう利用するか?
昨年末から今年にかけて、水害リスクに関する情報や緊急時に発表される河川関係の情報のアップデートが相次いでいます。今回の記事では、その中から最も注目すべき3つの変化(①リスク情報の充実、②災害時の情報の一元化、③洪水予報の自由化)を取り上げ、企業による平常時や緊急時の水害対策にどう利用できるかを解説していきます。
2023/04/10
-

価値観の違いが引き起こす新興リスク
われわれが日々暮らしている社会では、多様な価値観が存在する。こうした価値観が、社会から批判され、反感を覚えた顧客が報復として購買を中止したり、ネットで意見を流したりすることもありえる。新興リスクとも言える報復リスクを考える。
2023/04/10
-

迷惑動画のSNS拡散に企業はどう対応すべきか?
飲食店での迷惑行為がSNSで動画として拡散される事件が頻発しています。回転ずしチェーン店が集中的に狙われたことから「寿司テロ」と命名され、社会問題化しました。これら一連の迷惑行為に対しいち早く公式見解を出したスシローの対応から、企業としてのクライシスコミュニケーションのあり方を考えます。
2023/04/09
-

一筋縄ではいかないスケジュール管理
余裕を見てスケジュールを組んでもいつの間にか遅れてしまう。そのたびに時間管理の重要性が叫ばれますが、決定的な原因も見つからず、対策は意外と難しいのではないでしょうか。そのためまずは現実を謙虚に受け止め、できることを考えて実行する。そして万一遅れたときの対策も心得ておく。山の時間管理から学びます。
2023/04/06
-

人的資本の価値最大化
近年、企業価値の評価は、財務情報だけでなく非財務情報も重要視されるようになりました。そのなかでも特に人的資本情報の開示が注目を集めています。本稿では、人的資本を核にしたコミュニケーション戦略のポイントをお伝えします。
2023/04/05
-

保育施設等におけるBCP(業務継続計画)について
【大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故など不測の事態が発生しても、重要な業務を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを業務継続計画(Business Continuity Plan)をBCPと呼ぶ】と多くのBCPを説明するガイドにはこのような内容が書かれています。なにやら難しくてスルーしている人が多いのではないかと思います。今回は保育BCP初心者の方向けに発信いたします。
2023/04/04
-
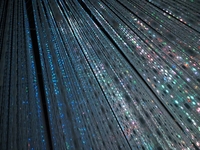
量子コンピュータとサイバーセキュリティ
現代のスーパーコンピュータをも凌駕することが期待されている量子コンピュータが、サイバーセキュリティにもたらす未来と人々の期待について、脅威としての側面から考察していく。
2023/04/04
-

セクハラとメンタルヘルスの関係性
労働災害というと長時間労働による過労死などがすぐに思い浮かぶかと思います。しかし、セクハラが原因で精神疾患を発病した場合でも、労災として認定されることがあります。そこで、今回は、「セクハラによる精神障害と労災の関係」について、元刑事の社会保険労務士が解説します。
2023/04/03
-

現時点で考えるべき3つのポイント
対話型の人工知能(AI)「チャット(GPT)」の活用が急速に広がっています。一方で、企業の間では、業務での利用を制限し始める動きも出てきています。今回はチャットGPTのリスクを考えてみます。
2023/03/30
-

様子見を決め込む企業が直面しているリスク
前回は西村経済産業大臣の発言を引用し、経済安全保障に関して企業が大きな経営判断を迫られる状況にあることを語りました。特に様子見を決め込んでいる企業は、大きな分岐点に差し掛かっています。今回は経済安全保障をめぐって企業にどのような問題が発生し、課題となっているのか、どのようなリスクが迫っているのかを検証します。
2023/03/28
-

アメリカ、カナダで公用端末での使用を禁止
世界150カ国、10億人以上の利用者がいる中国系動画投稿アプリ「TikTok」。いまやメインユーザー層が30代となって利用方法も多様化し、企業がPR動画として活用することも増えています。一方、今年2月末、ヨーロッパ先進諸国に続き、アメリカとカナダでも政府が支給する携帯端末からTik Tokを削除し、使用を禁じるように命じるなど、欧米政府機関では相次いで利用を制限する動きが広がっています。
2023/03/28











![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)





