2025/05/07
防災・危機管理ニュース
ごみ処理施設やごみ収集車で、スマートフォンやモバイルバッテリーなどに使われるリチウムイオン電池による火災が相次いでいる。別のごみに混入し、強い衝撃が加わることで発火するケースが多いとみられる。環境省は、家庭から出される全てのリチウムイオン電池の回収体制を構築するよう、全国の自治体に要請した。
環境省によると、2023年度にごみ処理施設やごみ収集車などで起きたリチウムイオン電池に起因する火災は8543件。前年度の約2倍に増え、過去最多となった。リチウムイオン電池を使用する製品が多様化していることなどが背景にある。
国立環境研究所の試算によると、自治体のごみ処理施設でのリチウムイオン電池による火災の被害額は、21年度は少なくとも100億円程度に上ったという。火災で施設の稼働が停止し、ごみ処理に影響が出るケースもある。
リチウムイオン電池の分別回収を行っている市町村は23年度の時点で全体の約75%にとどまる。環境省は今年4月、分別回収と適正処理の徹底に向け、新たな方針を示した。他のごみとの混入を防ぐため、ごみステーションや戸別での分別回収を基本とし、回収ボックスとの併用などを進めるよう自治体に要請。電池切れの状態にし、発煙・発火のリスクを低減させてから捨てることについて住民への周知を求めた。
大阪市は23年度、市内10カ所に回収ボックスを設置。膨張・変形した電池は窓口で職員が直接受け取る。24年度には電話予約による戸別回収も始めた。同年度の回収量は5トンを超えたという。
また、環境省は25年度、インターネット通販サイトで購入した海外製のモバイルバッテリーなどの回収に関する実証実験を行う。耐用年数が近づいた製品について、サイト側が購入者に通知し、回収する仕組みを検証。同省担当者は「リチウムイオン電池や使用製品は小さく、家庭内にたまりやすい。排出の利便性を高め、回収量を増やしたい」と話している。
〔写真説明〕ごみ処理施設で起きたリチウムイオン電池が原因とみられる火災=2023年2月、愛知県豊田市(同市提供)
(ニュース提供元:時事通信社)

- keyword
- 火災
防災・危機管理ニュースの他の記事
おすすめ記事
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/03
-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26
-







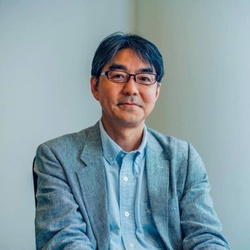

















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方