2012/09/25
誌面情報 vol33
寄稿 ベティー A・キルドー氏
米国危機管理コンサルタント
東日本大震災では、サプライチェーンの寸断により、国内外の多くの企業の事業が中断する事態となった。 米国で 20 年以上にわたり、危機管理コンサルティング業に従事するベティー A・ キルドー氏から、サプライチェーンのリスク管理手法について、本誌への寄稿をいただいた。
■世界に BCP を再認識させた震災
日本を襲った津波と地震から 1 年以上が過ぎた 2012 年6月5日、青森県三沢港から沖合に流され たとみられる 66 フィートの浮桟橋が、太平洋を渡 り米西海岸の岸部に漂着した。津波により流され何 千マイルも離れた陸に上がった漂着物は、震災が世 界規模で長きにわたって甚大な衝撃を与えたことを 再認識させた。また、将来起こり得る大規模災害や 業務リスクに備えて、十分に準備を整える必要を考 えさせるきっかけにもなった。
今後の災害に対応していく上で、企業の考え方、 さらには、顧客(※ここでは主に最終メーカーであ る企業) 、ビジネスパートナー(協力業者) 、ステークホルダーとの関わり方を変えていくことが重要と なる。これは、サプライチェーンの BCP(事業継 続計画) についても当てはまる。 顧客とサプライヤー の連携は、災害後の業務継続、もしくは早急な業務の回復を可能とさせるからだ。
■サプライヤーと顧客の協力関係
顧客とサプライヤーの理想的な関係は、互いに信 頼し合い戦略的なパートナーシップ(協力関係)※ を構築することだ。顧客とサプライヤーが、互いに BCP とリスクマネジメントの取り組みに協力した時、サプライチェーン内のすべての関係者に有益 な効果をもたらす。仮にこれまでの顧客とサプライ ヤーの関係が、協力的というよりはむしろ敵対し合 うビジネス関係であったとするならば、これから協 力的な関係に転じるには、 努力と忍耐が必要となる。
しかし、長い目で見れば、十分に努力をするだけの 価値があることだ。パートナーシップは、業務リス クを減らしたり、サプライチェーンの管理をより容 易にするなど、 生産的で有益な関係へと進歩させる。
| パートナーシップ(協力関係) :相互の信頼関係。情報の開示性、リスクと利益を共有する取引関係。競争優位を生み出し、結果、双方もしくは全体にとって個人で遂行するよりも高い業績をもたらす関係 |
自社の役割が、顧客かサプライヤーかどちらであ れ、サプライチェーンの主要な協力業者として機能 しなければならない。それは国内外の全ての協力業 者が共通の目標を持つ戦略的パートナーとして認識し合うことから始まる。顧客と接するように、サプ ライヤー、運送会社、在庫会社、受託業者など、すべての協力業者と良好な関係を築き上げなければならない。
顧客の観点から事業継続の要求に注目しがちだが、サプライヤーにもさらにその下請けがあり、そこには様々なリスクや事業継続の要求がある。顧客 とサプライヤーが、 事業継続の目標について議論し、 互いに事業継続の戦略や計画、課題を理解し合うた めに、一緒に会議を行ったり計画をつくることはと ても価値がある。
BCP の策定過程での協力は、より実行力のある 事業継続戦略の土台となる。敵対関係のないサプラ イチェーン内の取り組みは、自社と協力業者に良い 影響を及ぼし、災害直後でも事業を継続、もしくは 早急の回復を可能とさせる。 その際、 サプライチェーン内で情報とアイデアを共有することが不可欠とな る。自社だけでなく、協力業者のニーズも考慮しな ければならない。一緒に、問題の解決策と今後の計 画策定を行い、お互いに役立ち、費用対効果の良い 軽減と復旧戦略を作ることは十分に可能だ。
■情報の可視化
互いの協力体制によるサプライチェーンの継続が、すべての関係者の利益になるためには、サプライヤーと顧客の両者、もしくはサプライチェーン内 のすべての協力業者が、それぞれ直面するリスクを 開示し、リスクの管理法についても情報を共有する ことが重要となる。メーカーに直接、納品をするサ プライヤーは、より下層のサプライヤーの持つ脅威 まで明確にすることが必要だ。
協力業者に対しては、あらかじめ「相手に期待す ること」を伝えるとともに、反対に「相手が自社に 期待できること」 を明確にしてもらうことが大切だ。 これを実現する基本的なステップとして、サプライヤーは、企業情報に事業継続力について掲載するこ とが求められる。それにより、将来の顧客が情報を 入手しやすくなる。また顧客は新規契約のサプライ ヤー選定時に価格と質以外の能力について比較することが必要になる。
実効力の高い事業継続の関係は、顧客とサプライヤーが協力することで達成される。顧客は、ほかの主要な業績評価指標に合わせて、事業継続の達成度 の評価の基準を策定した方がいい。常時、設定した 目標を達成しているサプライヤーや、基準以上の業績を上げたサプライヤーには、報奨を与えることも できる。
サプライヤーは、顧客の事業継続の目標と要求に ついて精通していなければならない。その前提として、顧客と高い信頼関係を築き、普段から事業継続 について情報交換できるようなオープンな関係にな る必要がある。 ?
サプライヤー間において、事業継続はますます核 となるビジネス手法、重要な要素として受け入れら れている。もし企業が、事前に顧客もしくは、保険 会社、投資会社、規制機関、他のステークホルダーから事業継続について取り組みが求められていない としても、遅かれ早かれ BCP についていつか問われる時がくる。情報伝達は常にオープンにしていなければいけない。
サプライヤーの継続目標が不十分である時、顧客は重要なサプライヤーに対して、改善が必要な部分 を直ぐに正すチャンスを与えることができる。それ により、速やかに継続目標について議論することが できるようになる。湧き上がった問題を解決するた めには、共同での取り組みを導くプロセスを作らなければならない。
顧客が、サプライヤーに対して事業継続力への期 待をきちんと伝えることが重要である一方で、顧客が計画策定の情報やアドバイスを提供することは、 双方の協力において大切な要素だ。
サプライヤーもしくは協力業者は、BCP を策定 していなかった場合、対話しなければならない。各 サプライヤーにおいては、自社の事業継続のプログ ラムに責任を持たなければならないが、計画に対する顧客の要求は、事業継続の戦略を実行するための 推進力となることが多い。 顧客と契約を更新する際、もしくは要求に対して応える時、新しく追加された 事業継続の要求を知り、顧客の立場にたって考えな ければいけない。サプライヤーが顧客よりもだいぶ 小さく、ビジネス継続のために限られたリソースしかないこともある。事業継続の目的が顧客のニーズを満たすサプライヤーにとって、顧客のニーズや要求について顧客に尋ね、その情報を既存のBCP の改訂するときに考慮することは大切なことだ。
■サプライチェーン内の共有
災害に習い、経験した失敗は共有すべきだ。災害 の影響を受ける協力業者の損害を減少させる、相互 に有益な事業継続の取り組みを構築するために下記 のステップを考える必要がある。
・相互の利益を目標として BCP を見る
・事業継続の基準と方針を共有する
・協調的で統合された事業継続戦略と計画を発達させる指導するワークショップを開く
・計画のテンプレートと様々なツールを共有する
・災害や業務を妨げる事業が発生した時に、コンテンジェンシープランを発達させる
・サプライチェーンを巻き込んだトレーニング、 エクササイズ、テストを実施する
・問題発生後だけでなく、常時情報の可視化する
提供するものがサービス、製品に関わらず、どの組織でも顧客側でありサプライヤー側でもあることを頭に入れるべきだ。しっかりした計画を持ち、災害発生時でも互いの役割、責任を決め、重大な業務 を妨げる事業に備え、情報の見える化をしているサプライチェーンの協力業者は、互いの業務能力をサプライチェーン内すべてに役立てられる。パートナーシップに必要な信用力を高めるには、努力が必 要で時間もかかる。しかし、協力的な顧客とサプラ イヤーのパートナーシップは、次の災害の有無に関わらず、利益を生み出す。
誌面情報 vol33の他の記事
おすすめ記事
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/03
-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26
-



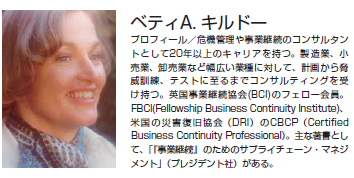






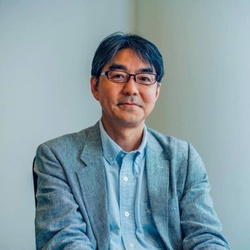
















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方