2020/01/24
危機管理の神髄
熱すぎて扱えない
正午頃、ロタンズは環境保護局から、現場コーディネーターという形で、ブレット・プロウを私の元へ差し向けた。プロウは環境保護局(EPA)のファーストレスポンダーで、やせて背の高い40代のエンジニアであり、赤と白と青で“EPA緊急事態対応”と書かれたロゴの付いた明るい青色のポロシャツを着ていた。私は彼にコン・エディソンの大気データの話をしてEPAのデータについて質問をした。
彼は混乱しているようだった。「何のことですか?」
「あなた方は何を持っているのか?」「現場の特性に関するデータはありますか?」
「いえ、われわれはあなたの現場の特性を分析することはしていない」「われわれは市を支援するためにここにいるのであり、われわれに何をしてほしいのか?」
「見てください」「現場周辺の大気に含まれるいかなる毒物も分析する必要があります」
「それをいつやり、いつまでやりたいのか」と彼は聞いた。
「今から1日24時間、永遠にやるのではどうか」
「永遠とは何のことか?」
「6週間、6カ月、6年、分かるものか」「実行し、実行し続けるだけだ」と私は言った。
数分後、彼は群衆を押し分けてきて親指を立てる仕草をした。「データがある。今こちらへ向かっている」
1時間がたったがデータは現れない。それが2時間になり、依然として来ない。
私は安全担当者とそのデータを求めてあらゆる場所を必死に探し始めた。間違いなくEPAだけでなくもっと多くの機関が現場で大気と残骸物のサンプルを採集していた。ワールドトレードセンターの現場の空気が危険なものであるかどうかを教えてくれるのはデータだけである。災害発生後30時間にもなるのに良いデータがないというのは一体どうしたことなのだ?
午後はあっという間に過ぎて、ブレットからは何度もそのたびに違う言い訳を聞くことになった。EPAはしかるべき担当者にコンタクトできない。サンプリングの装置に不具合があった。サンプルが試験所に届くのに遅れがあった。どの報告にも最後には「1時間で来る」という決まり文句があった。
午後5時頃やっとニュージャージー州ジャージーの1カ所、ブルックリンの2カ所からの大気データを記載した1枚の紙を振りかざしながらプロウが到着した。ワールドトレードセンターの現場あるいはマンハッタンの結果を見たいと言ったら、何も見せるものを持っていなかった。
「いやそこのサンプルは採っていない」と言った。
彼らは一体何をしていたのだ?
私は当惑した。アメリカ合衆国環境保護庁(EPA)に15年間勤務した経験からすれば、EPAは調査の手綱を握り采配を振るっていて当然だからだ。何といってもEPAは大気浄化法の創造者であり保護者なのだ。EPAはアメリカ合衆国の全土にわたる大気の質に関する基準を定めて、30年以上の間違反者を逮捕してきたのだ。今では文字通り、大気の抽出検査について本を書いたEPA当人が、そのやり方を知らないように見えるのだ。しかしすぐに分かるように、EPAの誰かが、どこかで大気の検査をしていたのだ。
呼吸をしても安全な大気
翌日EPAのクリスチーン・トッド・ホイットマン長官は「ワールドトレードセンタービルの崩壊によって放出されたかもしれないある種の物質に対する短期間の低レベルの暴露が健康への深刻な影響を与えることはないだろう」と表明した。ホイットマン長官はさらに「ニューヨーク市の大気中には危険なレベルのアスベストの粉塵があるようには見えない」と心配を取り除く発言をした。
仮にEPAがそうした主張の根拠となるデータを持っていたとしても、彼らはそれをニューヨーク市には見せていなかったのだ。EOCの中では、ニューヨーカー(ワールドトレードセンターの現場で作業をしている人たち、わが家やダウンタウンの仕事に戻りたがっている人たち)を安心させるよう、そして復旧を最優先にするようホワイトハウスがEPAに指示をしていたのだという噂が流れた。
影響はすぐにあった。わが保健局のチームはすでにP100指令を現場に発し、シフトチェンジの間にチラシを配布し、作業者にはP100が新たに必要になることとその入手方法を説明した。EOCでは、われわれは日次機関報告会でP100指令のリマインダーとともに毎回の報告を行った。しかしEPA長官の表明の後、ニューヨーク市消防とニューヨーク市警察はわれわれをこれらの会議に呼ばなくなった。彼らは、EPAが大気は問題ないと言ったのに、自分たちの保健局が作業者にそれらのマスクを装着するように指令するのは何故なのかを知りたがった。当然の疑問である。
われわれは証拠を必要とした。誰もそれを持っておらず、通常であればそれらのことに責任のある全ての人が突然関与しなくなってしまったので、自分たちで行って手にするしかなかっただろう。
(続く)
翻訳:杉野文俊
この連載について http://www.risktaisaku.com/articles/-/15300
おすすめ記事
-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-








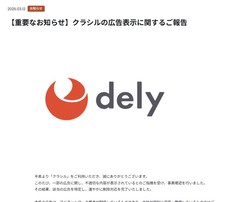


















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方