自然災害
-

溺れているペットの助け方
これから雨が多い季節になってきますが、洪水などで流されたり、岸に上がれなくなった動物を見つけたら、あなたはどうしますか?上記のビデオは狭い川幅の濁流における勇敢な警察官による救助でしたが、実際に、このように何も準備していない状態で遭遇することが多いのかもしれません。 しかし何も考えず、準備もせずに助けにいくと自分の身の危険を守れません。どうやって助けると安全なのか?どのような救助方法があるのか?どの程度の道具が必要で、どんな訓練が必要なのか?を知っておく必要があります。‘濁流に流された動物を助けるには次のことが必要です。
2017/06/28
-

流通7社が初めて指定公共機関に
内閣府は27日、セブン&アイ・ホールディングス、イトーヨーカ堂、セブン-イレブン・ジャパン、イオン、ローソン、ファミリーマート、ユニーの流通業7社を7月1日付で災害対応の指定公共機関に追加指定すると発表した。流通事業者の指定は初めて。
2017/06/28
-

文科省、現・基本施策下で津波観測成果
文部科学省が中心となっている政府の地震調査研究推進本部は27日、「新総合基本施策レビューに関する小委員会」の第3回会合を開催。現行の地震調査研究の原則となっている「新総合基本施策」における津波予測などの実績について評価が行われた。
2017/06/28
-

石川県で最大20mの津波予想を報告
国土交通省は27日、社会資本整備審議会河川分科会の第54回会合を開催。日本海に面した北海道、富山県、島根県の津波浸水想定の設定や土砂災害防止対策基本指針の変更などを承認した。また石川県では最大20mの津波が想定されることが報告された。
2017/06/28
-

医療機関向け業務継続力強化サービス
富士通総研は15日、病院などの危機対応能力を高めることを狙いとし、災害時に医療機関の重要業務を迅速に再開するための業務継続力強化サービスを開始すると発表した。大規模な災害が発生した際、各病院が院内だけでなく行政や医療団体、近隣病院、DMAT、取引先などと連携。迅速な対応・判断をすることで、医療サービスを継続的に提供できるよう支援する。同社が保有する1000社以上の事業継続コンサルティングの実績や知見をベースに、各病院の現状の課題に対応したサービスを提供する。
2017/06/28
-

戸別受信機の標準仕様策定で普及促進
総務省は22日、「防災行政無線等の戸別受信機の普及促進に関する研究会」の第4回会合を開催。報告書のとりまとめを行った。戸別受信機の普及促進に向け、標準的な仕様や防災行政無線と簡易無線の接続規格を定めるなどコスト削減を図る。
2017/06/28
-
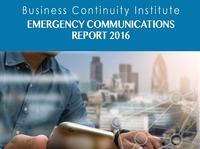
緊急事態下でのコミュニケーションの実態
BCMの専門家や実務者による非営利団体BCI(注1)は、緊急連絡システム(注 2)のプロバイダーの一つである米国のEverbridge 社(注3)と共同で、2016 年 12 月に「Emergency Communications Report 2016」という調査報告書を公開した。
2017/06/27
-

南海トラフ観測、システム3案で議論
文部科学省を中心とした地震調査研究推進本部は26日、「海域観測に関する検討ワーキンググループ」の第6回会合を開催。「次期ケーブル式海底地震・津波観測システムのあり方について」と題した中間とりまとめの骨子案を示した。高知県沖から日向灘にかけての南海トラフ南西部海域観測のためのシステムについて、インライン方式と拡張分岐ノード方式による3つの案から今後検討を進める。
2017/06/27
-
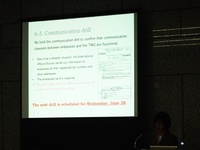
外務省と都、在京40大使館に防災説明会
外務省と東京都は26日、今年度「在京大使館等向け防災施策説明会」を都庁で開催。40カ国・地域の大使館から53人が出席した。都から各国大使館に災害時の連絡や情報交換について説明。28日に都と大使館による通信訓練を行うことも報告された。
2017/06/27
-

3.3cm厚の折りたたみヘルメット
ミドリ安全は16日、折りたたみヘルメット「Flatmet」(フラットメット)を開発し、5月26日よりインターネットなどで販売を開始したと発表した。収納時の厚さは3.3cm。厚生労働省の保護規格「飛来・落下用」の国家検定に合格している。
2017/06/27
-

グローバルリスク報告書2017年版を読み解く
「第12回グローバルリスク報告書2017年版」が今年1月に世界経済フォーラム(通称:ダボス会議)で発表された。世界の学術界、政府、国際組織、NGO、企業などのリーダーにグローバルリスクについてアンケート形式で調査したものを反映させており、今後10年間に世界で発生するリスクの可能性と影響度を評価している。今年の調査では、発生可能性が高いグローバルリスクのトップは「異常気象」。同報告書の編集に携わる、マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズのグループ会社で、保険仲立人大手のマーシュブローカージャパン代表取締役会長の平賀暁氏に、今年の報告書のポイントを解説してもらった。
2017/06/26
-

40市町村が火山避難計画完全策定済み
内閣府は23日、火山対策防災会議の第6回会合を開催した。内閣府など関係省庁の火山に関する取り組みのほか、40市町村で避難計画が策定済みであること、海外の事例の調査などが報告された。
2017/06/26
-

海水淡水化で水飢饉を救う
父島での救援活動で使われた海水淡水化装置(提供:水資源機構)大渇水の小笠原村・父島を救援水がなければ人は生きていけない。とりわけ自然災害時に求められるものはライフラインの確保、なかでも水の確保である。同時に、そのための英知である。
2017/06/26
-

五輪機に東京の防災力を世界に発信
東京都は23日、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた「ホストシティTokyoプロジェクト」を開始すると発表した。防災力など東京のストロングポイントを、五輪を契機に世界に発信。大会後も観光客や投資を東京に呼び込むことを狙う。
2017/06/23
-

熊本地震関連企業、BCP3割が策定
内閣府は16日、「企業の事業継続に関する熊本地震の影響調査報告書」を発表した。2016年の熊本地震被災地の1255社、被災地と取引のある全国の756社の2011社が回答。BCP(事業継続計画)について約3割が策定。大企業は全体の約7割が策定しているが、中小企業は約1割にとどまっている。
2017/06/23
-

東京東部洪水時、移動困難21万人残留も
内閣府を中心とした政府の中央防災会議は22日、防災対策実行会議の「洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討ワーキンググループ(WG)」の第4回会合を開催。主に墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区の東京都の江東5区における洪水時の広域避難について話し合われた。人口の約8%にあたる長距離移動困難者21万人については屋内安全確保などで5区内にとどまることも想定。5区外へ151万~172万人が避難すると見込む。
2017/06/23
-

水を入れるだけ、にぎらないおにぎり
尾西食品は15日、水やお湯を入れるだけで、三角おにぎりができる「えっ!?にぎらずにできる携帯おにぎり」を販売すると発表した。手を汚さずに作り、素手で持たずに食べられる。かさばらないので備蓄する場合も少ないスペースで済む。
2017/06/22
-

スーパー堤防整備へ開発協力促す
国土交通省は20日、「高規格堤防の効率的な整備に関する検討会」の第2回会合を開催。とりまとめの骨子案を提示した。「スーパー堤防」と呼ばれる高規格堤防の今後の整備の方策について、街づくりを行う共同事業者へのインセンティブ導入のほか、コストや工期縮減などを盛り込んだ。
2017/06/21
-

平時から気象台と自治体の防災協力を
気象庁は20日、「地域における気象防災業務のあり方検討会」の第2回会合を開催。地域にある気象台の防災への取り組みについて方向性を提示した。平時は地方自治体との信頼関係構築や気象への理解を深め、緊急時には情報共有強化や気象台職員によるチーム派遣といった自治体との協力を行う。
2017/06/21
-

仲間を助ける訓練は要救助者救出訓練につながる
私がレスキュー隊現役時代、救助年間訓練計画の一部ですが定期的に、 下記のような救助救急訓練を行ってきました。
2017/06/21
-
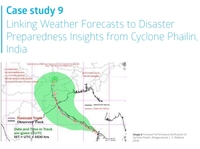
科学技術は災害リスクをどれだけ軽減できるのか?
本連載の 5 月 16 日掲載分の記事(注 1)では、アジア各国での災害リスク軽減における科学技術の活用状況に関する報告書を紹介したが、今回紹介する報告書『Science is used for disaster risk reduction: UNISDR Science and Technical Advisory Group report 2015』は、国連国際防災戦略事務局(UNISDR)の科学技術アドバイザリーグループ(STAG)が、災害リスク軽減に科学技術が活用されている事例を世界各国から集めた上で、提言をまとめたものである。
2017/06/20
-

BCP策定率は大企業6割、中堅3割
政府は16日、「防災に関してとった措置の概況 平成29年度の防災に関する計画」(防災白書)を閣議決定し国会に提出した。今年度の白書では2016年の熊本地震での教訓が多く盛り込まれたほか、被災企業の事業継続への取り組みも記載されている。また大企業と中堅企業のBCP(事業継続計画)策定状況では中堅企業では大企業の半分である約3割にとどまっていることも指摘している。
2017/06/20
-

防災科研など、防災AI活用で研究会議
防災科学技術研究所、情報通信研究機構、慶応義塾大学環境情報学部・山口真吾研究室は5日、防災・減災分野への人工知能(AI)技術の導入と普及のため共同研究会議を設立したと発表した。AIで災害時に膨大なデータから役立つ情報を入手・分析を行えるようにするほか、防災訓練を効果的に行うためのガイドライン作りも目指す。
2017/06/20
-

【第9章】 危険物/テロ災害対応 (2) (後編)
それでは一体、市民レベルではどのようにして危険物・テロ災害に備えればよいのだろう? まずはじめに読者の皆さんに認識して頂きたいのは「危険物・テロ災害から身を守り、生存することは可能だ」ということである。このことは自然災害へ備えることと同意義で是非、第1章の「災害準備編~本当に準備するべきことは!?~」を見直していただきたい。
2017/06/20
-

総務省、災対経験豊富な自治体職員登録
総務省は被災地へほかの地方自治体から応援職員を派遣する仕組みの構築を行う。16日、「大規模災害からの被災住民の生活再建を支援するための応援職員の派遣の在り方に関する研究会」がとりまとめた報告書が高市早苗・総務大臣に提出された。報告書には被災市区町村を支援する自治体を決める「対口支援方式」(カウンターパート)や災害対応が豊富な自治体職員を総務省に登録する「災害マネジメント総括支援員」制度の導入が提言として盛り込まれた。
2017/06/19


















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



